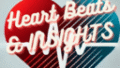強心薬と昇圧薬について、私自身が実際に行っている使用方法を紹介しようと思います。
特に強心薬は、慢性心不全の急性増悪をイメージした使い方になります。
心筋炎や急性広範囲心筋梗塞などの場合には、一気に医療資源を投入する必要があるので、下の記載とはことなり、ドブタミン 5γ → 10γ、そもそもドブタミンが必要なくらいなら、IABP, IMPELLA, VA-ECMOという感じだと思います。時間的に早く完全血行再建できた広範囲心筋梗塞ならともかく、12時間以上の時間が経った状態できた心筋梗塞や心筋炎の場合には、強心薬が必要なら、少なくともIABP、特に心筋炎ならVA-ECMOは、基本入れる前提でいいと思います。
あくまで私個人のルールですので、別の意見もあると思いますが、参考にはしていただけるかと思います。また、循環器科のない病院で、これら薬剤を使用するとなったときに、一応このまましていただいても大丈夫という内容にはしています。なにせ、私が2025年時点で10年以上変わっていないマイルールになります。
強心薬は循環不全で使用しますが、循環不全をどのように判断するのかに関しては、別記事を参照いただければと思います。今回は、具体的な使用方法にしぼって記載します。
補足として、抗不整脈薬のアミオダロンとニフェカラントについても記載しました。ちなみに、個人的には、重症心不全であればあるほど、ニフェカラントfirstが良いと考えています。
強心薬の増量時の注意点を先に記載すると、致死的な不整脈です。 強心薬の増量とともに明らかに心室性不整脈が悪化する人がいますので、必ずモニターで不整脈の状況を把握しましょう。心室性不整脈の対応のため、補足でアミオダロンとニフェカラントについても記載しました。
具体的な強心薬の使用方法
各薬剤の具体的な使用をみていきます。 (投与量単位はγ。γ=μg/kg/min)
①ドブタミン
2γ程度から開始し、1γずつ増量。4-5γ程度にとどめる 。 減量する時には、1γないし0.5γずつを3‐6時間程度あけて減量していく。特に2γあたりから慎重に減量する。
感染性ショックなどのときには、一時的に10γ程度まで使用することもある。
増量するかどうかは、倦怠感などの自覚症状、capilary refilling time (CRT)、尿中Na,K,Clなどの所見を確認しながら、30-60分程度で、「疑わしきは増量」で積極的に1γずつ増量していく感じでよい。 ただ、ドブタミン単独でどんどん増量というより、ドブタミン3γ程度で循環不全の症状・所見が改善しときは、ミルリノンの併用を早期から行うほうがよい。 (単剤増量よりも併用のほうが有効なことが多い) 敗血症性ショックなどの時には、サイトカイン ストームにより、心筋が一時的かつ可逆的なスタンニングで低心機能を呈する時があるので、低心機能の場合にはドブタミンの積極的な使用を検討する。
②ミルリノン
腎機能正常であれば、0.1γ程度から使用し、0.05か0.1γ程度ずつ増量し、0.3γ程度までにとどめる。
減量は、0.05γずつ、3-6時間程度の評価時間で判断していく。
慣れていれば、ドブタミンより優先して、ミルリノンから使用開始してもよい。
増量は30分-60分程度の間隔で、自覚症状や所見の改善がなければ増量していく。 腎機能による用量調整が必要で、腎障害があるときには、目安として、投与量(γ)をクレアチニンの値で割った値が大体の目安となる。
ローディングは原則不要で、実際にはあまり行わない。また、決して推奨はしないが、低心機能の電撃性肺水腫に、末梢の抵抗血管の拡張目的で少量のbolus静脈注射が有効なことはある。安全に行くならbolusではなくloading量を投与するのはあり。
腎障害時の具体的な用量(あくまで私個人の方法):
投与γ数をクレアチニンで割った数が目安。開始用量は0.1γなので、Cr 2であれば0.05γ、Cr 4であれば0.025γとなる。 増量する時には、開始用量の半量か同量ずつ増量する。
ミルリノンは腎代謝ではあるが、腎障害性があるわけではないので、心室性の不整脈の出現に注意しつつ、慎重に増量すればいい。
腎機能正常な場合の用量で、ドブタミン 3γ、ミルリノン 0.3γ投与状態で、循環不全の改善がない場合には、機械的なサポートが必要だと覚悟しておきましょう。ドブタミンをひとまず5γまで増量したうえで、機械的なサポートの準備を粛々としていきます。ドブタミン5γ、ミルリノン0.3γで改善していく人もいますが、正直これくらいの用量がいる人は超重症ですので、どちらにしろ移植か、緩和かということになると思います。
③オルプリノン
ミルリノンよりも血管拡張作用が強いとされる。 使用はミルリノンと同じで、ミルリノンと同量であれば、2倍の効果あるため、半量を目安にする。
開始用量:0.05γ。 0.025 – 0.05γずつ増量し、max 0.15γ
腎障害時には、ミルリノンと同様に、Crの値で割った量が投与量となる。
④ドーパミン
心不全の強心薬としては原則使用しない。
ドーパミンは虚血を悪化させたり、後負荷を上げたりする。 特に重症心不全では、後負荷の上昇は、拡張末期圧を上げ、肺うっ血を悪化させるだけでなく、afterload mismatchを引き起こし、心拍出量を減少させるため、最も起こしてはいけない状態といえる。
そのため、ドブタミンに対するアレルギーがある場合などに限定的に使用。使用する際には必ず強心作用と血管拡張作用のあるPDEIII阻害薬を優先的ないし併用で使用する。 (ドブタミンにアレルギーがあってもドブトレックスは大丈夫だったりすることはあるので、アレルギーがひどくない場合には検討する価値はある) ショックを伴う心不全の急性期に昇圧を目的とする場合には、ノルアドレナリンを優先させる。しかし、何らかの理由でドーパミンを使用する場合には、かならず十分な量のドブタミンを使用したうえで、最小限を使用する。
強心薬としての使用量:1.5 or 2γ程度から開始し、4γ程度にとどめる。
基本的に、昇圧するときには、ドーパミンを投与するよりも、ドブタミンとノルアドレナリンを併用し、ドブタミンは循環不全の所見がなくなるような用量に調整し、血圧自体はノルアドレナリンで調整する。
昇圧薬の具体的な使い方
昇圧薬に関しては、心不全とはいったん切り離して、単純にショックに対する昇圧ということでみていただければと思います。
ちなみに、私は昇圧に関してはノルアドレナリン単独で治療開始します。特殊な場合にバゾプレシンを併用するというのが、私の定石です。アドレナリンは、1例くらいしか併用した記憶がありません。
なお、慢性心不全の急性増悪では、基本的に普段より血圧が低下することは少ないので、昇圧薬が必要となることはほぼありません。強心薬だけで十分なはずです。
そのため、昇圧薬がいる心不全の急性増悪の場合には、ただの増悪ではなく、感染性ショック・敗血症性ショックなど、急激な何らかの変化が起きている場合がほとんどです。
そのような低心機能の患者のショック状態の治療には、昇圧薬を準備しながら、ドブタミン(3 -5 γ)・ミルリノン(腎機能正常 0.3γ)を固定量で投与しつつ、血圧の調整はノルアドレナリンで行うという感じで実施しています。
①ノルアドレナリン
昇圧薬としては、基本的にノルアドレナリンを第一選択として使用。
開始用量:0.1γから。0.05γずつ増量し、0.3 – 0.5γ程度まで増量。増量は、10-30分くらいで反応を見て、SBP 80とか、一定のラインをクリアするまで漸増。
おおよそ、0.3γくらいが一つの目安。0.3γで反応があって、もう少し増量したら安定するくらいの感じであれば、単剤0.5γ程度まで増量。 反応がわるく、単剤では無理そうなら、0.3γくらいの段階から、バゾプレシンを併用準備開始。
決して積極的に推奨しているわけではないが、緊急で速やかに使用したい場合。
ノルアドレナリン 1mgを生食100mlに溶解
60分程度の速度で滴下し、ひとまず血圧を上げるということはある。
60分で約100mlを滴下 : 100ml/60分 = 100ml/H 程度で投与していることになる。
患者の体重を60kgとしたときに、この組成であれば、1ml/H = 0.0028γなので、ざっくり0.3γで投与していることになる。
急ぎの場合の投与量としては悪くないとは思う。
②バゾプレシン
単独使用したことはない。
ノルアドレナリン単独では昇圧できないときに併用。
開始用量:0.5単位/ml or 1単位/ml。
個人的には、1単位/mlを超えて使用した経験はないが、文献的には2単位/mlまで使用可能
③アドレナリン
用量により、効果が異なるとされる。昇圧の場合には、α作用を期待することになる。
使用用量は0.1γ開始し、最大0.3γまで。
これらの用量でだいたいの病状には対応できるはずである ただ、それでもどうしても血圧が上がらないときがある。 その時には上限を無視して、ノルアド 1γ、バゾプレシン2単位/mlに、アドレナリン 1γなど、やらざるを得ないときにはやるしかない。
補足1. ニフェカラントの使い方と致死性不整脈の対応
重症心不全でアミオダロンのローディングを行ってはいけない。 私はニフェカラントの静注からの持続静注が使いやすいと考える。
強心薬投与で心室性不整脈が増えているときには、どうするかですが、心室性期外収縮は健常者であれば無視してもいいくらいの数(10-20%とか)でも、心不全の急性増悪の時には、それでも不安定化することがあったり、特に短い心室頻拍や短いながらも心室粗動が出ているときには、一気に急変の可能性もあります。
このような不整脈がある時には、強心薬をできるのなら越したことはありませんが、減量できるのならそもそも投与していないと思います。そのため、強心薬の維持や増量が必要な時には抗不整脈薬を併用します。 (強心薬を増やして状態を安定させれたら不整脈が減ることもあります) 心室性の抗不整脈お勧めは、ニフェカラントです。これは、Kチャンネル選択的に阻害するため、心機能にほとんど影響を与えません。 特に重症な心不全患者では、一般的なアミオダロンのローディングをすると一気にショック状態になることが多々ありますが、ニフェカラントであれば、静注してから維持用量持続注射しても、血圧は基本的に下がりませんし、心不全の管理自体には特に影響は与えません。 もちろん、投与中に心電図でQT間隔を確認しながら、用量調整が必要ですが、このやり方が非常に有効だと感じています。 繰り返しますが、アンカロンのローディングは危険ですので、循環不全をきたしているような心不全ではしないことをお勧めします。
具体的なニフェカラントの用量
- 静注:1V (50mg)を生食50mlで溶解して、15ml (=15mg)を3-5分かけてゆっくり静注。 速やかに持続静注に変更:0.4mg/kgで開始。 (静注で使用したシリンジをそのまま持続静注で使用。その後に、持続静注を続ける場合には、希釈5V/50ml (5mg/ml)とかにする必要はある)
説明:1回0.3mg/kgを5分で投与。とはいいますが、心室性不整脈で急いでいるときに、この掛け算をして、1V 50mgだからとか計算するのは手間ですし、間違えたら大変です。そんなしょっちゅう使う薬でもないですし。ひとまず50kgとして、15mg投与するというのでいいと思います。私は、そうしていました。
持続の時には、少し計算する余裕があると思いますので、0.4mg/kgを持続投与していけばよいと思います。あまり容量調整はした記憶はありません。
ニフェカラントよりアミオダロンのほうが有効な人もいるので、ニフェカラントにこだわるのもよくはないと思います。併用は禁忌ですが、正直、循環器の超重症領域では禁忌を承知で治療を行うこともあります。
血行動態的にニフェカラントのほうが導入が安全なので、ニフェカラントから入って、アミオダロンに変更か、併用かの判断をしていく感じです。繰り返しですが、この場合のアミオダロンもローディングは不要です。 ただ、アミオダロンに変更するよりも、カリウムの調整(4.8 – 5.5mEq/L)を行ったり、軽い鎮静をかけるためにプレセデックスを使ったり、フェンタニルを使ったり、エビデンスはありませんが、マグネシウムを使ったりして、致死的不整脈の治療をしていました。 完全に鎮静して人工呼吸器にのせることもありました。
また、致死的不整脈というのは、強心薬増量の禁忌になるので、速やかに機械的な循環サポートを導入する必要もあります。
徐脈のために心室性期外収縮が頻発している場合には、頻脈にすることも治療となります。心不全との兼ね合いで右室ペーシングで血行動態が破綻しないなら、普通の体外の右室ペーシングでいいと思います。 体外経静脈ペーシングでは心房ペーシングができるものはなかったと思います。VDDで心房センスできる体外経静脈ペーシングはあったと思いますが。 もし心房ペーシングできるものがあるなら、それに越したことはありませんが、緊急で永久ペースメーカを一時的に心房ペース目的に使用することも可能性としてはなくはありません。推奨してはいません。あくまで可能性の話です。
一度だけ、何をどうしてもどうにもならない完全左脚ブロックでdyssynchronyがあり、致死的不整脈が出ている徐脈の症例に対して、緊急CRT-Dの植え込みをしているのを横目で見たことはあります。
補足2. γ計算の実際
私のγ計算のやり方ですが、まず、ある組成で薬液を作ったときに、シリンジポンプ 1ml/Hの設定としたときに、それは何γの投与量になるのかを計算し、次に、目標の投与γにしたいときに、シリンジポンプを何ml/Hの設定にすればいいのかを計算していくことをしています。
カルテには、
・薬液の組成
・1ml/Hの時のγ数
・初期設定のXml/Hの時のγ数
を記載しています。
γ計算の概略
γの単位は、μg/kg/minです。で、実際のシリンジポンプの設定は、ml/Hです。この違いのため、計算が必要です。
私の場合には、シリンジポンプの濃度から、1ml/Hに設定した時に、何γになるかを計算して、目標とするγ数になるように、シリンジポンプのml/Hを設定するという感じで調整しています。携帯電話の計算機で計算しています。
計算に必要な値としては、
・シリンジ内の薬剤の総量(mg)
・シリンジの液体の量(ml)
・患者の体重(kg)
です。
この数値を使って、まず、1ml/Hあたりの薬剤の投与量(=mg/ml/H)をγ(=μg/kg/min)に変更していくことになります。
ノルアドレナリンを例に計算していきます。
ノルアドレナリン1A (1mg/ml)を5A使用して、生理食塩水 45mlで薄め、体重40kgの患者に使用したとします。
つまり、ノルアドレナリン 5mg, 総液量 50ml, 患者体重 40kg。
ひとまず、1時間当たりの投与量1mlの時の投与量:5mg/50ml/H =0. 1mg/ml/H
γが体重あたり、1分当たりの㎍の投与量になるので、
1mg = 1000㎍, 1時間 = 60分, 体重 40kgで割り込んでいきます。
0.1mg/ml/H = 0.1×1000μg/ml/60min/40kg = 1000/60/40 μg/min/kg/ml ≒ 0.042γ/ml
ということで、1ml/Hの設定師にしたときに、0.042γになります。
シリンジポンプは経験上、当初開始時には、 2ml/H程度以上にはしたいので、2.5ml/Hにすると約0.1γ程度になり、2.5ml/Hで開始、血圧をみながら、1ml/Hずつ増量指示になります。
①γ計算に必要な値:シリンジ内の薬剤の総量(mg)、シリンジの溶液の量(ml)、患者の体重(kg)
求める値:シリンジポンプを 1ml/Hに設定した時に、何γとなるか。(γ=μg/kg/min)
これをまとめると:
ノルアドレナリンを体重 40kgの患者に 0.1γで投与開始する場合:
ノルアドレナリン(1mg)5A + 生理食塩水 45ml,
ノルアドレナリン総量 5mg, 全体 50ml, 患者体重 40kg
5mg×1000÷50ml÷40kg÷60 = 0.042γ
1ml/Hで投与すると0.042γ,
0.1γから開始するには、
0.1÷0.042 = 2.5ml/H
で投与すればよい。
注:カルテには、1ml/Hで0.042γになることと、2.5ml/Hで0.1γ投与することを記載すると他の人にも理解しやすかったり、その後の増減の時にわかりやすくなります
投与開始時のカルテ記載参考:
ノルアド 組成 5000ug + 生食 45ml : 全量 50ml 1ml/H = 0.042γ 開始: 2.5ml/H = 0.1γ
続いて、同じようにドブタミンの規制製剤であるドブポンで計算していきます。
例2: 0.3% ドブポン(50ml,→50ml×0.3% = 0.15g = 150mg)
0.3%ドブポン50ml, 投与する患者の体重70kgとしたとき、
薬剤総量 150mg, 全体 50ml, 患者体重 70kg
150mg×1000÷50ml÷70kg÷60 = 0.714γ
2γから開始したいなら
2γ÷0.714γ = 2.8ml/H
で投与開始して、1γ刻みで増量するなら、1.4ml/Hずつ増量すればよい。