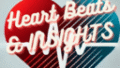- まとめ:
- 慢性心不全急性増悪の治療
- 心不全の治療で、一番重要なことは循環不全の有無を評価すること
- 低潅流所見は身体所見として取るのは結構難しい
- 私が最も重要視する循環不全の身体所見:爪の毛細血管再充満時間(CRT, capillary refilling time)
- 血圧も参考となる指標ではあるが、絶対的なラインはない
- 客観的な参考指標:心エコーによる心拍出量の計測
- 低拍出の評価として心エコーによるVTI(velocity time integral)とVTIの測定方法
- VTIによる心不全のリスク分類(個人的な見解)
- 定性的な評価になるが血液検査では、Na, K, BUN/Cr, AST/ALT/T-bilあたりが参考になる。
- 強心薬を使うと予後が悪くなるという意見は無視でいい。
- 強心薬の具体的な使用法
- 強心薬として使用するのは、ドブタミンとミルリノン(or オルプリノン)
- 私の臨床経験によるドブタミンとミルリノンの具体的な使用方法をもう少し具体的にみていきます。
- お勧めはしないが、PICCでも右心カテーテル検査ができなくはない。
まとめ:
①一番にするのは呼吸管理。
②呼吸管理と同時に、循環不全の評価をし、低潅流の有無を見極めるのが最も重要。
③循環不全・低潅流の評価は、CRT(capillary refilling time)と心エコーのVTIを中心に、血液・尿所見で評価。
④循環不全の状態で静脈系の血管拡張薬を使用してはいけない。
⑤強心薬は、ドブタミン(1.5-3γ)±ミルリノン(0.1-0.3γ, 腎機能に要注意)。
⑥それでもだめなら、機械的な補助を躊躇してはいけない。
慢性心不全急性増悪の治療
急性心不全の中でも、特に慢性心不全の急性増悪といわれる心不全を想定して述べていきたいと思います。
心不全の中には、一部の施設でしか救命できないような劇症型心筋炎や、移植か緩和医療しかないというくらいの重症心不全など非常に重篤な状態のものもありますが、まずは、普段一般的にみる心不全をイメージして、それに対する私個人の治療に対する考えをお話しすることから始めようと思います。
急性期の治療に関しては心不全の重症度に関わらず本来的には評価や治療に関する考え方は同じだと考えています。ひとまずは、救急車で酸素10Lなのに、SpO2 90%で頻呼吸、足がむくんでいる高齢者が搬送されたイメージを持っていただければと思います。
循環不全の評価
心不全の治療で、一番重要なことは循環不全の有無を評価すること
一番初めに対応するのは、呼吸管理ですが、 同時並行で、循環不全の評価を行うことが重要です。
普段見かける心不全で循環不全を有するのは、まれではありますが、低潅流による循環不全を見落として、特に静脈系の拡張薬を開始すると、患者さんの容態は一気に悪化します。 (利尿薬を使用しても反応がないだけなので悪化することは少ない)
初めに行うのは呼吸管理ですが、一般的に見落とされがちで、かつ実は最も重要な低潅流についてまず記載していきたいと思います。
私は心臓移植を実施していた基幹病院にいたことがあり、その際に心不全の患者で治療がうまくいかなかった症例を紹介いただくことがありましたが、その典型例の一つが、低潅流所見があるのに、静脈系の血管拡張薬を用いて重篤化し、機械的なサポートを導入せざるを得なかったというものです。
低潅流の有無が心不全治療の成否をわけるともいえます。
低潅流所見は身体所見として取るのは結構難しい
循環不全のは、心臓からの拍出が少なく、潅流が不十分で、組織が必要な酸素を供給できない状態となっているので、低潅流所見(low perfusion)ともいいます。
低潅流の症状は、倦怠感、身の置き所のない苦しさ、食欲不振となります。ある程度病態を把握している時期での低潅流ならこれらの症状は治療のメルクマールになりますが、急性期には肺水腫でもこのあたりの症状は出るので、非特異的です。
そのため、ある程度特異的な所見や検査が必要になります。
私がたどり着いた低潅流の身体所見は、手の温度、爪の毛細血管再充満時間(CRT, capillary refilling time)になります。
私が最も重要視する循環不全の身体所見:爪の毛細血管再充満時間(CRT, capillary refilling time)
手の指先の体温が冷たければ、低潅流の可能性があります。ただ、もちろん寒い状況では手は冷たいので、そのあたりの環境の影響は考慮する必要があります。
私が最も重要視していた身体所見は、爪の毛細血管再充満時間(CRT, capillary refilling time)です。CRTについてですが、これは指の爪をゆっくりと5-10秒程度押えて、離すと指の爪の色がピンク色に戻りますが、この戻る時間を評価する検査です。
押さえると爪の色がピンク色から白になります。抑える時間は、基本的には5秒ですが、私は10秒にしていました。経験上10秒のほうがよくわかる気がするので、10秒にしていました。指を離して、循環不全がなければ1秒もかかわらず、爪の外側や先端からすぐにピンク色になり、全体に広がります。基準では、これが2秒を下回れば循環不全はないと判断しますが、正直2秒は境界領域だと思います。
循環不全があると、かなりゆっくりと白色がピンク色になっていきます、4秒程度かかることもざらです。4秒かかるときには、循環不全です。2秒前後は微妙です。
ちなみに、元から爪が真っ白のこともありますが、重症の循環不全の可能性もあります。ただ白めの人もいますし、押せば多少さらに白くなる人もいます。
さらに、指によってCRTが違うこともあります。中指は2秒で、薬指は3秒とか。そういうひとは、ひとまず、一番循環のいい指でみればいいと思います。左右の人差し指、中指、薬指の計6本で評価することをお勧めします。
数を重ねて、低灌流の人もそうでない人もみて、実際に循環不全の人の所見に出会って、いろいろみてるうちにわかるようになっていくしかありません。経験的な要素が強い身体所見にはなるかもしれません。
血圧も参考となる指標ではあるが、絶対的なラインはない
血圧も重要な要素ですが、血圧100あるから循環不全がないかどうかはわかりません。
収縮期血圧で100を超えていれば、循環不全が合併している可能性は低くはなりますが、ないわけではありません。特に入院時とかは一過性に血圧が普段よりも若干高めに出ているだけのこともありますので、特に評価を慎重にしなければなりません。
来院時血圧100-120mmHgは一番危険な見誤りやすいゾーンです。
来院直後は、血圧は高めに出ることが多く、酸素療法をするだけでいきなり血圧が80mmHgくらいになることもあり、じつはこれが実際の血圧であったということはよくあります。
また、収縮期血圧70台だからといって、循環不全が必ず併存しているわけでもありませんが、可能性はかなり高くはなります。
客観的な参考指標:心エコーによる心拍出量の計測
CRTは重要な指標だと考えていますが、もっと客観的な指標による裏付けが欲しいとも思います。
低潅流の所見は、手を触って、指で爪を押さえて毛細血管充満時間(CRT, capillary refilling time)を計ってみる、そうするとすぐに評価が可能です。
しかし、主観的な要素も入る検査ですし、これが陽性だからといって、なかなかすぐに強心薬などの治療に踏み切るのは難しいと思います。
また、経過をみていくうえで、症状は非常に重要で、低潅流に伴う症状があれば、治療もその症状が良くなるかどうかを指標にできます。ただ、症状は、原因が特定されるまで、指標にできないという最大の問題があります。
心不全の人の倦怠感が、低潅流なのか、それとも他の原因なのかを明確にするまで、治療の指標としては使えません。
これらを踏まえて、客観的な数値を評価したいというときには、低灌流の指標として、尿検査と血液検査が有効です。
さらに、低潅流そのものではないですが、低心拍を、時間的に早く結果がわかるの指標が、心エコーでの心拍出量の推定です。
もちろん、心エコーで心拍出量を推定したからといって、低潅流があるかどうかはわかりません。心拍出量の絶対値によって低潅流になるわけではなく、その人の体が求めている血液の流量(≒酸素需要)を心臓が拍出できなくなった時に起こるからです。
ただ、それでもやはり、心拍出量を推定しておくことは、低潅流を評価するうえで、重要だと思います。
低拍出の評価として心エコーによるVTI(velocity time integral)とVTIの測定方法
エコーでの心拍出量の推定は、弁膜症の連続の式という狭窄性病変の狭窄の有効弁口面積を求めるのに使用したり、先天性心疾患である心室中隔欠損などの短絡量を推定する時などに使用します。
早速ですが、エコーでの左室流出路から左室の心拍出量の求め方です。
傍胸骨左室長軸像で、左室流出路を描出し、そこをズームします。できるだけズームした状態で、収縮期の左室流出路径を測定します。
この時に、カラードプラーもみておいて、左室流出路に狭窄や加速血流がないことを確認します。もし、はっきりとした加速血流があった場合には左室流出路での心拍出量の推定は基本的にはできないということになります。
次に、心尖部の5腔像と3腔像で、左室の流出路に、まずカラードプラーを当てます。通常の初期設定にすると、左室抽出路の青い血流が見えると思います。もし、左室の中隔が流出路に少し張り出していて、そこに加速血流があった場合には、その部位を避けて、できるだけ均質なカラードプラーの位置にパルスドプラーを当てます。
パルスドプラーは、時間を横軸、速度を縦軸にした図になりますので、ここで収縮期の左室流出路の血流の時間速度積分値(VTI, velocity time integral)を測定します。通常はきれいな放物線になるはずです。
左室流出路のVTIと流出路の断面積をかけることで、1回左室流出路が測定できます。
(断面積は、きれいに描出できれば直接断面を測定しても構いませんし、特に3Dエコーでは断面を長軸をみながら選べるので、正確に測定できると思います)
また、入院後の初回評価は、右室流出路のVTIも測定しましょう。右室流出路は、傍胸骨短軸で、大動脈弁が正面視できる高さあたりで測定できます。
右室のほうが、左室よりも加速血流になっていたりしないので、その点では有用ですが、右室流出路径は、ほとんど肺動脈弁レベルでの計測でいいと思いますが、右心の血行動態によっては、結構拡大していたりすることもあるので、右室流出路径の測定は注意が必要です。
さて、左室の流出路径 2cmの程度で、おおむね個人間での差が少ないこともあり、VTIの数値で直接的に評価することも多いです。
VTIによる心不全のリスク分類(個人的な見解)
以下に述べるのは、個人的な見解です。
ざっくりと分けるバージョンと、細かめに分けるバージョンで2つのバージョンに分けました。
また、あくまで1回心拍出の評価ですので、心拍数を考慮する必要がありますが、通常の心不全であれば、急性期で、洞調律の場合は、心拍数は80-110程度が多いかと思いますので、その範囲ならVTIの評価高でもよいと思います。
ちなみに、本人のしんどさにもよりますが、しんどがっている急性心不全なのに、脈が60前後であれば、やはり脈がおかしいと考える必要があります。徐脈系の不整脈か、内分泌の問題か、βブロッカーの効きすぎなどの可能性があります。
A) ざっくりと分けたバージョン
VTIを、<12cm, 12-16cm, 16cm< の3つに分けました。
< 12cm 低心拍出量が考えられます。低灌流が発症している可能性が高いので、他の臨床所見と合わせて慎重な評価が必要です。低還流、循環不全の所見があれば、強心薬を使用しましょう。血管拡張薬は使用しないほうが安全です。
12-16cm 低心拍出の可能性はおそらくないが、特に12-14辺りはほかの所見と合わせての評価を慎重に行い、必要があれば強心薬を使用しましょう。血管拡張薬の使用は慎重に行いましょう。
16cm< 低心拍出の可能性はないと判断される。
B) 細かくわけたバージョン
< 6cm 低心拍出量で、超重症です。もともとこの程度で生活している低心拍出の方はいなくはありませんが、相当珍しいです。強心薬の使用が勧められるどころか、一時的な機械的なサポートの必要性も考慮されます。安定した後でも、強心薬が長期間必要なことが多いです。原因・年齢によって、心臓移植登録の準備が必要です。
6-8cm 低心拍出量で、かなり重症です。もちろん、安定しているときでもこの程度の低心拍出量の方は一定数います。他の身体所見とあわせてですが、強心薬の使用を積極的に考えましょう。また、血管拡張薬は使用しないほうが安全です。原因・年齢によっては、心臓移植登録の具体的な準備が必要です。
8-10cm それなりに重症な心不全で、低心拍出ではある。心拍数なども考慮に入れるが、低潅流の可能性はある。循環不全の指標を慎重に評価し、静注強心薬か、場合によっては経口強心薬の一時的な併用を積極的に考慮する。血管拡張薬は使用しなほうがいい。
10-12cm 通常よりはやや重症の心不全か。低心拍出の可能性があり、低潅流を起こしている可能性はなくはない。循環不全の指標を慎重に評価し、静注の強心薬が必要な可能性は低いが、経口強心薬の一時的な併用は考慮される。やはり血管拡張薬は使用しないほうがいい
12-14cm 低心拍出ではない可能性が高いが、境界領域である可能性は考慮しながら治療にあたる必要がある。経時的な身体所見の評価が必要。
14-16cm 低心拍出である可能性はほぼない。
16cm< 絶対に大丈夫とはもちろんいわないが、低心拍出ではない。利尿薬を中心に積極的な治療が行える。ただ、あまりに高い場合には高心拍出性心不全(貧血やシャント、脚気など)を考慮する必要がある。
というようになります。
あくまで、目安で、心拍数にもよりますし、VTIの誤差として2㎝程度であれば、状態の変化なしにかわる可能性もありますが、やはり、VTI 8cmと10cmと12cmの心不全は、血行動態的に違う心不全だと思います。
この段階で重要なことは、循環不全・低潅流を疑う状況であったなら、安易に静脈系の血管拡張薬を使用してはいけないということです。 初めに触れましたが、この段階で静脈系の血管拡張薬を使用すると、前負荷の低下による心拍出量のさらなる低下をきたす可能性が高いです。
そもそも、静脈系の血管拡張薬を使用する理由は肺うっ血の改善です。静脈系を拡張させることで、右室への流入量を減少させ、ついで右室の拍出量が一時的に減ることで、左室の前負荷を軽減させ、肺うっ血を軽減させることが狙いになります。心拍出量に余裕があり、過剰な前負荷状態にある心不全であれば有効ですし、afterload mismatchという状況を多少なりとも起こしているのなら、前負荷の軽減で心拍出量は維持ないし増加する可能性がありますが、これはやってみなければわかりません。 あえてこの状態で強心薬のサポートなしに、静脈系の拡張薬を使用すると一気に状態悪化をきたす可能性があるので、そのようなことをする必要はありません。
何より昔と違って、陽圧換気が非侵襲的に使用できる時代ですから、肺うっ血の管理には陽圧換気を行えばよいので、あえて静脈系の血管拡張薬を使用する必要はありません。 なお、私事ですが、陽圧換気時の血行動態の変化は一時期重点的に調べた得意分野です。別に記載しますが、陽圧換気によって心不全が急性増悪しているときには心拍出量の減少は起こりません。今までの実験データから論理的に説明できますし、5年間ですが、移植実施可能施設で重症心不全の診療にかかわった中で、重症心不全で陽圧換気をして低還流所見の増悪を経験したことはありません。
あとで述べますが、呼吸管理で陽圧換気を行い、低潅流の所見があれば強心薬を使用し、フロセミドの静脈注射による利尿反応を見ながら、フロセミド追加か静脈注射用トルバプタンを使用するかで、ほぼすべての心不全は対応可能です。
これに該当しない場合、虚血の時にはIABP±IMPELLA or VA-ECMO、心筋炎の時には、VA-ECMO ± IABP (IMPELLAは両室IMPELLAができることが前提ならOK)くらいではないでしょうか。
定性的な評価になるが血液検査では、Na, K, BUN/Cr, AST/ALT/T-bilあたりが参考になる。
血液検査も参考になります。ただ、もともとの状態と比較してという要素も大きいのですが、安定している時と比べて、Na,Clが低下し、Kが上昇している、Crが上昇し、BUN/Cr比も上昇しており、総ビリルビン(T-bil),AST,ALTなどの肝酵素も上昇しているときには低潅流の可能性が高いです。
これらの変化、特に腎機能と肝酵素に関しては、うっ血でも上昇しますので、心不全増悪した時には一様にみられる変化とは言えます。しかし、低潅流時には、ショックの時同様大きな変化が見られます。
Na,Clに関しては、5-10mEqないし、それ以上低下しますし、AST/ALTもうっ血では2桁の範囲で収まることが多いですが、低潅流では3桁ということも珍しくはなく、うっ血よりも大きな変化をきたすことが多いです。
循環不全の治療
強心薬を使うと予後が悪くなるという意見は無視でいい。
循環不全と診断したら、強心薬を使用する必要があります。
一部の観察研究などのデータで、心不全の治療に強心薬を使うと、多変量解析でほかの因子を補正しても、予後が悪いので、できるだけ使用しないほうがいいという意見があります。
このような意見は基本的に無視でいいと思います。
まず、多変量解析で他の因子を補正できません。
急性心不全で、循環不全になっているようなときには、循環不全という因子が大きすぎて、他と強い相関関係をもちます。当たり前です。
循環不全になるだけで、肝障害もでますし、腎機能障害もでますし、尿量も減れば、食事の摂取量も格段に落ちます。このような状況で、統計ソフトをたたいて、補正したといっても、できているわけがないというのが現実です。
循環不全になれば、強心薬を使う。強心薬を使うと臨床医が判断するような循環不全の状態の各因子から、強心薬を使うということだけを独立させて評価することなど統計ソフトは想定していません。それぞれの相関が高すぎます。
また、前向きの臨床研究も循環不全に対する強心薬の是非を問うてはいません。
ミルリノンなどで臨床試験はありますが、基本的に強心薬を投与してもしなくても、どちらでもいい人というのが試験の前提になっています。
これは、心不全に対する薬の有効性の評価であって、強心薬の是非を問うているわけではありません。
つまり、どんな心不全の人でもこの薬を使うと心不全が早くよくなるよとか、急性期にこの薬を使うとある一定の心不全の人なら慢性期にいい影響が出るよということを証明するための評価試験であって、本当に強心薬が必要な循環不全の人に、強心薬を投与するかどうかを評価するための臨床試験はないですし、また、今後もおそらく倫理的な問題で実施できないと思います。
もちろん、強心薬に限らず体にいい薬なんてものはありません。薬なんてものは使わなくていいならそれに越したことはありません。
ある病気や病態があって、それに対して、治療しない場合どうなるか、治療をするなら、薬を飲んでおこる作用、副作用はどうなのか、それらすべてを考慮して、どうするかという判断と実行が治療です。
つまり、循環不全があるかどうかをしっかり評価できること。
これが重要で、その次に、診断できた循環不全に対して、強心薬の作用と副作用とを考慮して、投与するかどうかの判断をすることが、心不全の一番重要な治療判断になります。
もちろん、心臓の状態、全身状態、社会的背景などから、強心薬よりももっと強力な循環不全に対する治療を行う必要があるときも多々あります。
IABPやImpella、VA-ECMOなどの通常の病院でもできる治療と、VADなどの心臓外科や特殊な循環器内科医がないとできない治療、または、緊急心移植なども考慮しないといけません。
(注:緊急心移植という言葉はありません。しかし、マージナルドナーからの心移植といって、何らかの理由で多少移植される心臓が不適切でも心移植にふみきらないといけない状態の患者さんに対しては、通常よりも早いタイミングで心移植が行われる時もあります)
これらの基本となる判断は、すべての心不全を診療する人に判断することが求められます。
もちろん移植か、補助循環かという特殊な施設にいないとできない判断ではなく、強心薬をいくかどうか、そして、強心薬だけでいけるかどうかという判断が重要です。
より高次の医療機関に送るかどうかも常に考えておかねばなりません。
また、話は変わりますが、緩和医療における強心薬も重要です。緩和だから強心薬なんて不要という人がいますが、違います。低灌流による倦怠感には強心薬を使用します。もちろん、フェンタニルや、必要に応じてプレセデックスなども使用します。
緩和ステージの人で、強心薬を使ったからといって、残念ながらそれほど寿命は変わりません。時として、催不整脈性から予後を短くすることもあります。
その治療が寿命を短くしたとしても長くしたとしても、今ある症状を最大限緩和するのが緩和医療です。
循環不全のある終末期心不全の患者さんに対しては強心薬も緩和医療の一つの選択肢であることは、忘れてはいけません。
緩和ステージでしてはいかない治療というは、患者さんの苦痛をしいてまで治療を行ってはならないということです。ラーメンを食べたいなら食べてもらえばいいですし、不整脈がでまくっていても、モニターの届かない庭で桜をみたければ、みてもらえばいいのです。強心薬で楽になるならすればいい、鎮静・人工呼吸管理(非侵襲的なもの)で楽になるならそうすればいいのです。
緩和の心不全は、ある意味これらをしたからといって、それほど延命できません。
すこし、話がそれましたが、次回具体的な強心薬の使用方法について述べていきます。
強心薬の具体的な使用法
強心薬として使われているのは、ドブタミン、ミルリノン、オルプリノン、ドーパミンになるかと思います。
また、強心薬と似て、非なるものが昇圧薬です。これには、ノルアドレナリン、バソプレシン、ドーパミン、アドレナリンがあります。
まずは、強心薬と昇圧薬は違うということを認識していただければと思います。
昇圧薬は、末梢血管抵抗を上げることで血圧を維持します。つまり、心臓にとっては後負荷が増加しますので、基本的にはうれしくないことです。しかし、最低限の血圧を保つというのは、腎臓には必要なことですので、血圧が低い時には、昇圧薬が必要になります。
(糸球体のろ過圧は、平均動脈圧と中心静脈圧の差以上にはなりません)
ただし、重症心不全の方では、収縮期血圧70ちょっとでも、尿量が確保されていて、日常生活を送られるような人もいますので、あくまで、昇圧薬を使用するのは、血圧が低くて、それによる何らかの不都合や障害(主に腎臓)があるときということになります。
強心薬として使用するのは、ドブタミンとミルリノン(or オルプリノン)
さて、強心薬の使用の順番というのはないのですが、使いやすさでいくと、ドブタミン、ミルリノンの2つだと思います。
オルプリノンは、ミルリノンに準じて使用していただければいいですし、ドーパミンは、昇圧作用がありますので、昇圧させたい時以外の心不全の使用には適しません。特に利尿がコントロールできていない状態(=利尿薬投与で利尿が確保できていない状態)では、左室拡張末期圧があがり、呼吸状態が不安定化することがあります。
全体的な注意事項としては、脈が速くなるだけでなく、心室性の不整脈が不安定化することがあるのと、解除されていない(虚血による症状があったり、心電図で虚血性変化が顕在化している)重症な虚血によって心機能が低下しているときに、ドブタミンやドーパミンを投与すると心筋の酸素需要が増大するために虚血が一層不安定化することがあり、虚血症状が悪化し、さらに、全身状態が不安定化することがあります。
虚血で心機能低下があり、PCIやバイパスされていて、主要な血管による虚血の所見がない時には、強心薬の使用は全く問題ありませんが、心電図の変化や虚血による症状があり、虚血が顕在化しながらしているときには、IABPが有効ですので、IABPを導入したうえで、血行再建を行いましょう。
まず、各薬剤の使用を簡単にみていきます。
(投与量はγという単位になります。γ=μg/kg/min)
①ドブタミン
使用量:1.5 or 2γ程度から開始し、4-5γ程度にとどめる
ドブタミン 3γ程度でLOSの症状が改善がないときは、ミルリノンの併用を早期から考慮する
(単剤増量よりも併用のほうが有効なことが多い)
また、感染などによるショックの時は10γまでの使用を考慮します。
②ミルリノン
腎機能正常であれば、0.1γ程度から使用し、0.05か0.1γ程度ずつ増量し、0.3γ程度までにとどめる。
腎障害があるときには、目安として、投与量(γ)をクレアチニンの値で割った値が大体の目安となる。
③オルプリノン
ミルリノンよりも血管拡張作用が強いとされる。
使用はミルリノンと同じで、ミルリノンと同量であれば、2倍の効果あるため、半量を目安にする。
④ドーパミン
強心薬としては、ドブタミンに対するアレルギーなどの際に使用する。
急性期に使用するときは、可能な限り血管拡張作用のあるPDEIII阻害薬と併用する。
ショックを伴う心不全の急性期の昇圧目的に使用する際には、かならず十分な量のドブタミンを使用したうえで、最小限を使用する。
使用量:1.5 or 2γ程度から開始し、4γ程度にとどめる。4γ以上必要な時は、NADを使用する。
基本的に、昇圧するときには、ドーパミンを投与するよりも、ドブタミンとノルアドレナリンを併用し、ドブタミンは循環不全の所見がなくなるような用量に調整し、血圧自体はノルアドレナリンで調整するのがよい。
また、投与経路ですが、まずは、薬剤は薄め溶いて末梢のルートから投与し、落ち着いてきたら、できれば、その日のうちに、遅くとも翌日にはPICCカテーテルからの投与を強く推奨します。
強心薬を投与しても落ち着かなかったら、もっといろいろとしないといけないので、まず、これで落ち着いたとして話を進めたいと思います。
投与に関してですが、具体的には、速やかに循環不全を改善させるのが優先ですので、末梢静脈から専用のルートをとって、投与を開始します。できれば、薬液は薄めにしてください。薄めて、投与スピードを速くするほうが投与される薬液量が安定します。速やかに投与することを優先しつつも、末梢静脈からの投与は、漏れてしまうことがありますので、これをもっとも注意して投与をします。
一定期間で入れ替えても、やはり、末梢ルートでは漏れてしまう危険があります。漏れてしまうと、入れ替えの間に薬剤の投与が切れてしまいます。これをもっとも避けたいので、できるだけ、速やかにPICCか、CVカテーテルによる安定した投与を行いたいところです。
私の臨床経験によるドブタミンとミルリノンの具体的な使用方法をもう少し具体的にみていきます。
①ドブタミン
使用量:1.5 or 2γ程度から開始し、5γ程度にとどめる
ドブタミン 3γ程度で循環不全の症状が改善がないときは、ミルリノンの併用を早期から考慮する
(感染などによるショックの時は10γまでの使用を考慮する)
②ミルリノン
腎機能正常であれば、0.1γ程度から使用し、0.05か0.1γ程度ずつ増量し、0.3γ程度までにとどめる。
腎障害があるときには、目安として、投与量(γ)をクレアチニンの値 で割った値が大体の目安となる。
初回の投与方法に関しても、繰り返しになりますが、まずは、末梢静脈ルートから投与します。薬液の濃さに関しては、できるだけ薄めにして、流量を早めに設定することで、静脈炎による点滴ルートの漏れを予防し、また、安定して薬剤を投与します。
本体ルートを用いてもいいですが、 これをすると全体的に点滴の投与量が意外に多くなったりすることがあるので、そこには注意が必要です。特に、循環不全で利尿が不十分な時に、20ml/Hとかで投与すると結構な負荷になります。
私の使用法では、基本的には2γから開始します。30分から1時間程度様子を見て、倦怠感や低酸素を伴わない呼吸困難などの症状が循環不全からくると診断できていれば、そのあたりの症状(大阪弁で言う、なんか知らんけどしんどい、息すんのもしんどいという症状)を指標にして、症状が改善すれば投与量を固定します。
症状の改善がない時には、他の所見や尿量もみますが、心室性の不整脈が増えていなければ、2.5 or 3γに増量して、再度状態を0.5-1時間程度みます。
それでも、症状や循環不全の所見に改善がみられないときには、ミルリノンを併用します。
併用時には、基本的に同じ末梢ルートから投与します。いわゆる共流し状態です。(ただ、できるだけCVCやPICCに変更しましょう)
ミルリノンは、0.1γ程度から開始します。腎機能が悪い時には、クレアチニンで割ったγ数にします。
例えば、Cr 2であれば0.05γ、Cr 4であれば0.025γです。ミルリノンは腎代謝ですが、腎障害性があるわけではありませんので、心室性の不整脈の出現に注意しつつ、気持ち少なめから開始します。
これも、症状をみながら、0.5-1時間程度の期間でみていきます。
この段階で、ドブタミン3γ、ミルリノン 0.1γですので、これで改善されない低潅流からくる循環不全はかなり重篤です。
一応、ミルリノンを0.05γか0.1γずつ増量して、0.3γまでは増量します。
この段階で、ドブタミン3γ、ミルリノン0.3γです。これで改善されない循環不全は、薬剤投与のみでは無理だと思います。社会的な状況によりますが、心移植を念頭に置きましょう。特に、この段階で心不全が悪くなっている明確な因子があって、それが改善させることができるものである状態であればいいのですが、これがないときには、本当に心不全を安定化させることは困難と考えてもいいです。
また、改善できても、一過性に強心薬を中止することができたとしても、また繰り返します、しかも、短時間で。基本的に繰り返したときの心不全のほうが、重症のことがあり、治療がさらに困難になることは多々あります。 (特に基礎となる心疾患の進行が速い場合には要注意)
さて、年齢などの問題で、強心薬でいくしかないときには、ミルリノンは0.3γ程度以上にはあげずに、ドブタミンを5γ程度まで上げていきましょう。
感染などの増悪因子がない時の心不全への強心薬投与としては、これが最大用量だと思っていいと思います。
これ以上上げても、意味がなくはないのですが、頻脈や中期的な治療でかなり困難になります。
もちろん、感染やなんらかの一時的な増悪因子があって、それを改善させる間だけの一時的な投与であれば、ドブタミンはもっと増やしてもいいと思います。その間に、感染などをコントロールできれば、そのあとに強心薬を減量できる可能性は大いにあります。
強心薬投与で心室性不整脈が増えているときには、どうするかですが、心室性期外収縮は健常者であれば無視してもいいくらいの数(10-20%とか)でも、心不全の急性増悪の時には、それでも不安定化することがあったり、特に短い心室頻拍や持続せず短いながらも心室粗動が出ているときには、一気に急変の可能性もあります。
このような不整脈がある時でも、強心薬の維持や増量が必要な時には抗不整脈薬を併用します。(強心薬を増やして状態を安定させれたらと不整脈が減ることもあります)
お勧めは、ニフェカラントです。これは、Kチャンネル選択的に阻害するため、心機能にほとんど影響を与えません。
重症心不全患者への投与でやってはいけないことがあります。それは、アミオダロンのローディングです。一般的なアミオダロンのローディングなどすると一気にショック状態になることが多々あります。ただし、ニフェカラントであれば、静注してから維持用量持続注射しても、血圧は基本的に下がりませんし、心不全の管理自体には特に影響は与えません。
もちろん、投与中に心電図でQT間隔を確認しながら、用量調整が必要ですが、非常に有効だと思います。
繰り返しますが、アンカロンのローディングは危険ですので、循環不全をきたしているような心不全ではしないことをお勧めします。
また、ここまでしないといけない心不全は集中治療室に準じる場所で治療をしていることと思いますので、こまめにカリウムの値の補正も行います。基本的には、4.8-5.5mEq/Lのレンジを目標に、基本的には5は切らないというような感じでいきます。また、マグネシウムも時には必要です。
PICC (peripherally inserted central catheter)について
何度かPICCという言葉を説明なく使いました。もう一般的に使用されていると思いますが、PICC (peripherally inserted central catheter)というのは、日本語では末梢静脈挿入型中心静脈カテーテルのことになります。
つまり、両腕の末梢静脈から細めのカテーテルを入れて、それを中心静脈あたりまで進めていって留置します。この位置であれば、安定して薬剤や中心静脈栄養といわれる濃度の濃い薬液を投与することができます。
現時点では、singleかdoubleといって、カテーテルの内腔に仕切りのないsingleか、しきりがあって、2つに分けれているdoubleかしかありません。ただ、海外ではtripleといって3つに分かれているものも存在はしていましたので、日本でも使えなくはないと思います。また、比較的近位の上腕のあたりから穿刺するなら、少し細めのCV(central vein)カテーテルを代用することはできますので、どうしてもtripleルーメンが必要な時には、考慮してみてください。
さて、このPICCの優れているところは、やはり感染が少ないということにつきます。
もちろん、穿刺前に石鹸などできれいにして、十分にマキシマルな清潔操作で挿入することも必要ですし、管理も3方活栓をシュアプラグというものに変更したり、圧ラインを閉鎖式にしたり、さまざまな感染対策を十分にすることは必要です(これらで本当にカテーテル感染は減ったと思います)。
留置部管理がしやすいのと、留置部と中心静脈に距離があるので、留置部が少し発赤したり感染が怪しいと思った段階ですぐに入れ替えれば、感染などもほとんどなく経過することが可能です。
非常に優れたカテーテルだと思います。
病棟の処置室などで留置されることも多いと思いますが、私はカテーテル室で留置していました。
お勧めはしないが、PICCでも右心カテーテル検査ができなくはない。
循環器内科医でしたので、カテーテル室のハードルが低いというのは絶対的にありますが、カテーテル留置の際に、混合静脈血と簡易的な右心カテーテル検査を同時に行っていたからです。
すこしの工夫で、簡単な右心カテができてしまいます。
ただ、正しいか値かどうかはわかりませんし、マネをしてくださいとも言いません。
臨床工学士の人と、こっそりと二人でやっていた検査ですが、一応記載しておきます。
こつは、一番長いPICCカテーテルを選びます。また、親水性コートとされていない、曲げようと思えば曲げれるガイドワイヤーのものを選びます。
そして、いったん上大静脈くらいまでカテーテルをもっていって、そこで、いったんワイヤーを抜いて、思いっきりワイヤを曲げます。
くるくるくるとねずみ花火的な先端にします。
それを入れていくと、いい感じでカテーテルの先が上を向くので、そのまま肺動脈まで持っていきます。
そこで、圧ラインをつないぎます。
すると、肺動脈圧が測定できます。この時に、よほど重症の心不全で肺血管まで傷んでしまっているような心不全でなければ、肺動脈の拡張期圧と左室の拡張末期圧はほぼ同じ値になりますので、肺動脈圧ならびに左室拡張末期圧を測定できます。
そのまま、肺動脈で混合静脈血を測定することで、心拍出量も測定することができます(この辺りは、心臓カテーテル検査で述べます)。
さらに、どんどんとカテーテルを引いていくと、右室圧、右房圧を測定することができます。
そして、最後は上大動脈のいいところに先端を確認して、固定して終了します。
現在ほとんどのカテーテルは、液体充満型カテーテルといって、カテーテルの先端の液面にかかる圧がカテーテルの中の液体を押し上げる圧を計っています。そのため、直接コンデンサーで測る圧よりも不正確です。カテーテルが、長く細くなればなるほど、この値は不正確になります。特に、時間と圧の関係が不正確になり、時間当たりの圧変化率のデータは評価してはいけないとされています。
ただ、最高圧や最低圧に関しては、ある程度信用できる値になります。
もちろん、PICCはかなり細径のカテーテルですので、正確な値ではありませんが、参考程度にはなります。
循環不全のゴールドスタンダードは尿所見であると個人的に強く信じている
低潅流による循環不全のゴールドスタンダードはなんでしょうか。
私の答えは、尿中クロールです。10割本気です。
一時期、心筋マニア、心不全オタク、ただの通りすがりの心不全屋などなど、さまざまに評価されながら、たどり着いた最終地点、それが心不全の循環不全を評価するスタンダードは尿中クロールだということでした。
心不全の時にどのように尿中生化学をみていけばいいかをお話ししたいと思います。
心不全時のスポット尿検査
まず、尿生化学検査は、蓄尿してはいけません。かならず、スポット尿といって、1回分の尿で検査するか、バルーンで尿を管理しているときには、10ml程度を検査用にとってそれを検査に出します。
検査をするタイミングとしては、入院時と入院2日目の朝です。
入院時の測定は、入院後に初めての尿か、バルーンを入れた場合には、バルーンに流れてきた初めの10mlを検査に出して測定します。
次に、入院翌朝食事前、内服前の排尿時のものがいいのですが、それが困難であれば、起床後の一番初めのものを検査に出します。バルーンの場合には、大腿私は、6時に0-6時までの尿量を測定してもらって、その尿は廃棄して、6時から30分くらいでた待った尿を検査に出してもらっていました。
初めは、なかなか理解してもらえませんが、何回もお願いすると、看護師さんからはおしっこの先生といわれながらも、協力してくれるようになります。
(その後、大学の院生の研究の関係で、循環器疾患と便の細菌の関係を調べる病棟側の担当をすることになり、尿だけでなくとうとう便にまで手を出したのかと、看護師さんにいじられたのも思い出です)
さて、測定する項目は、最低限は、尿中クロール、カリウムで、通常はナトリウムも加えた3項目です。可能なら、クレアチニン、尿素窒素。さらに、可能なら尿酸の合計6項目を測定します。
入院2日目以降は、同じように尿中クロールと、カリウムに、ナトリウムの3項目は測定したいところですが、さまざまなしがらみの中で決めていただければよいかと思います。
尿中クロールが循環不全の指標となる
さて、解釈ですが、尿中クロール濃度をまずみます。
30mEq/L以下だとほぼ循環不全確定です。
(以前、入院2日目の尿で尿中クロール35mEq/L以下は、ほぼ強心薬かそれに準ずる機械をつけているという臨床報告をしましたが、なかなか受け入れてもらえず、挫折した過去があります)
30-40mEq/Lなら、循環不全の可能性が結構あります。
40-60mEq/Lなら、おそらく循環不全はありません、たぶん大丈夫です。
そして、60mEq/L以上であれば、循環不全ではありません。大丈夫です。
これだけみるのでも大丈夫ですが、さらにカリウム濃度を合わせてみると、ざっくりいうとクロール濃度よりも高ければ循環不全です。
また、ナトリウム濃度は、だいたいクロール濃度と相関して動きますので、クロールと同じように考えていただければ結構です。
心不全の時に尿化学検査をどのように評価をするかですが、個人的にはいろいろと模索した結果、電解質だけをみればいいのではないかと思うようになりました。
ただ、尿中のクレアチニン(urinary Cr, uCr)や尿素窒素(urinary UN, uUN)、尿酸(urinary UA, uUA)に意味がないわけではありません。
1日の尿中のクレアチニン排泄量は、個人によって違います。ただし、同一の個人であれば、入院中のような2週間程度で、ほぼ同じ生活強度であれば、1日の尿中のクレアチニン排泄量は同じです。
さらに、時間当たりの尿中のクレアチニン排泄量もほぼ一定です。
つまり、1日に1g、1000mgのクレアチニンを排泄する人であれば、1時間あたりは、ほぼ40mgと一定なのです。
これは、尿量の推移に使えます。
朝一番の尿中のクレアチニン量を比較すると、ある日の尿中クレアチニンの濃度が80で、翌日が40であれば、純粋に2日目のその時の時間当たりの尿量は、1日目と比べて2倍になっています。
尿道バルーンなどを入れていれば、時間当たりの尿量を調べることができますが、ラシックスなどの利尿薬の投与前と、投与して1-2時間くらいの尿中のクレアチニン濃度を測定して、その比を見ることで、ラシックスの効き具合が尿量という時間当たりの結果よりも早く知ることができます。
ただ、少し待ったら尿量がわかるので、これだけのために、尿生化を見る必要はないと思います。
大事なのは、uUNやuUAもuCrと同じように濃度が変化するということです。
これを利用すると、尿量が減った時に、ただの利尿薬不足か、循環不全の悪化なのかの情報の一つとすることができます。
スポット尿検査のuUN/uCr, uUA/uCrの比は、利尿薬不足か循環不全の悪化かを教えてくれる。
循環がよくなろうがわるくなろうが、Crは多少尿細管から分泌されるとはいえ、ほぼその排出量は、1日で決まっています。循環、特に腎循環には影響を受けません。
しかし、uUNや特にuUAは腎循環によって大きな影響を受けます。循環不全になると再吸収が亢進するため、尿中の排泄量が低下します。
つまり、前日と比べて尿量が低下した時であったとしても、尿中のクレアチニンと尿素窒素の比、または尿中クレアチニンと尿中尿酸の比が一定であれば、腎循環の悪化はなく、ただの利尿薬不足の可能性があるため、利尿薬を投与を続ければ、利尿は得られます。
しかし、この比が変化、つまり、尿中クレアチニンあたりの尿中の尿素窒素や尿中尿酸の濃度が低下するときには、循環不全を起こしている可能性があります。
この時には、2つの可能性があります。すでに引ける水がなくなっているときには、うっ血の治療は終了です。利尿薬を維持容量に減量します。
もう一つは、引けそうな水があるのに、この尿生化学検査で循環不全のサインが出ているときには、強心薬の投与や、利尿の速度を落としてあげる必要があります。
このように治療のマーカーの一つとして利用することができます。
それでは、尿中尿素窒素と尿酸のどちらがいいかというと、尿酸です。
両方とも、それぞれにちがう理由で再吸収が亢進しますが、尿酸は近位尿細管で乳酸と交換で再吸収されます。
とまり、腎臓での組織内での乳酸の濃度が上昇している可能性が示唆されるためです。
これは、臨床の私のデータでも、尿酸のほうが少し、さまざまな悪化を予見できる可能性が高いという結果を説明する要素だと考えています。
さらに、どの変化すれば優位ととるのかというと、20%を超える変化は優位だと思います。10%以下は、特に何も変化なくても変わりうる値だと思いますし、10-20%はグレイゾーンです。
また、尿検査の異常の後には、血液検査の異常が出てきます。つまり、尿中の排泄量が減った尿素窒素や尿酸が血液検査として変化したときには、尿中の変化はいったんリセットする必要がありますので、血液検査との兼ね合いも重要です。
あくまで、血液検査が変わる前に、尿検査のほうが早く変化するので、この変化をとらえに行っていると思ってください。
補足:なぜ循環不全で電解質異常が起こるのか
傍髄質にある糸球体は、一般的に説明されるような構造で、尿細管などがすべてそろっていて、電解質の再吸収などが非常に精巧に行われています。
しかし、皮質の外側にある糸球体には、尿細管などが十分に発達しておらず電解質の再吸収などは、十分に行われないとされています。
この尿細管の発達の差が非常に重要で、心不全の低潅流の時には、皮質の糸球体への血流の分布が減少するとされています(アンギオテンシンが関与するといわれています)。
つまり、低潅流の時には、尿細管レベルでのナトリウムやクロールの再吸収が亢進しているだけではなく、もともと電解質の再吸収が行われやすい傍髄質の糸球体により血流が回されることで、一層電解質の再吸収が行われやすいという現象が起きます。
また、糸球体単位でも、低潅流時にみられるレニン・アンギオテンシン・アルドステロンの上昇は、尿細管でのナトリウムとクロールの再吸収を更新させますし、さらに皮質集合管の上皮性ナトリウムチャンネルでのナトリウムの再吸収とカリウムの尿細管への分泌を亢進させます。
つまり、腎臓レベル、糸球体レベルで、低潅流時には、尿中のナトリウムやクロールの濃度が低下し、カリウムの濃度が増加するという現象が起きます。
そして、低潅流が改善するともともと電解質の再吸収能力の弱い皮質の糸球体へも血流が元通りに増加するので、電解質を含んだ尿が増えてきます。
この一連の変化が、腎臓の尿所見を通して低潅流を評価できる病態となります。
(一応この仮説を、3名の腎臓内科の専門医(腎臓内科の教授、元教授、講師)にも確認しましたが、合っていると思うとの見解でした)