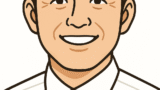老後資金とインフレ率──見落とされがちな前提条件
老後資金に関して、ああでもないこうでもないと考えているのですが、最近インフレの世の中になってきて、学生時代からずっとデフレないしゼロインフレ(インフレではない状態)を生きてきた身としては、これからの2%台のインフレは、老後の資金計画への影響がすごく大きいなと途方に暮れています。
具体的に、例えば今50歳で年間生活費が300万円だとしたら、インフレ率が年2%で進んでいくと、10年後60歳で同じ生活を送るのに360万円必要になって、さらに70歳では440万円、80歳では530万円と、年齢を重ねるごとに必要額は膨らんでいきます。
こうして数字にしてみると、インフレ率を無視して老後の資金計画を立てることは、危ういなと思いました。そこで、改めてインフレ率やCPI(消費者物価指数)について調べてみました。
CPIとは何か?
CPI(Consumer Price Index:消費者物価指数)とは、消費者が購入する商品やサービスの価格の平均的な変化を示す指標で、インフレ率の代表的な指標として使われます。
日本では総務省統計局が毎月公表しており、食品、住居、光熱費、交通、教育など約600品目以上の「代表的な商品やサービス(バスケット)」を基準年(直近では2020年)に設定し、その価格変動を追跡しています。
CPIの「バスケット」──品目構成と比率
CPIは、家計の支出構造をもとに、次のような大分類で構成されています(2020年基準のウェイト):
| 大分類 | 主な品目例 | ウェイト(%) |
|---|---|---|
| 食料 | 米、パン、肉、外食など | 約26% |
| 住居 | 家賃、持家の帰属家賃など | 約21% |
| 光熱・水道 | 電気、ガス、水道など | 約7% |
| 家具・家事用品 | 家電、掃除用品など | 約4% |
| 被服及び履物 | 衣類、靴など | 約4% |
| 保健医療 | 医療費、薬代など | 約4% |
| 交通・通信 | ガソリン、車、通信費など | 約14% |
| 教育 | 授業料など | 約2% |
| 教養娯楽 | 書籍、映画、旅行、パソコン等 | 約11% |
| その他 | 理美容、たばこ、仕送りなど | 約7% |
この「バスケット」は5年ごとに全面改定されます(最近では2015年→2020年)。次回は2025年基準へと更新予定です。
日本のCPIの変化と特徴
日本では、1990年代以降、長らくインフレ率が低迷し、デフレやゼロインフレの状態が続いてきました。しかし、2022年以降、世界的なエネルギー価格高騰や円安の影響を受けて、日本でもCPIが上昇し、2%台のインフレが定着しつつあります。
CPIの上昇は、生活費の増加だけでなく、賃金や年金の改定、金融政策(金利)にも強い影響を与えます。
CPIが老後資金に与える影響
国・日銀が2%インフレを目標にすると言っているので、基本的に平均2%程度のインフレを前提に老後資金を計画しないといけないのだろうと思っています。今、300万だと、60歳の時には同じ生活を送るのに360万必要で、それをスタートラインとして、70歳で440万円、80歳で530万円と必要額は増え、年金も物価スライドしてくれると信じても、年金と必要額の名目の差額は広がっていくので、それを埋めていかなければならない。60歳の時点で現金預金のみだと、どんどん価値としては目減りしていくので、何らかの投資は必要なのだろうと思います。
おそらく、私の場合は、もともと長期(生涯保有)前提の株式投資ですので、死ぬまで保持して、インデックスを適時取り崩していくことになるのだろうと思っています。
CPIが金利・投資に与える影響
日本銀行はインフレ目標を2%と設定していて、CPIがその目標を上回ると、利上げ(政策金利の引き上げ)などの金融引き締め策が検討されます。これにより、市場の金利全体が上昇し、債券価格の下落や株式市場の変動につながる可能性があります。
インフレ率が高まると、投資家はインフレ率を上回るリターンを得るために、よりリスクの高い資産に資金を移す傾向があります。また、定期預金や低利回りの債券では、実質的な購買力が下がってしまうため、ポートフォリオの見直しが求められます。
本来、債券の利率というのは、”名目利率(額面の利率)=CPI + 実質利率”の式で表され、欧米では、2〜2.5%のCPIの時、中期国債の額面利率は 2〜3%程度でした。今の日本は、CPIが2.5%を超えているにもかかわらず、5年固定国債の利率が1.0%程度(2025年8月時点)というのは異常な事態です。
このような状態が続く限り、日本人がインフレに対応した安全な資産運用を行うことが難しく、大きな問題だと思います。
まとめ:インフレを無視しない資産形成を
CPIは単なる統計指標ではなく、老後資金の設計、投資戦略、金融市場の安定性にまで影響を及ぼす重要なファクターです。
50歳の今から老後を見据えて資産形成を考えるなら、インフレ率とそれを反映するCPIの動向には注意が必要で、それを前提とした資産計画を立てなければ、老後破綻する可能性もあると思っています。