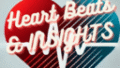- 聴診法とは、まったく測定原理が異なる。
- 電子血圧計は、血管の振動から生じるカフ内の振動を計測し、その値が最大となる平均血圧を実測している。その後、振動の変化や既存の膨大なデータなどの諸条件から、最終的には数学的に収縮期圧及び拡張期圧を計算により求めている。
- 電子血圧計は、いくつかの条件下では測定値の信用性が低下する
1. 平均血圧が一定とならない心房細動などの不整脈
2. 平均血圧からの解離(脈圧)が大きかったり小さかったりする場合
a. 脈圧が大きい:高度な動脈硬化や大動脈弁閉鎖、
b. 脈圧が小さい:重症心不全
(ただし、平均血圧自体は正しく測定できている)
3. 安静でも振動してしまう疾患(パーキンソンなど)
電子血圧計に関わる各機関の定義
1.ISO 81060-2:2018(非侵襲式血圧モニタに関する国際規格)の定義:
「オシロメトリック法とは、カフの内部圧に重畳する微小な圧脈動(oscillation)を検出し、それらの振幅特性から平均血圧を求め、収縮期・拡張期血圧を算出する間接測定法である」
= MAP(平均血圧)は実測、SBP/DBP はアルゴリズムにより推定。
2. AAMI(米国医療機器振興協会)の公式定義
米国の医療機器規格 AAMI/ANSI SP10 では:
「オシロメトリック法は、カフ圧の減圧過程で生じる振動の最大点を平均動脈圧とし、振動の立ち上がり・低下点の比率から収縮期・拡張期を計算する方法である」
ここでも 最大振動=MAP、比率による推定=SBP, DBP が明記されています。
3. AHA(アメリカ心臓協会)ガイドラインでの公式説明
AHA Scientific Statement(Blood Pressure Measurement in Humans, 2017)より:
「電子血圧計は、カフ内圧の振動(oscillations)から MAP を抽出し、そこから収縮期・拡張期を数学的に推定する oscillometric method を用いる」
4. 日本高血圧学会(JSH)の公式説明
上腕式電子血圧計は オシロメトリック法を用いる
測定値は MAP が基礎となり、収縮期・拡張期はアルゴリズム推定
手首式は誤差が大きいため基本推奨しない
5. 医療機器メーカー(OMRON, A&D)の公式技術説明
● OMRON
「カフの脈動(振動)をセンサーで検出し、その波形から平均血圧を求め、独自アルゴリズムで収縮期・拡張期を算出する方法」
● A&D(エー・アンド・デイ)
「カフ圧振動の最大点が平均血圧であり、振動比から収縮期・拡張期を決定する」
電子血圧の測定方法、聴診法との違い
このように家庭用の電子血圧計(上腕式)は「オシロメトリック法(Oscillometric method)」と呼ばれる方式を使っています。この仕組みは非常に洗練されており、十分な実績がありますが、注意すべきは、聴診法(コロトコフ法)とはまったく異なる原理であるという点です。
1. 聴診法(コロトコフ法)は「血流音」を聴く方法
我々が行う聴診器を用いた血圧測定は、マンシェットを巻いて「コロトコフ音」を聴く方法です。
●仕組みの流れ
- カフを加圧し、動脈を完全閉塞
- 少しずつ圧を下げる
- 動脈が“部分的に開く”と血流が乱れ、「トントン」という音が出る
- 最初に音が聴こえた圧=収縮期血圧
- 最後の音が消える圧=拡張期血圧
血が流れ始める瞬間の音と、静かになる瞬間の音を利用する方式。
原理が明確であるため、ガイドライン上は長年「基準法(ゴールドスタンダード)」として扱われています。
2. オシロメトリック法(電子血圧計)の正式定義
オシロメトリック法は、マンシェット内の微小な圧振動(oscillation)を検出する方法で、ISO国際規格およびAHAの公式定義では次のように説明されています。
- カフ圧の減圧中に生じる圧の振動(oscillation)を検出する
- 振動が最大になる点=平均血圧(MAP)
- 収縮期・拡張期血圧は、振動比率からアルゴリズムで推定する
ここが重要です:
✔ 電子血圧計で 実測している値は MAP(平均血圧)
✔ 収縮期と拡張期は“統計的推定値”
3. 電子血圧計でカフ圧を下げていくと振動はどう変化する?
電子血圧計では、血管の振動が血圧計のカフを振動させ、そのカフの振動を測定しています。
それでは、カフの振動から最高血圧と最低血圧が聴診法のように実測できるかというと、それはできません。
聴診法のように、血流、特に乱流を測定できれば可能ですが、あくまでカフの振動を測定しています。そのため、血管が完全に閉塞され、血流が途絶えていても、動脈自体に多少の振動は生じるので常に振動を感知します。また、拡張期血圧以下でも血流や動脈自体の性質により血管は振動しますので、振動がなくなるということはありません。
そのため、振動の有無で最高血圧や最低血圧を測定することはできず、あくまで振動の最大となる平均血圧を実測し、あとは、血圧の変化当たりの振動の変化や既存の膨大なデータなどから数学的に最大血圧と最低血圧を推定するということになります。
簡単にまとめると下記のような典型的なパターンになります。
- カフ圧が高い(完全閉塞) → 血流はゼロ → しかし血管壁は拍動に合わせて“動こうとする”ため微小な振動が生じる
- 収縮期を下回ると血流が部分再開 → 壁の拍動+乱流の影響で振動が増える
- MAP付近で振動が最大になる → 血管がもっとも大きく変形する(膨らむ・戻る)
- 拡張期を下回ると血管は常に開通 → 壁の変動が減るため振動は徐々に小さくなる → ただし完全にゼロになるとは限らない
重要:なぜ「振動の開始点=収縮期」とならないのか?
- 完全閉塞状態でも、血管壁は拍動でわずかに動く → 振動は収縮期より前(もっと高い圧)から出始める
✔ だから“開始点=SBP”にはならない。
重要:なぜ「振動の消失点=拡張期」とならないのか?
- 血管が開通しても、拍動で壁は動き続ける
- 体動・皮下組織・筋肉の張りでも微小振動は加わる → 拡張期を下回ってもしばらく振動が残る
✔ だから“終了点=DBP”にはならない。
4. どうやって SBP/DBP を求めているのか?
唯一信頼できる生理学的なポイントが MAP(最大振動点) です。
- 振動が最大になる圧=平均血圧(MAP)
- 個人差がほとんど出ない
- 再現性が最も高い
電子血圧計は、
1. MAP を実測
2. MAP から見た振動比のパターンから
SBP(収縮期)DBP(拡張期)を 数学的に推定 します。
これがメーカーごとに違う“アルゴリズム”です。
聴診法と電子血圧計のズレはなぜ起きるのか?
● 聴診法
- 血流の“音”を直接拾う
- ただし皮下組織の状態により血圧は高めに出ることがある。収縮期では高度に締め付けているが、拡張期では皮下組織が緩めになっており、圧を逃がしやすくなるため、実際の値よりも、高めに出やすい
● オシロメトリック
- MAPは正確だが、SBP/DBPはアルゴリズム推定
- 動脈硬化、脈圧、体動で推定誤差が出る
- 一般に 収縮期は高め・拡張期は低め → 脈圧が広く出やすいといわれています。
- 特に以下の条件では、測定値の信頼性が低下する。
1. 平均血圧が一定とならない心房細動などの不整脈
2. 平均血圧からの解離(脈圧)が大きかったり小さかったりする場合
a. 脈圧が大きい:高度な動脈硬化や大動脈弁閉鎖など
b. 脈圧が小さい:重症心不全
(ただし、平均血圧自体は正しく測定できている)
3. 安静でも振動してしまう疾患(パーキンソンなど)