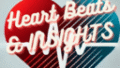血管拡張薬は、動脈系と静脈系の2つに分けられる。
血管拡張作用には、大きく分けて2つ、動脈系の血管拡張と、静脈系の血管拡張があります。ただ、明確に分かれるというよりは、両方の作用を持つが、静脈系の作用が強いなどどちらの作用がより強いかで考える感じになります。
動脈系の拡張薬について
動脈系には2種類あります。大血管系を拡張させて、コンプライアンスを上げて後負荷を下げる薬剤(高用量ニトロ製剤)と、末梢の細動脈を拡張させて末梢血管抵抗を緩和させる薬剤(ACE阻害薬やカルシウムチャネルブロッカー、PDE3阻害薬など)です。
心不全の急性期に、動脈が硬くなっているかどうかを診断する方法はありません。
重症心不全の時には、カテーテル検査を行って血管抵抗値を算出しますが、急性期には気管挿管でもされていないとできませんし、やる意味はありません。
わからないなりに、どのような人に動脈系のコンプライアンスを上げる治療が必要かのプロファイリングはあります。
急性期に動脈を拡張させないといけない人は、血圧が(その人の普段の血圧よりも)高く、肺水腫を起こしているときです。
さらにいうなら、頻呼吸、頻脈になり、拡張期血圧も上がっていて、末梢は冷感、顔も冷や汗をかいているような状態です。循環不全も伴っている状態といえます。
このような時には、動脈系の血管拡張を行う必要があります。
具体的には、ミオコールスプレーの投与です。
ニトログリセリン舌下錠のスプレー製剤です。
もともとは、狭心症の発作時に頓用で使用することで、冠動脈への血流が改善し、胸部症状が緩和される目的に作られました。
しかし、心不全の一部に、大血管系が何らかのきっかけで硬くなってコンプライアンスが低下し、コンプライアンスが低下した大動脈に血液を駆出することは、左室にとって後負荷上昇となり、左室拡張末期圧が上昇してしまいます。
この変化は、短時間でも起こりうるため、いきなり発症する肺水腫となることがあります。
逆に突然肺水腫になるような病態は、このような経過をたどるため、ミオコールスプレーが一時的な肺水腫の管理に必要不可欠となります。
ミオコールを5分から10分おきに、血圧と呼吸状態をみながら投与を繰り返します。
このような場合には、非侵襲的陽圧換気による治療が必要ですので、これらの管理も併せてしていくことになります。
PDE3阻害薬やドブタミンも動脈系の血管拡張作用があります。
強心作用と合わせて、低潅流の治療に使用し、不整脈に注意すれば、安全に使用できます。
静脈系の血管拡張薬について
現在、心不全で血管拡張薬として使用されている持続静注の薬剤(主にニトロ系の製剤とhANP)は、基本的に静脈系の血管拡張薬であり、前負荷を軽減させること、つまり、右室拡張末期圧、左室拡張末期圧を低下させる効果があります。拡張末期圧の低下は、拡張末期容積の減少の結果ですので、心拍出量は低下します。ただ、特に非代償期の心不全の場合には、拡張末期容積の減少に対する心拍出の低下はほとんどみられないか、わずかであることがほとんどです。さらに、血行動態的に疑似的な収縮性心膜炎状態(hemodynamic CP)になっているようなときには、右室の拡張末期容積を減少させることで、心拍出量が増加することもあります。(フランク・スターリングの下行脚の一つの形)
心不全がなぜ急性増悪するのかは別テーマで述べますが、心不全の急性増悪は、酸素需要が一時的に増加し、それに合わせて心拍出量を増加させようとするものの、正常な心臓より拡張末期容積を増加させてもそれを満たせず、悪循環的にどんどん末期圧が上昇してしまうか、実は必要な拍出量に達しているのに、センサーがいかれていて酸素需要を満たしていることに気付けずに錯覚してしまうことから始まると、私は考えています。
心不全の原因で多い薬の飲み忘れも、静脈潅流が増えますので、利尿薬の飲み忘れも、心拍出量は上昇することということなるはずです。
つまり、急性心不全の奏で、慢性心不全の急性増悪では、心拍出量が普段よりも増加していることのほうが多いと考えられます。
もちろん、心筋炎による急性心不全では純粋に突然の心機能低下による低拍出が生じますし、重症心不全などでは、hemodynamic CPとなって、急性増悪であっても、心拍出量が低下していることは多々ありますので、こういうときの見極めが重要になります。
(見極めなくても、血管拡張薬を使わなければいいだけですが)
多くの非代償性心不全では、血管拡張薬によりそれほど心拍出量の低下を意識する必要はありませんが、低潅流流がある、もしくは低潅流がありそうなグレーゾーンの場合には、血管拡張薬の使用は危険です。一気に病状が悪化し、薬剤投与では代償できず、IABPやECMO, IMPELLAなどの機械的なサポートが必要になることもあります。
血管拡張薬について、具体的に。
さて、具体的な薬剤のお話です。
ミオコールやニトロールは基本的にNO供与体といわれ、NOを平滑筋に作用させます。カルペリチドは、平滑筋の受容体に結合して作用します。どちらも、cGMPを平滑筋細胞内で増加させ、ミオシン軽鎖に脱リン酸化を起こすことで平滑筋を弛緩させます。
これらは基本的に静脈を拡張させ、前負荷を軽減させる薬剤となります。また、ある用量以上では末梢動脈も拡張させて、後負荷の軽減作用もあるとされています。ただし、そのような場合でも静脈は拡張されていますので、前負荷が低下している点には注意が必要です。
ニコランジルは、少し特殊で、NO供与を行うだけでなく、K-ATPチャンネルも開きます。このNO供与以外のによる血管拡張作用があるため、低用量でも後負荷を軽減させる効果があるとされています。
NO供与体が通常の用量では動脈拡張をさせないというのは、東北大学循環器内科の研究が参考になります。末梢の血管抵抗がつくられるレベルの終末細動脈などでは、血管内皮のeNOSから、NOではない別のEDHF(=H2O2ではないかとされています)が作られ、それによって血管の弛緩が起こると報告されており、これであればNO供与体であるミオコールやニトロールでは動脈の末梢血管抵抗を下げられない理由になります。
他の機序による血管拡張薬としては、高度な血圧の上昇を伴うときに使用する薬剤で、主に動脈系に作用し、心臓に陰性変力作用(収縮を弱める)もあるニカルジピンや、強心作用とともに血管も拡張させるドブタミンやミルリノン、オルプリノンがあります。
ニカルジピンは、平滑筋の収縮に重要な役割を果たしているカルシウムの流入を阻害することで、カルシウムーカルモジュリンの複合体の濃度を減らし、血管を弛緩させます。これは、他のカルシウムチャネル阻害薬と同じ機序です。
繰り返しになりますが、私は静脈の血管拡張薬は呼吸管理の一環であると考えており、酸素投与などで呼吸管理が行えているときには、特に必須ではないと考えています。
また、血圧が高い時には、その血圧が呼吸困難を悪化させている(#)のなら、低下させる必要がありますが、少なくとも呼吸管理ができていれば、血圧が高いことが肺うっ血を増悪させていたとしても、別に血圧を下げる必要はないのではないかと思っています。
(#血圧が高いということは末梢血管抵抗が上がっているということであり、それは後負荷上昇であり、左室拡張末期圧を上昇させ、肺うっ血を増悪させる)
特に、高齢者の場合には、腎臓にそれなりの灌流圧がないと利尿の反応が悪くなる可能性もあり、血圧は呼吸管理ができている限り、血圧は多少高め(収縮期血圧で160程度くらい)でもいいのではないかと思っています。
さらに、高齢者は持続の静注薬で行動を制限されると、不穏が悪化します。不穏で寝られない、体動が多くなる、興奮するなどが起これば、これらのほうが心不全にとっては治療を阻害する因子となります。ですので、私は、できるだけ持続点滴はせずに、ルートはキープしておいたとしても、利尿薬を尿量に合わせて静注するくらいにしか使わないようにし、血管拡張が欲しいときにはフランドルテープなどで対応するようにしていました。
また、血管拡張薬で何かいい効果があると報告されている(慢性期への影響など)のは、ニコランジルくらいで、他の薬剤には、そういった報告はありません。
あと、カルペリチドには、カルペリチドにしかできないことはあります。僧帽弁疾患の時です。僧帽弁疾患、特に僧帽弁の狭窄や、人工弁不全で左房が伸び切っているときには、ANPの分泌が極端に低下していることが示唆されており、そういう時にはカルペリチドを使用すると、尿量が確保させることはあるようです。それ以外の一般的な心不全に対しては、少し利尿作用もある血管拡張薬であり、あくまで血管拡張薬であることは忘れてはいけないと思います。用量依存性にあるのは血管拡張作用であり、利尿作用ではありません。利尿が欲しい時には、他の薬剤を使いましょう。
血管拡張薬の具体的な使用方法を述べていきたいと思います。
何度も繰り返しになりますが、血管拡張薬を、私は呼吸管理の一環と考えています。
心不全だから、血管拡張薬という風に素直にいかずに、すべての治療でそうですが、目の前にある心不全に対して、どうして血管拡張薬を使用するのかを考えてから使用していただきたいなと思っています。
具体的な使用薬剤
①ミオコール
ニトログリセリン製剤は、アルコールの代謝にかかわるALDH2という酵素が関連して、NOが産生され、そのNOによって、血管の弛緩が生じます。また、
長期連用(一般的に24時間以上)すると、ALDH2のSH残基がニトロシル化を起こして失活し、耐性を起こすとされています。また、ALDH2に異常があると(お酒に酔いやすい人)、パーオキシナイトライトが産生され、
血管や心筋などの障害が起こることが示唆されています。使いやすいということはあるかと思いますが、24時間以上持続投与する場合には、他のニトロールやニコランジルを使用することをお勧めします。
使用方法としては、血圧がある程度以上高い場合(180mmHg程度)には、個人的にはミオコールスプレーを使いますが、ミオコールを希釈なしで、2ml程度静注して、その後、2ml-3ml/Hで持続静注し、その後、血圧をみつつ、2-4ml/Hずつ程度増量していくことになります。
減量の基準は、よくわかりませんが、呼吸管理の一環とみなしたときには、呼吸が落ち着いて(SpO2、呼吸数など)から下げる。循環・うっ血の治療だとしたら、利尿がついてきたタイミングだと思います。
強心薬は少しずつ減量するのにこしたことはないです(ドブタミンで1-2日で0.5-1γ)が、ミオコールは2-4ml/Hずつを1日に数回程度の頻度でどんどん減量していっても大抵大丈夫です。
強心薬は、心臓や循環がある程度依存してしまう傾向があるように思います、そのため、心臓と体があまり気づかない程度に慎重に減量する必要がありますが、うっ血は一旦改善すれば、血管拡張薬はあまり必要ない状態がほとんどですので、どんどん減量しても大丈夫です。
注意する副作用は、あまりありませんが、頭痛は比較的多いと思います。特に開始時というよりは増量時に多い印象があり、頭痛が出てきた場合には、減量する必要があります。
②ニトロール
硝酸イソソルビドという種類に含まれる薬剤になります。一硝酸イソソルビドであるアイトロールと、二硝酸イソソルビドであるニトロールやフランドルがあります。違いは、イソソルビドのヒドロキシル基が1つ硝酸化されているか、2こ硝酸化されているかの違いで、臨床でこの違いを意識することはありません。私は、心不全の治療では静注で使うならニコランジル or ニトロール。ほとんどの場合で、フランドルのテープ剤を貼ることで治療としていることがほとんどです。ミオコールなどと違い、耐性や活性酸素などの発生はないか、少ないと考えられています。
使用の方法は、おおむねミオコールと同じです。ニトロールの原液を2-4ml/H程度から開始して、高血圧をどうしても下げたいとき以外は、30-60分程度でゆっくりと増量していきます。心不全では、すぐに血圧を下げたい時には、ミオコールのスプレーか、静注でニトロールを2ml程度を使用しつつ、その間に、ミオコールやニトロールなどの持続静注薬を投与して、ミオコールで下げた血圧を維持するようなイメージになります。
また、ミオコールと違って、耐性は生じないため、比較的長期の連用が可能となります。ただ、血管拡張薬をだらだらと流すよりも、経口か経管が可能であれば、その間に経口内服薬であるACE阻害薬などを調整するほうが有用と考えられます。血管拡張薬を投与しているときには、血圧に余裕があるときがほとんどだと思いますので、ひとまずの呼吸管理が済んだら、利尿薬を積極的に使用して溢水の治療を行うことでうっ血の治療を行っていきます。
③ニコランジル
ニコランジルは、硝酸としてのNO供与体による作用と、K-ATPチェンネルを開口させることで血管平滑筋を弛緩させる効果があるため、ニトロ製剤だけでは拡張が困難な動脈の終末細動脈などの弛緩・拡張を促します。
平滑筋の一定の血管の径の維持(収縮・弛緩)には、カリウムチェンネルが非常に重要な働きをしています。カリウムは、心筋でも収縮の時間を決める重要な因子(いわゆる収縮の第2相を決める因子)であり、収縮弛緩を繰り返さない血管においてはトーヌス(緊張度)を調整するのに、カリウムの出入りを非常に重要な因子となります。
さて、ニコランジルは狭心症や冠動脈のカテーテル治療中に使用されるかと思いますが、心不全でも有用な薬剤です。
血管拡張薬ですので、使う状況としてはミオコールやニトロールと同じで、肺にうっ血があって、それによって呼吸困難などの症状が出いて、一時的に静脈系の血管を拡張してうっ血を軽減させたいときに使用することになります。
また、ニコランジルは、末梢の動脈も併せて拡張させるため、末梢血管が作る後負荷を軽減して、左室拡張末期圧を下げる、または状況によっては心拍出量を増やすという効果が期待されます。もちろん用量に依存しますが、過度または不要な血圧の低下も他のNO供与体と比較して起こりにくいとされており、確かにそうかなという実感もあります。
このため、私は静脈の注射が必要な心不全にはニコランジルを使うことが多かったです。ただし、病院によっては採用しているバイアルが小さいのしかないときには、医療側の問題で使用を躊躇されることもあるのが残念なところです(12mgバイアルしかない場合、4-8バイアルが必要になるため)。48㎎バイアルがあるときには便利です。
投与方法としては、2mg/Hくらいから開始します。ちょうど48mgバイアルがあれば、一本を1日で使う感じです。増量は、2mg/Hか4mg/Hずつ増量します。8mg/H程度で十分なことが多いように思います。
ちなみに、ニコランジルは、血管拡張薬の中では患者さんの予後をよくするという臨床結果のある薬剤であるというお話をしました。
販売されている国が少ないので、大きな臨床研究はありませんが、おおむね心不全の入院や心疾患の発症などを押さえていると思います。
投与方法は、急性期から持続静注を行って、その後経口内服を継続しているか、初めから経口内服を行っているかのどちらかなので、急性期の持続静注だけでの効果が証明されているわけではないので注意が必要です。
④カルペリチド (hANP)
カルペリチドは、心房由来のナトリウム利尿ホルモンであるANPの遺伝子組み換えの製剤です。
薬理作用ですが、血管の平滑筋と腎臓に作用します。心臓などへの作用もあるようで、J-windの中のANP試験で、急性心筋梗塞後に使用すると予後にいい作用(心臓死と心不全入院が減る)があるとの報告(#1)がありますが、心不全に対する投与ではないので端折ります。(#1 Lancet. 2007 Oct 27;370(9597):1483-93)
2025年に改訂された心不全のガイドラインでも記載されているように、有用な報告は、小規模なものに限られる(PROTECT, Circ J 2008; 72: 1787–1793)一方で、使用により入院中の新事故発生率が高いという報告が散見される(J Card Fail. 2015 Nov;21(11):859-64、Int J Cardiol. 2019 Apr 1;280:104-109)ため、積極的な使用は慎重になるほうが良いと思います。
カルペリチドの具体的に使用用法としては、少量から開始し、必要があれば増量するということでいいだろうと思います。
具体的には、0.01γ(=ug/kg/min)程度で開始して、0.005 or 0.01γずつ30-60分程度で増量していく感じでいいと思います。
それ以下でしか始められそうにないような血圧の低い時や、低潅流などがあるときには使用する必要はないと思います。
繰り返しますが、増量によって得られるのは、血管拡張作用であって、利尿作用ではありません。利尿が不十分な時には、カルペリチドを増量するのではなく、利尿薬を積極的に追加投与するほうが有効です。
次: 急性心不全治療 (5) : 急性期の心拍数の管理について
補足:
血管拡張薬の生理学
すこしだけ生理学的な話を追加します。 ニトロ系製剤の血管拡張薬の主な作用はNOを増やし、NOが血管平滑筋に作用することで、血管を弛緩させるということになります。血管内皮にeNOSという酵素があって、これが内皮にかかるずり応力(流体の進行方向に平行にかかる力)などにより活性化すると、Lアルギニンに作用して、NOを産生します。このNOが平滑筋に作用して、血管を拡張させるようなシグナルを送って、最終的にはミオシン軽鎖が脱リン酸化されて、血管は弛緩します。
このシグナルの中心が、PKGというリン酸化酵素を制御するcGMPの濃度ということになります。このcGMPが増えれば血管は拡張し、減れば収縮します。NOや他のEDHF(内皮細胞由来過分極因子=内皮由来血管弛緩因子)は血管内皮から、血管平滑筋内へ入っていって、cGMPを作るグアニル酸シクラーゼ(GC)を活性化させることで、cGMPを増やします。さらに、これにより細胞内のカルシウム濃度の上昇が抑えられ、カルシウム・カルモジュリン複合体の形成が抑制されることを通して、ミオシン軽鎖の脱リン酸化が起こり、平滑筋は弛緩します。
このcGMPは、ANPやBNPが作用するレセプターの下流にありますし、さらにいうと、バイアグラ(PDEV阻害薬)なども、この同じ経路に作用します(このため、バイアグラ内服中の人はニトロ舌下が禁忌になります)
動脈も静脈もリンパ管も、NOやEDHFに反応して拡張するのは同じです。
ただし、静脈は、一部を除いて動脈のように交感神経による制御を受けていません。交感神経の支配を受けている一部が腹腔内臓器の静脈で、この交感神経の制御を受けている静脈系が体の循環血流量の維持に非常に重要な役割を果たしています。
普段は、循環血流量に無関係な血液を腹腔内にプールさせておいて、出血などの緊急時に交感神経が刺激されると、交感神経刺激に反応するプール血液が一気に循環に乗り、循環血流量が増加します。
具体的には、脾臓と肝臓の静脈が交感神経のα受容体を持っていて、出血などの時に、α受容体が刺激され、静脈が収縮することで、肝臓と脾臓から血液が一気に右心系に戻ってきます。
このようにして、出血時に循環血液量を維持する機能ですが、電撃性肺水腫の形成にかかわっているとされています。