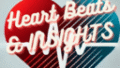- 入院中の心拍管理:モニター心電図のトレンドに留意
リエントリー性不整脈の見落としに注意 - 心房細動での頻脈はよくあるが、洞調律で120bpmとか140bpmの時には要注意。
- 心不全で、徐脈にすると、心室性不整脈が増加することがある。
- ジギタリス製剤を常用していない場合、単回ジゴキシン点滴静注は有用
- すべての頻脈性不整脈に積極的にアブレーションを検討
- 慢性期に頻脈性心房細動でコントロール困難な場合には、Node ablationに両室ペーシングも積極的に検討
- 徐脈の場合には、基本的にはペースメーカ植え込みしかない。
- 具体的な治療:
洞調律:
ジギタリス 0.25mg or 0.125mg 点滴静注(ジギタリスの内服をしている場合はスキップ)
→ オノアクト 0.5 ~ 2γで投与開始し、適時調整
心房細動:
ジギタリス 0.25mg or 0.125mg 点滴静注(ジギタリスの内服をしている場合はスキップ)
I. オノアクトがある → オノアクト 0.5 ~ 2γで投与開始し、適時調整
II. オノアクトがない → ① ~ ③のどれかを実施
①ワソラン 0.5 or 1A 点滴静注を1日3~4回心拍数を見ながら繰り返す
②ワソラン 0.5 or 1A点滴静注した後に、ワソラン 1日 2~4Aくらいのペースで点滴静注開始。
③ワソランの点滴静注はせずに、ワソラン 1日 2~4Aくらいのペースで点滴静注開始。
重症心不全で、ワソランを使用する時には0.1-0.2Aの静注など非常に少量で繰り返すのが安全。
急性期の心拍数の評価:モニター心電図のトレンドに留意
(尿閉やリエントリー性不整脈の見落としに注意)
心不全の急性期に心拍数に対して治療するかどうかは、悩ましい問題です。
救急外来や入院直後の頻拍に関しては、循環不全や呼吸不全に対して治療を行うことで安定することが多いので、基本的には入院して落ち着いた段階で評価して、治療するかどうか検討していくことになると思います。
では、どのくらいの心拍数なら、そのまま様子を見るかという問題です。
循環や呼吸の治療を行い、ひとまず落ち着いて、初回の利尿薬を投与して、利尿がそれなりに得られているような場合であれば、洞調律で120bpm程度以下、心房細動で平均160bpm程度以下なら心拍数が速くても、心拍数に対しての直接の治療介入は必要がないと思います。 (ジゴシン 0.25mgの点滴静注は行ってもよいかとは思います)
ただ、心不全の急性期といっても、洞調律で心拍数を120bpmを超えるのは、おかしいかなと思います。もちろん頻呼吸で呼吸管理がうまくなっていないときなど120bpm前後は多々ありますが、何らかの併存(甲状腺疾患など)や排尿異常(特に尿閉)だけでなく、実は洞調律と思っていたが、よくみるとリエントリー性の心房頻拍などであったということもあるので注意しましょう。
入院時だけでなく、ある程度落ち着いた段階での心拍数に違和感があれば、積極的に12誘導心電図を確認しましょう。虚血用の連続12誘導モニター心電図まではいらないと思います。
ちなみに、洞調律っぽくみえて、140bpm以上が続くときは、絶対におかしいです。何かあります。モニター心電図で数時間単位の心拍数をみていて、洞調律でも心拍数は±10bpmくらいで変動しますが、変動がほぼない(±2bpm程度)時には、洞結節や心房、洞房結節の関与しているリエントリー性の不整脈の可能性があります。この時には、ワソランとか、電気ショックなど有効なことがあります。
12誘導だけでは見落とすこともありますのので、かならず入院中のモニター心電図のトレンド(心拍数の時間経過のグラフ)を確認しましょう。
心房細動の時の心拍数はどのように評価していけばいいかというと、私はモニター心電図のトレンドをみていました。今のモニター心電図は、時間軸の拡大幅に合わせて、秒単位とか、15秒毎とかの心拍数を点でプロットした心拍数の変動をみる点のグラフと、それの平均値を線であらわした平均心拍数のグラフの2種類が表示できます。
大抵初期設定では、心拍数の細かい変動をみるグラフになっていると思います。まず、それをみて、なんとなくの心拍数の幅をみます。例えば、60-120くらいの幅で変動しているなという感じです。特に、これで注意するのは、低いほうで、低い心拍数が多い時には、平均心拍が高くても、高い心拍ばかりに気を取られて、徐脈にすると、pauseといって、心拍の間隔が長くなることがあります。寝ているときに多少1-2秒程度pauseが起こっても、問題ないのですが、心室性不整脈が不安定な人の場合は、このpauseの時に心室性不整脈が不安定化しますので注意が必要です。
ちなみに、心室性不整脈がひどいときには、カリウムをかなり高め(K 5.0-5.5mEq/L)に維持するのとペースメーカが留置されている場合には心拍数の設定を高くすることがあります。
モニターの心拍変動の幅を確認したら、次は、モニターの設定を変更して、平均値を曲線であらわした表示に変更します。私は、心房細動の時の心拍数はこの線の変化で評価していました。
急性期の心拍数に関して、どの程度がいいのでしょうか。
心不全の急性期の人では、心拍数を調整して心拍出量との関係を実際に見るのは困難ですが、今までに報告された様々な研究から不全心では、心拍数80-110bpmの間が、心拍出量(1回拍出×心拍数)のピークとなるようです。
急性期の心不全治療では、先ほどに述べたように、多少脈が速くても心不全治療自体が、循環・呼吸・利尿という点でうまくいっているならそのまま様子を見てもいいと思います。
それで、ある程度うっ血の治療にめどが立ちそうになった段階で、徐々に慢性期治療を視野に入れて、β遮断薬を導入し、徐々に増量し心拍数も併せて評価していけばよいと思います。 β遮断薬の導入のタイミングに関しては、慣れていない場合には、うっ血が完全に解除されて、心不全が代償状態になった時がいいと思います。もちろん、慣れていけば、心不全の程度とか、治療反応性とか、いろいろなものからうっ血が残っている段階からでも導入できるようになると思います。 β受容体遮断薬は、導入や増量のタイミング・仕方を間違えると、心不全を再増悪させてしまう可能性があるので、慎重にいくのが安全です。
頻拍に対する治療(洞調律の時)
循環不全や利尿が不十分で、その理由として心拍数が考えられる時には、心拍数そのものを治療しに行くことになります。
あくまで目安ですが、洞調律の時には110bpmくらいまでは、心拍出量が低下する原因にはなりにくいといわれており、心拍数そのものに介入をしに行くときには、少なくとも120bpm以上というのが目安でしょうか。
具体的な方法としては、薬剤投与ということになります。ワソランは洞調律には効果はありませんので、ジギタリスとオノアクトということになります。オノアクトは、一般名ランジオロールで、超短時間作用型のβ1選択的遮断薬になります。循環器がない施設であれば、採用されていない施設も多いかとは思います。
ジギタリスは、腎機能に注意が必要ですが、単回の投与では、中毒域にはならないと考えています。一応、小さい高齢女性などでは、ジゴシン注0.25mgを0.5A(0.125mg)だけ投与するようにしたり、多少の減量はしていました。ただ、ほとんどの場合には、1回のみの投与で、連投したり、毎日投与したりすることはあまりなく、ひとまず、ジゴシン0.25mg (or 0.125mg)を30分程度で投与して、投与後、1~2時間程度経ったタイミングでも、心拍数がまだ高い場合には、そのままオノアクトを持続で投与するという方針で行っていました。
オノアクトの投与方法は、少量からちょっとずつ増量していくという感じで、開始は、0.5 or 1 or 2γ程度で、1γずつ増量していく感じです。
心拍数を落とす目的は、早すぎると1回心拍出量が低下することが多く、そのため、1分間の心拍出量が減少するのと、頻拍自体がは後負荷を上げるので、それを是正するということになります。また、重症心不全では酸素・エネルギー消費ということも関係してきます。
一般的には、心拍数を下げることで、下がった分以上に1回心拍出量を増加させ、1分間あたりの心拍出量を増やそうとするか、また、心臓の酸素消費を効率化させ必要な心拍出量を軽減させるのが目的になります。オノアクトは、陰性変力作用がありますので、いきなりある程度の量を投与すると、低拍出が悪化することがあります。このある程度の量というのが、人によって違うので、あくまで低用量から、少しずつ増量していくということが安全だと思います。
また、手持ちのデータでは、40人ほどオノアクトを使用していて、きれいに半数にジゴシンの先行投与を行っていました。ジゴシンの先行投与を行っていた患者さんたちのほうが、主治医が適切だと思う心拍数に到達したときのオノアクトの使用量が半分で済んでいました。
かなり限られたデータですので、一般化はできません。ただ、どちらを使うかというよりことではなく、私は心拍数を管理する時には、基本的に透析や腎不全でもジゴシン(0.25 or 0.125mg)を先行投与し、そのあとでオノアクトを使用するというようにしていました(もちろん、普段からジゴシンを服用している人には血中濃度的に危ないので、オノアクトだけでいい思います)。
ちなみに、最終的なオノアクトの投与量は、平均2γ程度で、最大でも4γほどでした。
慢性期を見越して、アーチストやメインテートといった、左室収縮率の低下した心不全の慢性期に有効なβ受容体遮断薬を心拍数の管理目的に少しずつ導入することも可能だと思います。
ただ、急性期に、心不全の治療管理に慣れていないときには、β受容体遮断薬の導入は心不全のさらなる悪化を起こす可能性があるために注意が必要です。
ビソノテープも使用することは可能です。内服よりは、立ち上がるもゆっくりで、何かあった時のも中止後の血中からの薬効の消失は早いので、内服よりも安全な可能性もあります。保険適応の問題に注意が必要ですが(拡大していくと思います)、内服よりも安全に使用できる可能性は高いと思っています。一応、ビソノテープ 4mg(1枚)=メインテート 2.5mgが等価とされています。
心不全の急性期の心拍数管理に使用する時には、ビソノテープを4分割して、1mgで開始するのが安全です。メインテートで0.625mgであり、大体そのような感じになると思います。ただ、4分割すると結構はがれやすいので、優肌絆などで上からさらに固定する必要があります。
イバブラジンに関しては、基本的には、心不全の基本的な内服加療がされている代償状態のHFrEFで、洞調律かつ心拍数が一定よりも早いというのが条件なので、急性期の心拍管理には使うことはありません。
頻拍に対する治療(心房細動、心房粗動の時)
心房細動の時には、ジギタリス、オノアクトに加えて、ワソランやヘルベッサーも有効になります。
また、特に初回の心房細動では電気的除細動をどのタイミングで行うかというのも、重要な選択になります。
心房細動は、洞調律に比較して、慢性期と比較した心拍数の増加の度合いは大きくなります。どういうことかというと、心不全が代償されている安定している状態の洞調律と心房細動の人がいて、それぞれ平均の心拍数は80bpmだとします。この二人が同じような心不全の非代償状態となった時でも、洞調律では100-110bpm程度でおさまることが多かったとしても、心房細動の人では容易に平均で140-150bpm程度になります。
同じような交感神経の暴走が起こったとしても、洞結節よりも房室結節のほうが、興奮が起こりやすいと思われます。
心房細動の頻拍で平均140-150bpmだったとしても、もちろん心不全の治療自体がうまくいっているのであれば、急性期に積極的に心拍数をコントロールする必要はないと思います。
ただ、心不全治療に対する反応が悪く、心拍数が原因の可能性として考えられる時には、洞調律の時と同じく治療ターゲットとなります。
心房細動の時にも、基本的にはジギタリスを使って、そのあとにオノアクトで調整していくということでいいかと思いますが、オノアクトがない施設もあると思いますので、その場合には、ワソラン 0.5Aの点滴静注か、持続静注で対応することになると思います。
ジギタリス 0.25mg or 0.125mgを30分で投与して、オノアクトがあれば、オノアクトを 0.5 or 1 or 2γで開始して、少しずつ増量し、オノアクトがないなら、ワソラン 0.5 or 1Aを30分程度で点滴静注するか、心機能などによっては、ワソランを1日2~ 4A程度のペースで、持続静注を開始するというのもいいと思います。ただ、この場合には、循環不全の有無を評価し、循環不全があるなら、強心薬を先行して投与開始するほうが安全です。
・ジギタリス 0.25mg or 0.125mg 点滴静注
オノアクトがある → オノアクト 0.5 ~ 2γで投与開始し、適時調整
オノアクトがない →
①ワソラン 0.5 or 1A 点滴静注を1日3~4回心拍数を見ながら繰り返す
②ワソラン 0.5 or 1A点滴静注した後に、ワソラン 1日 2~4Aくらいのペースで点滴静注開始。
③ワソランの点滴静注はせずに、ワソラン 1日 2~4Aくらいのペースで点滴静注開始。
洞調律よりも心房細動の時には、長いpauseが出やすくなります。
徐脈やpauseの時に心室性不整脈は出やすくなりますので、モニターなどで心室性の不整脈などの出現に注意してください。
ワソランやヘルベッサーは、オノアクトに比べて陰性変力作用が強い傾向にあるのと、薬剤中止後の薬効の切れるのが遅いので、より一層の注意が必要です。
個人的には、低心機能の心房細動には、ジギタリスとオノアクトで調整できる範囲で調整して、ワソランまで使うことはあまりありませんでした。
低心機能で重症心不全に、ワソランを使用した経験としては、発作性上室性頻拍が合併していて、その時に止まるまで使うということはありました。
また、オノアクトが発売されるまでは、心房細動でも時折使うことはあり、使用方法としては、すごく少量を静注します。0.5-1mg(0.1-0.2A)程度を静注し、様子を見ます。反応があるようであれば、1日換算でワソラン 2.5-5mgを投与するような低濃度で持続投与します。
心房細動や心房粗動の時に、心拍数を落とすことでの安全性の評価として、RR間隔が伸びた時に、outputがどれだけ増えるかをエコー(LVOTのVTI)で評価するというのは一つの方法として有用です。
心房細動の時には、RR間隔は不定ですので、しばらくエコーを構えておいて、RR間隔が長い時の、outputがどれだけ増えて、どの程度になるのかを評価すれば、心拍数を下げる効果を予測することができます。
心房粗動に関しては、じっと待っていてもなかなか伸びてくれないと思いますので、ワソランを片手に、少しだけ静注して、2:1伝導の中に、時折4:1伝導が現れるようにして、2:1の時と、4:1になったときのoutputの変化をみます。4:1になったときに、もし、2:1の時とoutputが変わらなければ、心拍を落とすのは危険です。そのまま完全に4:1にしてしまったら、純粋に心拍出量は半分になり、より循環不全が進みます。しっかりとoutputが増えれば、ある程度の自信をもって、ワソランの持続で4:1くらいの心拍数に管理をすることができます。
また、電気的な除細動や除粗動を行うことも、考えなければなりません。
洞調律に復帰し、維持することができれば、ある程度適当な心拍数でコントロールもできますし、洞調律になること自体で拡張末期圧が低下しますので、心不全のコントロールはかなりしやすくなります。
ただし、電気的な治療を行うに際して、基本的には経食道エコーが必要ですが、ある一定期間抗凝固薬を十分に服用しているのがわかっているときには、経食道エコーは省けます。
経食道エコーは、特に慣れていない人しかいない施設では、受ける患者さんにそれなりの負担とストレスを与えますので、呼吸状態の悪化が懸念されます。
除細動で、一瞬心停止が起こります。静脈からのある程度の還流は続きますので、心臓から血液が出ないのに返ってくるという状況となり、特に右心系を中心とした拡張末期圧の上昇という結果になりますので、心不全が一段と不安定化することもあります。
ある程度安定している状況であったり、もう気管挿管されているような状況であれば積極的に行ってもいいと思います。
心不全が安定したら、特に初回の心房細動や心房粗動は除細動しておきましょう。
積極的にアブレーションを検討することも重要
私は、アブレーションをする立場になったことはありません。心不全合併の心房細動に対しては、最近のエビデンスからもできるだけ早期にアブレーションを検討し、アブレーション専門医に相談するのが良いと考えています。
もちろん、心房細動以外のリエントリー性のものに関しては、アブレーションをしてもらうほうが良いと考えています。
慢性期に頻脈性心房細動でコントロールが困難な時には、
AVnodeアブレーション + 両室ペーシングも選択肢
心房細動に対するアブレーションの適応がなく、βブロッカーを認容できる範囲で投与し、アンカロンなどを適切に使用しても心房細動による頻脈によって心不全のコントロールが安定しないときには、AV node アブレーションと両室ペーシングを行い、心拍管理を機械的に制御するというのも有用です。
侵襲的で、不可逆的であるので、すぐに実施というのは困難かと思いますが、甲状腺などの検索や可能な範囲での薬剤調整を行ってもなお心房細動の頻拍で心不全の状態が不安定である場合には、考慮される治療だと思います。
多くはないですが、ある程度の施設であれば、紹介患者も含めれば1年に1名程度は候補に挙がるのではないかと思います。
急性心不全時に徐脈を呈しているとき
急性心不全の時には、一般的には普段よりも脈は速くなります。
しかし、明らかな徐脈になっていたり、心不全の急性期のわりには徐脈になっていることがあります。
脈が半分になったとしても、拡張機能に異常がない場合にははうっ血性の心不全にはなりにくく、多少の徐脈性不整脈で心不全をきたすということは拡張機能に異常があるということになります。
徐脈が心不全増悪の主因である場合には、経静脈的にペースメーカを一時的に使用して、脈を80bpmとか90bpmに調整し、適時利尿薬を使用すれば心不全は代償化できると思います。この時に、右室ペーシングとなりますが、HFpEFの場合であれば、右室ペーシングとなることでの心機能への影響は少ないと思います。
左心機能が低下しているような場合には、一時的ペーシングの場合、房室結節が正常であれば、右房ペーシングを行ってできるだけ右室ペーシングにならないように試みることも重要ですし、特殊にはなりますが、一時ペースメーカでVDDのような形で使用できるカテーテルもありますので、そのような特殊なカテーテルの使用も考慮されます。
房室結節が不安定であれば、右室ペースをせざるを得ないかと思いますが、できるだけQRS幅が狭くなるような位置に留置したりすることも試みたいですが、場所がずれてしまっては意味がないので、安定している場所が最優先にはなります。経静脈ペースメーカのリードは、硬いので冠静脈にいれて左室ペースをするのはお勧めしません、危険です。
一時的な原因による徐脈であれば、原因を解除して様子を見ればいいですし(圧倒的に薬剤性が多い)、はっきりとした原因がない時には、心不全が代償されたころに、植え込み型のペースメーカを植え込むことになります。
また、もともと植え込み型ペースメーカ患者であれば、心拍数の設定を、慢性期と急性期で変更したりすることが有効な時もあるので、心不全の急性期だけ調整するかどうかも選択肢として考慮しなければなりません。
薬剤で心拍数を上げにかけることもできますが、プレタールで心房細動の脈が少し早くなるくらい現状では期待できません。
徐脈性心房細動の時に、プレタール内服を行うと脈がある程度早くなることが知られていて、確かにある程度心拍数が速くなりますので、出血傾向に特に注意がいらない場合には選択肢になります。テオフィリンも脈を速くする作用がありますので、使用を考慮されますが、効果は限られます。
注射剤でも、いくつか脈が速くるようなものはあります。β刺激薬のイソプロテレノールや、硫酸アトロピンです。
これらの治療薬を心不全の時に使用することは稀ですが、イソプロテレノールは洞結節の不全と徐脈となるようなときに、経静脈ペースメーカや植え込みまでの一時しのぎに使います。
また、硫酸アトロピンに関しては、心停止の時の治療中や、心筋梗塞の高度な徐脈の時以外に使用したことはなく、心不全に基本的には使用しないほうがいいと思いますが、薬理作用的には、使ってはいけないわけではないように思います。薄く溶解して持続するのもいいのかもしれません。薬理的には、副交感神経系の伝達物質であるアセチルコリンを阻害する薬剤であり、副交感神経の支配が関係している部位にしか作用しないため、房室伝導以下のHIS束以下での房室ブロックに対しては無効となります。
このような注射による方法は不安定ですが、今後、さまざまな社会的な理由でこういった一時しのぎを行わなければならない心不全治療も増えてくるのかもしれません。
補足:心不全と心房細動とジギタリスと
ジギタリス製剤は、心房細動によく投与されているのをみかけますが、慢性期の心房細動の患者に投与するのは、エビデンス的には、有害な可能性がありますので、心房細動を伴う心不全患者への投与は勧められません。
ジギタリスの作用としては、Na/Kチャンネルを阻害します。すると、Naの心筋細胞外への流出が障害されるため、かわりにNa/Caチャネルの作用が亢進することで、細胞内にCaイオンの流入が増え、心筋に陽性変力作用をもたらします。
また、ジギタリスは副交感神経の作用を亢進させます。副交感神経の活性化は心筋の収縮性への影響はありませんが、洞結節や房室結節などに対しては、分極を阻害する作用があり、結果として脈が遅くなります。特に、心拍数が100bpm以下では、副交感神経による心拍数のコントロールが強くなるとされています。このため、運動時や心不全などで交感神経の亢進によって100以上に心拍数がなっているときには、心拍数を抑える効果はあまりなく、このあたりの心拍数をコントロールできるのは、β受容体遮断薬ということになります。
そのため、労作時の頻拍によると考えられる症状を押さえに行くときには、β受容体遮断薬が必要になります。
さて、ジギタリスの非常にいいところは、陰性変時作用(脈を遅くする作用)を持ちながら、陽性変力作用をもつという心不全には使うには大変使いやすい薬ということになります。
このような性質のある薬剤ですので、大規模な臨床試験も行われています。それがDIG試験(N Engl J Med. 1997; 336: 525-33)です。
この試験で最も重要な点は、洞調律でLVEFの低い(<45%)の心不全患者に投与されたということです。(>45%はサブ試験として行われ有用性はなかったとされています)
心房細動の患者は除外されていますので、心房細動の心不全患者への投与は一切行われていないということになります。
試験結果に関しては、生命予後の改善はありませんでした。そのため、無条件にこの薬剤を心不全の人に使用するということにはなりません。
ただし、心不全の入院は減らしそうだという結果が付随的に示されており、また、血中濃度が低濃度(0.3-0.8)であれば、死亡率は低そうだと(不整脈などの有害なイベントが少ないのかもしれません)いうことです(JAMA. 2003; 289: 871-8)ので、心不全の入院を繰り返しそうな洞調律の心不全患者へ低血中濃度を維持するような用量で投与するのは有効だと考えられます。
さて、では心房細動の患者への投与はどうかというと、残念ながら前向きの臨床試験はありません。
ただ、この10年ほどで行われている新規の抗凝固薬(NOAC, ないしDOAC)の臨床試験の中で、ジギタリスを用いられている心不全の人は、心疾患に関連するイベントが増えているという結果が複数報告されております。だいたい、同じような結果が得られているので、真実である可能性が高いと考えられます。
そのため、心房細動患者へのジギタリス製剤の投与は現時点では勧められません。
ただし、低拍出による症状に対して経口強心薬としてしようするのは有効です。この有効というのは、予後をよくするとかどうとかということではなく、純粋に強心作用があって、低拍出による循環不全の症状が緩和されることはあるという意味です。
この低拍出による症状に対して、ピモベンダンやジギタリス製剤といった経口強心薬を使用するというときは、心不全のStageDであると考えます。そのために、心臓移植の適応がなければ、できるだけのことをやって、だめそうなら緩和医療ということになります。
緩和医療の定義はいろいろありますが、ここでは予後をよくするが今をよくするわけではない治療を積極的には行わない、また、一歩進んで、予後を悪くする可能性はあるが、今の症状を緩和させるための治療を優先して行わなければならない終末的な段階とします。
この段階においては、ジギタリスはある程度血中濃度が高いほうが強心作用が上がりますので、中毒症状に注意しつつ1.0-1.5といった正常高値の血中濃度まで増量することもあります。
ピモベンダンを使って、ジギタリス製剤もある程度の濃度で使用すると致死的な不整脈などの出現の可能性は出てきます。しかし、今の症状をとることが優先される段階なので、それも仕方ないと考えまず。また、患者・家族にも、不整脈などによる死の訪れが速くなる可能性があるが、今ある低心拍出による循環不全の症状をとるには、これの治療が有効だと説明する必要はあります。