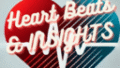うっ血・溢水の治療:利尿薬
心不全の治療で、循環不全と呼吸不全に対する評価と治療を行ったら、次はうっ血の解除です。
多くの心不全では、うっ血を起こして、余分な水が溜まっている状態(溢水)ですので、トータルの水の管理、体内の水分を適切な量にすることは重要です。
(一部の心不全では血管の中の水の分布の異常によりますが、この場合でも大概は溢水傾向が事前にあり、まったくその傾向がないものはかなり少数です)
水の管理としては、利尿薬か、機械的な除水 (ECUM, extracorporeal ultrafiltration method)による治療になります。
利尿薬に反応が鈍い場合には、再度循環不全の有無を評価をして循環の問題であると判断されれば、速やかに強心薬を導入し、腎臓の問題や利尿薬抵抗性のような状態であれば、利尿薬の変更や増量、状況によって速やかにECUMを導入することが、特に呼吸状態が不安定な場合には重要だと思っています。
うっ血の治療には、血管を拡張させることで一時的にうっ血を軽減させることは可能です。ただ、血管拡張薬は、全身のうっ血を軽減し、その結果として肺のうっ血を軽減させて、呼吸を楽にするというのが主たる役割になります。血管拡張により、循環動態が改善し、利尿薬の追加投与をせずとも利尿が得られ、水分コントロールがなされることはあります。ただ、基本的にはうっ血・溢水の治療は利尿薬が中心となります。
あくまで、血管拡張は呼吸管理の一環で行われるのがいいだろうと思います。
心不全の増悪は、余分な水が貯まっている状態
心不全の増悪状態では、余分な水が体にたまっていることがほとんどです。
一部の心不全では体内の水の分布が一過性に異常を起こすことでおこりますが、これだけで生じている急性心不全はまれで、水が貯まった上で、分布の異常が合わさることのほうが多いです。分布異常の要素が強い場合、具体的には、浮腫や胸水がたいしてない割に、肺うっ血・肺水腫を起こしている場合には、血圧や循環不全に十分留意し、血管拡張薬を使いつつ、利尿薬を併用していくということになります。
こういう場合でも、心不全の急性期の治療は、この余分な水を体外に排除し、体内の水分量をいかに適正にするかが目的になります。
まず、利尿薬を中心に記載しようと思います。
利尿薬について
大きくは、注射薬と内服薬にわけられて、それぞれにナトリウム利尿薬と水利尿薬に大別されます。
急性期の治療は、静注を中心に、徐々に慢性期を見据えて内服に移行していくことになります。
注射薬は、主にはラシックスとサムタスになります。
補助的な薬剤として、ソルダクトンとハンプがあります。ソルダクトンを使うなら、内服のアルダクトンを使えばいいかなと思いますが、使って悪いことはありません。ハンプは使っても使わなくても、どちらでもいいですが、循環不全に使うと一気に血行動態が破綻しますので、禁忌といえます。利尿を目的に投与するときは、僧帽弁狭窄などかなり特殊な状況に限られます。
私はどちらも基本的には使用しません。
ラシックス静注(10mg or 20mg)から始める。
では、まずラシックスの使い方ですが、もちろん正解などはなく、あくまで、私はこうしていたというやり方をお話しするだけです。
急性心不全の人がきたら、救急外来か、入院直後に、ラシックス 10 or 20mg 静注して、30-60分程度で反応をみて、その後のことを決めるという感じです。
さて、次の手としては、
- ラシックス静注の追加・反復投与
- ラシックス持続静注
- サムタス点滴静注
- サムスカを含む内服の追加
- 高張食塩ラシックス療法
(0.9% NaCL(生食) 50ml (or 100ml) + 10% NaCl 20ml + ラシックス 1~5A; 30分~2時間程度で投与) - ECUM
ということになります。
30-60分というのは、ある程度逼迫した心不全増悪の患者ということになり、歩いて外来に来たような人であれば、4時間とか6時間程度の時間でみればいいと思います。
一番最初の投与するラシックスの量を決めるのは、心機能というよりは、腎機能と性別、年齢(体格ともいえる)でした。
基本は、20mgを選択することが多くて、その中で、例えば、腎機能が正常(eGFR>60)で、小さい女性なら、ラシックス10mgとか減量して投与していました。正直、20mgで出過ぎたところで、初回単回であれば、それほど問題となることは少ないので、20mg一律投与でもよいかとは思います。
ただ、付け加えるなら、初回心不全入院とか、もともと利尿薬を飲んでいない人はラシックスがよく効くので、10mgでもよいと思います。
悩んだら、呼吸状態をみて、呼吸が安定していれば、少量を投与し、30分での反応をみて、追加投与するかどうかを決めるでいいと思います。
腎機能正常なHFpEFなら、結構これだけで利尿は十分ついて、速やかに内服に移行してもうまくいくことも多いですが、ある程度悪い心機能・腎機能や心不全の急性増悪を繰り返しているような患者の場合には、追加に何かしないといけないことが多いです。
利尿の評価は、時間当たりの量だけではなく、薄さも重要です。尿道バルーンを留置しているなら、管腔内の尿の色がバルーン入れた直後の尿よりも薄い尿が流出していれば、利尿薬に反応していますので、2時間の尿量をみて、その段階で、2時間で120ml以上のペースで出ていれば、ひとまずOKかなと思います。その後、4時間、6時間とみて、そのあたりでラシックスの効果は切れてきますので、その段階の尿量をみて、追加でラシックスを静注するか、持続投与するか、その日はそのまま見て、翌日から内服を調整にかかるかなどでいいと思います。
利尿薬に対する反応が良ければ、尿道留置カテーテルの中に、薄い尿がみられるようになりますが、これは、尿がたくさん出ると、電解質以外の生化学検査項目(UN, Cr, UAなど)が薄くなりまることによります。
この薄い尿をラシックス尿と私の周りは言っていますが、これがでれば、利尿薬に反応しているということになりますので、尿量自体はその時は少なくても、いずれ、たくさん出てくる可能性があります。
反応がないときには、早い目に、フロセミド20mg静注追加か、2時間程度の段階で利尿が悪く、入院時の血液検査で、血清Naが143を超えていなければ、サムタス 8mg投与もよいと思います。
サムタスに対する利尿の反応は、同じように尿の濃い・薄いのをみつつ、時間としては2-4時間程度の尿量で判断できると思います。
ちなみに、ラシックスで出た尿は、ラシックス投与前の尿と比較して、尿生化学では、Na,Clが高く、Kが少なくなり、UN,Cr,UAは尿量の逆数と比例します。サムスカで出た尿は、Na,Clはほとんど変化なく、UA,Cr,UAはラシックスと同じように尿量の逆数と比例します。さらに、SGLT2阻害薬投与後の尿は、若干Na,Clの上昇を伴いますが、これは浸透圧利尿で説明できる範囲ですので、別にナトリウム利尿作用というわけではありません。
忘れがちですが、心・腎機能によっては早期にECUMなどの機械的な除水というのも検討しなければなりません。特に重症の心不全治療では機械的な治療というのを常に意識しなければなりません。
2日目になっても、フロセミド静注の反応も悪いし、サムタスの反応も悪い(ないし、すでにサムスカ 15mg服用状態)、そのうえで、機械的な除水の適応がない場合には、高張食塩ラシックス療法が候補に挙がります。
私の高張食塩は、生食 100mlか50mlに、10% NaCl 10~20mlを加え、そこのラシックスを 1~5A混ぜて、30分~2時間くらいかけて投与するというものになります。
それなりに高張になるので、患者さんの血管痛などによっては、生食100ml + 10%NaCl 10mlとか薄めに作ったりします。
この治療のイメージとしては、腎臓の尿細管にClを補充しながらラシックを効かせている感じです。サムスカの販売前には結構やっていましたが、サムスカ販売後しばらくはやらなくなっていました。しかし、最近はサムスカ15mg内服している状態で、急性増悪している患者が増えてきており、そのような患者には積極的に試しています。
基本的には、NaClを使いますが、CCUやICUなどであれば、カリウム補正時に使用するKClに混ぜるというのでもOKです。ただこの場合には、投与速度などには十二分の注意が必要です。
循環不全の有無や呼吸状態などによると思います。循環不全がなく、呼吸も酸素がいらないような心不全だと、ひとまずラシックスを静注しておいて、6時間後とか翌日とかに評価するということでもよいかと思います。
具体的な尿量の基準について
- 最低ラインは1日1500ml
- 目標は、1日 2500ml ± 500ml
- 状況によるが4000ml以上は出過ぎ(電解質異常が起こる可能性あり)
- 体重で、0.5-1.0kg/日程度の減少が安全
ファーストタッチの後に、具体的にどのように利尿薬を使用するかをお話ししました。
心不全の急性期の治療において、どれくらいの尿量があればよしとするかについての、私がなんとなくこれくらいかなと思っていることをお話ししたいと思います。
まず、入院した直後のファーストタッチでは、ラシックスに反応して、最低時間60ml程度は出てほしいなと思います。時間100ml以上出ていれば、反応はいいなと思います。
尿道バルーンを入れるような状態では、バルーンを入れた直後は、濃い尿が少量出てくると思います。この尿の電解質をみると低循環か、利尿薬に反応しそうかわかりますが、今回は端折ります。ラシックスを投与して、30分くらいでカテーテル内に薄い尿が見え始めたら、そのあとに尿が出てくる可能性が高いと判断できます。いわゆるラシックス尿です。
バルーンを入れていないときでは、4時間程度の尿量で、やはり時間60mlを超える尿量があるかないかが一つの基準になると思います。また、利尿薬投与前後の尿生化学をみると利尿薬の反応性から腎循環まで評価できますが、これも端折ります。
時間60mlでいうのは、一応このペースでいくと、24時間で1500ml程度になりますので、まぁ、最低限これだけ出てくれば、あとは利尿薬の再調整や点滴などを調整すれば何とかなるかなと思います。
時間40ml程度であれば、点滴や飲水などで水を摂取するため、プラスバランスになっている可能性があります。
最低限1500mlを基準に、呼吸状態やうっ血の状態にもよりますが、1日あたり2500ml±500ml程度(時間80-120ml程度)が心不全の治療の時の1日尿量として適当かなと思います。
これ以上の尿量では、多少のことで腎不全や低循環になることはないと思いますが、電解質の乱れは注意が必要です。特に、カリウムは要注意です。カリウムは少なくとも4.0、重症心不全や心室性の不整脈があるときには、4.5を最低ラインとして適時補正をするのがいいと思います。
また、サムスカ投与時には、ナトリウムも一定間隔で定期的に測定する必要はあります。どの程度の間隔かは、投与前の値と、初回投与の翌日はさすがに血液検査すると思うので、その間の尿量とナトリウムの変化を見て、決めていくことになります。慣れないうちは、毎日に近いくらい測定してもいいと思います。慣れていけば、なんとなく、尿量とか見ながら適当に間隔をあけれるようになります。
心不全の時の引水制限はどうするかというのがありますが、私は点滴していない人は、1日1200ml程度を基準としていました。これは、外来でもそのままの水分摂取の基準としては1200ml程度で、発汗などに合わせて、+していくようにしてくださいと伝えていました。
後、もちろん尿量は、飲水や点滴などのいわゆるInの総量とも強く関係します。2500ml程度というのは、Inが1000-1500ml程度を想定していて、マイナスで1000ml程度で、体重でマイナス1kg前後減っていくのが理想かなと思います。
交感神経の緊張をとることも利尿には重要
利尿薬の反応が悪い原因はいくつかあり、循環不全や純粋に利尿薬の量が足りないなどもありますが、心不全の急性期であれば、交感神経の緊張というのも意識する必要があります。
その評価として、呼吸数や脈の数を見るのですが、呼吸や頻脈に関しては、少し経験的な話になってしまいますが、その時のレントゲンや心機能から想定されるよりも、呼吸数がはやいとか脈がはやいと判断される時には、それそのものを積極的に下げる治療を行うことで、交感神経の緊張が緩和され、利尿が得られることがあります。
なんか無駄に息がはやい、脈がはやいと判断されるときです。
呼吸に関しては、陽圧換気や塩酸モルヒネ(2-4mgの静注)やフェンタニルの持続静注、保険のしばりはありますがプレセデックス持続投与などは有効です。
脈に関してはジギタリス、オノアクト®(ランジオロール)の投与が中心ですが、心房細動の時にはワソラン®も有効です。また、一過性の頻脈性不整脈であれば、除細動も積極的に考慮しましょう。
ランジオロールが発売されて、心房細動で頻脈の50例くらいの使用実績を後ろ向きに検討をしたことがあるのですが、ランジオロール使用前にジギタリス1A点滴静注していると、ランジオロールがジギタリスを使用していない群と比較して半量で目標心拍に到達しているう結果でした。
ジギタリスの慢性投与は、少量かつ洞調律に限定すれば有効ですが、心房細動などには勧められない状況です。ただ、急性期の単回投与であれば、特に予後に影響は与えないように思います(急性期のデータはないですが)。
慢性期を視野に入れた内服の選択
内服に移行する時には、原則ループ利尿薬の選択になります。利尿効果のある慢性期治療薬として、抗ミネラルコルチコイド拮抗薬とSGLT2阻害薬がありますので、このあたりを投与しつつ、ループ利尿薬を調整していくということになります。
ただ、その中でもうっ血が取れつつある段階でも、血清ナトリウムが137mEq/Lを下回っているようなときには、トルバプタンの積極的な適応になると思います。140mEq/Lを基準にしてもよいとは思います。
ループ利尿薬の中での選択は、慢性期を見越して投与するのであれば、カリウム値をみて、4.2mEq/Lを超えていれば、ダイアート、以下であればルプラックということでいいと思います。また、急性期だけの使用で、最終的には中止する予定であれば、ラシックスをその間だけ追加でもいいともいます。
慢性期のラシックスはお勧めしません。ラシックスは腸管からの吸収が不安定で、特にうっ血が起こった時の吸収が落ちるので、心不全の増悪に結構無力です。持続時間も腸管からの吸収も安定している、ダイアートとルプラックを血清カリウム濃度によって使い分けることをお勧めします。
心不全を治療していると結構低カリウムになります。この時に、カリウムの補正といって、塩化カリウム製剤20mEq、20mlを2時間程度で投与することがあると思います。この塩化カリウムにラシックス20-60mgを混ぜておくのも有用です。特に重症心不全では、不整脈予防のため、血清カリウム 4.5mEq/Lは死守すべきラインになります。カリウム補正とともにクロール+ラシックスを投与するイメージで行くのもいいと思います。
心臓外科の手術の術後合併症の半分は内科の責任
利尿に関して外科の手術との兼ね合いで1点補足しておきます。
時折重症心不全で内科的な治療だけではこらえきれなず、補助人工心臓をいれることは特定の施設ではよくあります。この際に重要なのは、強心薬でも何らかの循環補助を入れててもいいので、体の水分バランスをできればやや脱水くらいに維持することです。
以前、左心機能不全だけでなく、かなり右心機能不全があり、全身のむくみや胸水が多量にあった方がいました。
経験上、両室の補助人工心臓が必要だろうという見立てで、そうなると補助を付けた後も状況は厳しいだろうという予想がされました。
いろいろな理由が重なり、私が直接の主治医になりました。
私は、術前にできるだけうっ血、少なくとも溢水はきれいになくすのが、内科の仕事と思っています。術中の縫合や術後創部感染、肺炎の発生に違いが出るだろうと考えているからです。
そのため、これまでに述べたあらゆる手段を使って循環を維持しながら利尿を積極的に行い、5日で30,000ml程度の利尿を得ました。
もちろん、循環や電解質など身体所見や検査でわかるあらゆるデータと経験から一つ一つ手を打っていきました。
最終的に、胸水を含め、完全に溢水を解除して、手術に送り出すことができました。私がいた施設の外科の先生方は間違いないので、術中・術後大きな合併症もなく、無事に終えていただき、右心系の補助はいらず、左心補助のみとなりました。
内科から送り出した患者さんに合併症が起きた時は、どのような合併症であっても、少なくとも半分は内科の責任だと思っています(9割以上内科の責任の時もあります)。どんな手術でも、その術前に合わせて、ベストな状態で患者さんを送り出すのも、内科の重要な仕事だと思っています。
できることは限られますが、循環不全の解除と溢水の除去で、このためには機械的な補助を含めて積極的に治療を行う必要があると考えています。