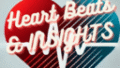- 酸素投与の必要性は、呼吸数とSpO2で判断するが、できれば入院時に動脈血ガス、最低でも静脈血ガスの測定はして、CO2の貯留がないか確認したほうが安全。
- 陽圧換気がいるかどうかは、呼吸努力(臨床的には、呼吸数としんどさを肌感覚で評価)やCO2が貯留しているかによる。判断に悩む程度であれば、Nasal High Flowがおすすめ。
- 急性心不全での陽圧換気では、劇症型心筋炎や、敗血症などのほかの要素がない限り、非侵襲的な陽圧換気で対応可能。
- 非侵襲的陽圧換気は、いかに患者さんが不快感を感じないかが重要。CPAP (continuous positive airway pressure)だけにしてPS (pressure support)は行わない、マスク形状を工夫する、鎮静・鎮痛薬を併用するなどが必要。
- 心不全の非代償期に、陽圧換気を行っても、臨床上不利益な血圧の低下は起こらない。
- 心不全の代償期に、重度なOSAS (閉塞性睡眠時無呼吸症候群)がないなら陽圧換気を行ってはならない。ただし、終末期の呼吸困難や倦怠感の治療に対してのASV (adaptive servo ventilation)は有効なことがある。
急性心不全の呼吸管理
急性心不全の呼吸管理に関しては、まずはSpO2と呼吸数をみながら酸素投与の必要性を判断することになると思います。特に救急車で搬送され、肺水腫による呼吸不全をきたしているような人には、何を差し置いても、まず陽圧換気をすることになります。
外来で歩いてきた人でも、安静にして頻呼吸があるなら、SpO2 96-98%とかでもO2 2L程度の投与は行ったほうがよいと思います。
血ガスの必要性に関しては、心不全だけではCO2が蓄積することはなく、治療が必要なレベルの貧血がなければSpO2だけを参考に酸素投与を開始してもいいと思います。ただ、どうせ血液検査をするので、動脈血で採血して、入院時に血ガスのデータを見ておくほうが安全ではあります。また、静脈ガスでも抹消でのCO2負荷があり、動脈よりも値は高いですが、それを前提にすれば動脈血ガスのCO2は、静脈血の値を参考にこの値以下ということを推定することは可能ですので、いわゆるVガスでも取らないよりはよいかと思います。
呼吸管理をするうえで非常に重要になるのが、血液中の二酸化炭素(CO2)濃度だと思います。CO2の貯留さえなければ、後はSpO2(経皮的に測定できる動脈血酸素飽和度, 皮ではなく爪ですが)と呼吸回数で、呼吸管理は行っていけます。
血液のCO2の測定は、呼気のCO2濃度を測定できるものもあり、気管挿管での人工呼吸管理では使われていると思いますが、非侵襲的な状況では、測定できるものはありますが、(2019年現在)一般的ではないため、現時点では動脈血を採取しているというのが一般的かと思います。ただ、ひとまずのCO2の確認は、静脈血でいいと思います。理屈的に、動脈血のCO2よりも静脈血のCO2のほうが高いはずですので、静脈血で高くなければ、動脈血も高くないはずです。
動脈血を採取するタイミングがあったり、それなりに重症で動脈血が必要と判断されればもちろん動脈血を確認することは重要だと思いますが、まぁ、それほどでもないというときには、心不全入院の時には通常の静脈血の血液検査は必ずすると思いますので、静脈血でガス成分の検査を行って、それで、<45torr以下であれば、正常と判断できると思います。(静脈血で<50torrであれば、まぁ大丈夫ですが)
COPDなどが併存していなければ、大抵は心不全による呼吸不全のための過換気でCO2はとんでいて低めのことが多いです。
ただ、もちろん心不全だけでも、末梢気道浮腫(左心不全による細気管支中心の浮腫)により肺胞内の換気が不十分になってCO2が貯留していることもありますので、CO2をチェックしないよりは、静脈血でもチェックしておいたほうがいいと思います。
非侵襲的な陽圧管理(noninvasive positive airway pressure ventilation, NiPPV)は心不全の非代償状態の患者においては不必要に血圧を低下させたりすることはありませんので、安全に使用できます。
陽圧換気で血圧が下がるのは、手術のように、水分バランスが正常かマイナス(術前の絶食などでマイナスバランスのことは多い)で、鎮静系の薬剤で静脈が拡張し、さらに、その状態で胸腔内圧を陽圧にすると、理論上心拍出量は低下し、血圧は低下します。 ちなみに、一番危険なのは、頚椎の手術で、あの体位は危険です。何度か手術室に血圧低下や頻脈で呼ばれましたが、ほとんどが頚椎の手術でした。
心不全の場合には、陽圧換気で血圧の低下は起きません。呼吸が楽になって適正な値に低下するということはありますが、ショックになるような下がり方はしません。 論文でもそうですし、ある程度重症といわれる心不全患者を診てきましたが、非侵襲的な陽圧換気を行うことで血圧が下がって、陽圧換気を中止したり、それに対して治療を行ったことがないという経験はありません。
特に、急性期の心不全に対するNiPPVは、悪いことは何もありませんので、迷ったら行う。行ってみて、不要そうなら早めにやめてみるということでいいと思います。
また、後述しますが、慢性期では、重症な閉塞性無呼吸症候群以外にNiPPV(CPAP)は行ってはいけません。臨床試験でもそういう結果が出ていますし、理屈的にもいいはずはありません。やってはいけません。
非侵襲的陽圧換気をするかどうかについては、ガイドラインなどにもありますが、3点に絞れるかと思います。
- CO2の貯留がない。
- 呼吸数が少なくとも20回以下で、酸素投与と安静で、15回程度で努力性の呼吸ではない。
- 陽圧換気を行わなくても十分に酸素化ができている。
ということであれば、陽圧換気を使わなくてもいいと思います。(もちろん使ってもいいです)
逆に、行ってはいけない状態は、正直あまりないと思います。
一般的には、不穏や意識障害、アシドーシスが高度な時など、いくつか条件は決められています。確かにこれらの状態では、気管挿管などをして、しっかりと治療を行うことが必要な状態が多いのは確かです。ガイドラインにはありますが、絶対に気管挿管しないといけないかというとそうでもないとは思います。ただ、漫然と非侵襲的呼吸管理は危険なので、このような状態で非侵襲的に行くなら、ICUやCCUのように必ず看護師がほぼ専属で常時状態を見れて、医師が常駐し安定するまで状態を監視できるというのは前提だと思いいます。そのような前提で、常に気管挿管が必要になるかもしれないというで、なったらすぐに挿管できる状態であれば、初めは非侵襲的な換気を試みるのでもいいと思います。
このような状態の人では、まず用手的に換気行っていることが多いと思います。そのような状態で、しっかりと酸素化を確保したうえで、鎮痛や軽い鎮静などを試みながら、呼吸の状態をしっかりと監視しつつ、非侵襲的な呼吸管理を始めてみるというのは、決して悪い選択ではないと思います。繰り返しますが、常に気管挿管ができる準備は必要ですので、酸素化が維持できないとなったらすぐに気管挿管に移ってください。
もちろん、もうショック状態で、代謝性のアシドーシスでということであれば、気管挿管の上、がっちりと呼吸と循環管理をしていくほうがいいと思います。
最重症であれば、もう何も考えずにどんどん侵襲的な検査・治療を行っていけるのである意味迷わないのですが、重症の中で、どこまで必要か迷うようなグレーゾーンのようなものは絶対にあります。個人的には、迷ったときには重症度を一段上げて対応するというのが安全だとは思います。
また、常に一度下した判断に固執せず、常にスムーズに違うレベルの治療に移行できるように、デバイス的な面でも、スタッフの意識的な面でも準備しておくことが重要かと思います。
心不全の呼吸療法:各論
酸素は多少なりとも投与するとして、次に大きく陽圧換気がないものと、あるものにわけることができます。
カヌラ、マスクによる酸素療法
酸素の投与量は、1分間に酸素の供給を何リットル行うかという単位で決められていて、X L/minという単位であらわされます。以下酸素の流量単位を単にX Lと表記します。
カヌラは低流量で2-3L程度で使われ、マスクに関しては4-5L以上の酸素流量の時に適しています。
カヌラとマスクを流量で分ける理由としては、カヌラの高流量では乾燥で鼻粘膜の出血などがあったり、逆に低流量で酸素マスクにすると、呼吸数や換気量に依存してマスク内の酸素濃度が一定にならなかったり、マスク内の空気が滞留してCO2が高濃度になったりするリスクの懸念があるためです。
さて、若年者の酸素投与は、3 or 4Lでカヌラとマスクを切り替えれば、特に問題はないと思いますが、高齢者の場合にはいろいろと問題が起こると思います。
例えば、ほぼ寝たきりの人で、口呼吸が中心で、鼻カヌラでは全然意味がない人には、鼻カヌラを皮膚にやさしいテープで固定して、口にあてて投与したり、マスクがどうしても嫌で鼻カヌラじゃないと絶対に嫌とかいう人もいたりします。このあたり、酸素を投与することを優先して、工夫していくしかないと思います。
また、一応カヌラ何Lで、FiO2 何%相当とかありますが、特に覚える必要はないと思います。結局は、SpO2が目標に達するまで酸素流量を上げるしかないので、マスク10 or 15Lを上限として、どんどんとあげることになります。
はっきりとした基準はありませんが、酸素マスク 8Lあたりでも、目標とする酸素化を得られないときには、2つの方法が考えられます。
(もちろん、無気肺などの一過性の低酸素血症の原因を除外したうえでですが)
ひとつは、もっと高濃度の酸素を投与する。もうひとつは、陽圧換気を行う。という選択肢があります。
リザーバーマスクとベンチュリーマスク
高濃度の酸素を投与するのに、ひとつはリザーバー付き酸素マスクというのがあり、これを使えばほぼマスク内の酸素が100%に近い(90%程度)高濃度酸素とすることができます。
酸素投与の弱点は流量が少ないと、酸素を送っても、患者さんが吸うときに、呼吸の状態によっては、酸素濃度が不安定になることです。
例えば、2L程度の酸素投与では、ゆっくりと呼吸してい時(1分間に12回、1回400mlの換気)では、空気を1分間に4.8L吸っていることになるので、2Lの酸素でもそれなりに有効です。
しかし、早い呼吸(1分間に20回、1回400ml)であれば、8Lを吸っていることになり、酸素投与の効果は落ちます。
そのため、この酸素と空気を事前にブレンドして、十分な流量で送ると安定した酸素濃度の空気(正確には空気ではありませんが)を送れるので、事前に酸素と空気をブレンドして、酸素濃度をある一定の値として送るような投与方法が、ベンチュリ―マスクといわれるものです。
安定した酸素濃度の空気を送れるという以外に、特に酸素マスクなどよりも有利な点はありません。
ただし、以前はこのようなものをよく使用していましたが、現在では、こういった酸素濃度にこだわるよりも少しでも陽圧をかけたほうがいいだろうという考えになってきていると思います。
その産物が、ベンチュリ―マスクの進化系であるnasal high flowだと、勝手に思っています。
非侵襲的陽圧換気療法
陽圧換気には、段階的にnasal high flow(NHF)、noninvasive positive airway pressue(nPAP) or nonivaseve positive airway pressure ventilation(NiPPV)、 invasive positive airway pressure(iPAP)があります。
Nasal High Flow (NHF)
nasal high flowは、特殊な回路を用いて、鼻からかなりの高流量(30-60L/min)のガス(酸素+空気)を投与します。しっかりとした加湿器もありますので、乾燥による鼻粘膜の障害などもありません。また、ベンチュリ型のブレンダーを使用するので、100%の酸素投与も可能です。高流量のガスを流すので、肺胞レベルで少し陽圧がかかります。だいたい、2-3mmHgだとされており、臨床的な感覚でもそのくらいだろうと思われます。
この治療のいいところは、準備が簡単です。やろうと思えば、すぐにできます。また、少しの陽圧がかかりつつ、高濃度の酸素投与も可能です。
ただ、鼻からかなりの高流量のガスを流すので、多くはないですが、強い不快感を訴えて、継続できない人はいます。もしかしたら、鼻中隔などに何らかの異常があるのかも制れませんが、わかりません。
また、結構音がうるさいです。そのために、大部屋などでは使用できないと思います。結構うるさいので、それだけで他の人が不穏になってしまうかもしれません。あと、コスト的には、保険が人工呼吸管理加算がつかないと、結構な出費になります(この保険適応は流動的なので確認してください)。
個人的には、心不全の急性期の陽圧は、肺水腫を起こしていなければ、2-4mmhg程度で十分と思っているので、この程度の陽圧がちょうどいいと思っています。
NiPPV (非侵襲的陽圧換気療法)
さて、続いては、非侵襲的陽圧換気療法(NiPPV)です。バイパップといわれることもありますが、それはたぶん一番初めに簡単に使用できるようになったのが、BiPAP(biphasic positive airway pressure)だからだと思います。biは、biphaseとbilevelの二つのどちらも指すことがあります。
この治療は、心不全の急性期と終末期に特に有効な治療となります。
簡易的なポータブルの機械(本来は在宅用の呼吸器)か、または本格的な機械(V○○など)により、気管挿管などの管を使わずに、何らかのマスク(鼻だけ、鼻口、顔全部、時には鼻に突っ込むタイプなど)などを用いて、マスク内を陽圧にして換気を行う治療です。
最近は、急性期でない病院でも在宅用ではないきちんとして非侵襲的な呼吸器があったり、または、侵襲的・非侵襲的両方に対応可能な呼吸器があり、在宅用を無理して急性期に使用しなければならないことは少なくなったと感じています。
在宅用NiPPVの急性期への流用
在宅用の機械は、簡単に使用できるのと、バッテリーが内蔵されているものに関しては、移動時などにもそのまま着用しての移動が可能です。
モードに関しても、一部の機械ではオーシャンウェーブといって、もともとの呼吸の波形に合わせた優しい陽圧設定が可能であったりします(このモードにこれ以上の意味はありません)。また、既存のCPAP(continous positive airway pressure,持続陽圧換気)や、それにpressure supportを行うなど基本的な陽圧治療に関する機能は十分に備わっています。
ただ、投与するガスの酸素濃度に大きな問題があります。在宅用の機械はあくまで陽圧にすることだけが目的ですので、酸素の投与に関しては、一応の機構しかついていません。それが機械自体かチューブのどこかに酸素のカヌラをつないで流すというものです。これは、かなり不安定な投与方法になります。
送られる酸素の量が多ければ、薄くなります。特にリークが多かったり、呼吸回数が多いと、1分間に送られる空気の量が増えますので、酸素濃度は低下していきます。
目安としては、O2 15Lで流し続けて、かなり安定しているときでFiO2 40%。急性期の不安定な時では、FiO2 30-35%程度と考えていただいていいと思います。
以前にきちんとした非侵襲的な陽圧換気の呼吸器が1台しかなく、陽圧換気自体を離脱するか在宅用に切り替えるしかなかったのですが、切り替えの時には、呼吸器の設定がFiO2 35%以下でないとSpO2が維持できなかったという経験があります。
専用の呼吸器による非侵襲的陽圧換気療法
次に、ちゃんとした呼吸器による非侵襲的陽圧換気療法についてですが、酸素の配管と直接つなぐので、FiO2 100%まで設定が可能です。
また、CPAP(continous positive airway pressure)、pressure support圧(PS)、呼吸回数といった基本的な設定はもちろん、PSをどれくらいの時間で上げるかの設定も可能です。
これらの設定のコツは、心不全の時には、患者さんの使い心地の良さを追求します。多くの場合には、CPAPのみで、それも低めの圧(4-6cmH2O)でいけることがほとんどだと思います。これに、呼吸の補助として、軽いPSを上乗せすることもあります。だいたい2-3cmH2O程度でいいと思います。また、このPSもゆっくりと圧が上がるような設定にしたります。また、機種によってはFLEXmodeといって、吸気から呼気に代わるときに分圧がふっと抜けて、呼気がしやすくなるような設定もあります。
NiPPVは、患者さんが不快感を示すとできなくなり、どうしても陽圧が必要だと、そのまま寝かせるか、気管挿管しかなくなるため、いかに心地よい状態にするのかが重要です。
ただ、どうしても設定として、高いCPAPとPSが必要なことはあります。それでも、元の状態より呼吸の補助が効くので、楽に呼吸ができると継続できる方もいますが、そうでない方もいます。
不快感が強い場合にどうするかですが、まずは、マスクの形態を見直してみましょう。人によっては、顔全体がいいとか、鼻だけがいいとか、鼻だけでもピロータイプといって、鼻に突っ込むタイプがいい方もいます。特にシリコン製のピロータイプは、リークも少なく、そのまま話や食事もできます。そのため、急性期だけでなく緩和医療などでは有用なことがあります。
次に、鎮痛や軽い鎮静も考慮します。特にモルヒネやフェンタニルなどによる鎮痛はマスクの不快感をやわらげるますし、麻酔薬のプレセデックスは呼吸抑制が少なく、循環にもいい作用がありますので、心不全には適した薬剤といえます。
用量は、かなり少なくても大丈夫です。プレセデックスに関しては、1日に0.5-1バイアル(100-200ug)を24時間持続注射で十分なことが多いです。
侵襲的な気管挿管による呼吸管理
最期は、気管挿管による呼吸管理です。心不全の急性増悪では、気管挿管まで行くことはあまりないと思います。
心筋炎や多枝病変による虚血、また、肺炎や他の重症の感染症を併発している場合には、気管挿管による人工呼吸管理を行いながらしっかりと治療をすることが必要になります。ちなみに、感染が安定しても気管挿管から離脱できそうにない時には、早めに気管切開を行ってください。1週間から10日程度が見極めの期間になると思います。これが遅れて、ずっと鎮静で治療を行うと、肺炎などの呼吸器関連の感染症がづっとついて回ります。
気管挿管の場合には、鎮痛をしっかりと行ってください。フェンタニルやアセトアミノフェンなどでしっかりと鎮痛を行うと、鎮静が不要で、覚醒状態で管理することもできます。気管挿管していても、意思疎通も可能で、呼吸もしっかりしてくれるので、肺炎などの合併症も減ります。
ちなみに、VA-ECMOやIABPなど機械的なサポート時にも十分な鎮痛を行うことで覚醒状態での管理が可能です。
自験例ですが、若年でありながら、先天性疾患のため、肝硬変をきたしてしまっており、心臓移植の適応がなかった患者が、最終末期にVA-ECMOをしながら多少の食事摂取などをしながら最期を過ごしたということもありました。
陽圧換気の循環動態に与える影響
心不全の非代償期には陽圧がかかっても血圧は低下しませんが、心不全が代償状態にあるときとか、感染性のショックの時などは血圧が低下します。
陽圧換気による肺にかかる陽圧は、心臓を外から抑え込みます。10cmH2O程度の持続的な陽圧は血行動態に対して4mmHg程度の障害となります。データ的に、右房圧や左房圧が4mmHg程度上昇するのですが、静脈の還流からするとこれは抵抗・障害となるため、心拍出量の低下を伴い血圧低下の原因となりますので、
全身麻酔時など静脈の中の血管内の血液量などによっては、鎮静が効いていると血圧を低下させますので、注意が必要です。
陽圧換気が循環動態にどのような影響を与えるかについてお話ししていきたいと思います。
まず、要約すると、非侵襲的陽圧換気で、持続的な陽圧(CPAP)を10cmH2Oかけると、肺の圧が上昇し、肺が心臓の拡張を阻害します。
それによって、最終的には、右房圧と肺動脈楔入圧が4mmHg程度上昇します。また、肺血管抵抗と体血管抵抗は減少します。
抵抗の減少には、交感神経が抑制されることによると考えられます。
酸素消費にかかわるところでは、呼吸運動が補助されて、呼吸運動による酸素消費が減少します。
心臓の酸素消費も減少するという報告も一部あります。
心拍出量に関しては、酸素消費が減少するため、正常、または心不全でも心拍出量は安静時で保たれている人に関しては、減少します。
(心拍出量は、全身の酸素消費量に合わせて変化するため)
また、心機能が悪く、安静時でも酸素消費を満たせていない人に関しては、心拍出量が上がることが示唆されています。血管抵抗が低下する事が原因かもしれませんが、機序は不明です。
このように、いろいろな報告を合わせると、非代償状態の心不全患者に陽圧換気を行うことは、血行動態的に悪いことはしないと結論付けられます。
そのために、心不全の急性増悪の時期に、一時的に陽圧換気を行って、呼吸を補助し、胸腔内の循環を立て直し、その間に治療を進めるということは正しいと思います。
ただし、慢性期の安定している代償状態の心不全の方には、陽圧換気は好ましくないと考えられます。
理由は簡単です。陽圧換気をすると、その間に体循環のうっ血が増悪するためです。
先ほど示したように、右房圧が2-4mmHg程度上がります。これは、何の理由で上がろうとも、胸腔外の臓器からしてみると抵抗の上昇でしかありません。
そのため、臓器の静脈圧がそれに応じて上昇します。血管抵抗もあるため、距離の遠いところほどより上昇します。すると、諸臓器がうっ血状態となります。
そして、一定時間が過ぎて、陽圧換気が終わると、いきなり右房圧が低下するため、一気に体循環からうっ血していた静脈血が戻ってきます。
圧の解除は、終わった時だけではなく、リークといって、マスクフィットの関係などで夜につけている間にも何度か起こっています。
このような循環の揺さぶりが何度もおこっています。
これが、陽圧換気が循環動態を不安定化させる私の仮説です。
論文としても、陽圧換気が安定した慢性心不全患者の予後を悪化させることがCowieらの臨床試験(SERVE-HF)により示されてしまい、この論文以降安定した心不全患者にASVを使用してはいけないこととなりました。
(Cowie MR, Woehrle H, Wegscheider K, Angermann C, d’Ortho MP, Erdmann E, Levy P, Simonds AK, Somers VK, Zannad F, Teschler H. Adaptive servo-ventilation for central sleep apnea in systolic heart failure. N Engl J Med. 2015;373(12):1095-1105. doi:10.1056/NEJMoa1506459)
私が考える陽圧換気をしてもいい心不全は2つです。
先ほどから繰り返しているように、心不全の非代償期。つまり、一番の症状である呼吸困難を軽減させるために使用し、その間に、体循環のうっ血を治療により改善させる。その後に、陽圧換気を解除させても、うっ血が軽減しているので、症状の増悪はないという状態。
それと、終末期です。終末期は、呼吸筋疲労などで息をするだけでも、普通の人より多くの酸素を消費しますので、このような方には症状を軽減させる目的で、使用するのに適しています。というか、呼吸苦をとるには、陽圧換気か、麻薬またはプレセデックスの組み合わせによる治療くらいしかできない状態となります。