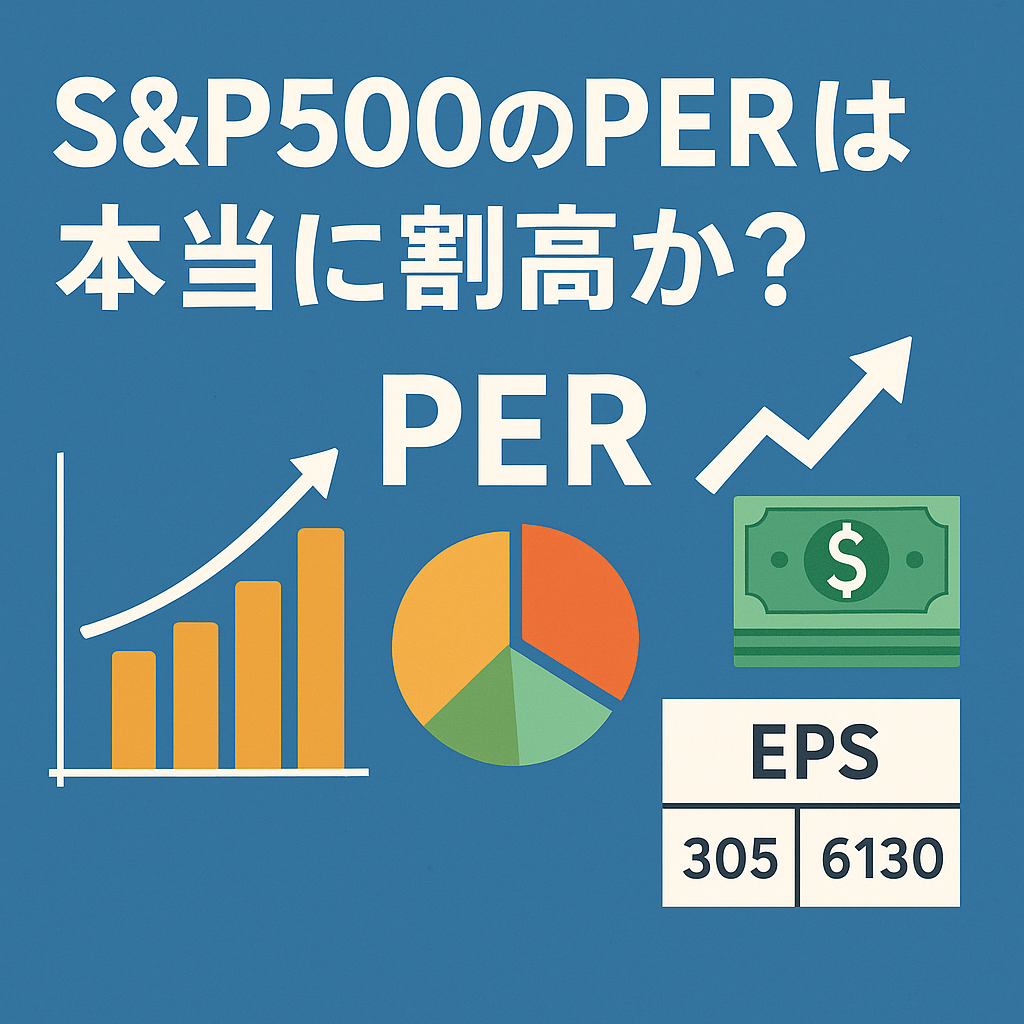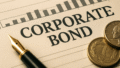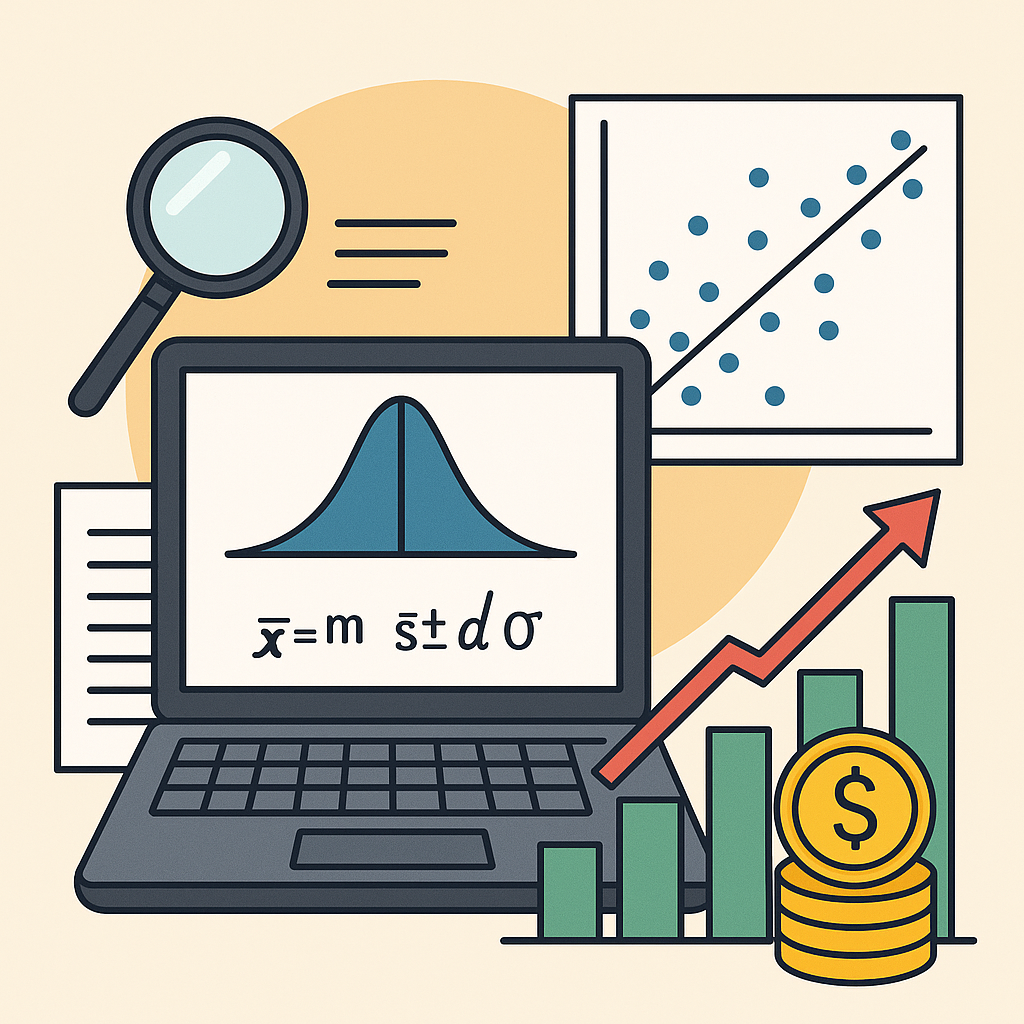初めに
現在のS&P500のPERは約30倍と、過去と比べて非常に高い水準にあります。一見すると割高に見えるこの数値ですが、実はS&P500を構成するセクターの比率に注目すると、違った見え方ができます。
特に、構成比率が高い情報技術(IT)セクターは、そもそもPERが高くなりがちなセクターであり、利益成長が期待されている企業が多く含まれます。S&P500全体としてのPERが上昇しているのは、こうした高PERセクターの比率が増加しているためとも考えられます。
本記事では、異なる期間の各セクターの平均PERを用いて、現在の構成比率での「妥当なPER水準」を再計算し、現在のPERが本当に割高なのかを再検証します。
現在PERが歴史的に高値である
PERとは、現在の株価がその株の1株あたり利益(EPS)の何倍であるかという指標で、「何倍」の部分がPERになる。
なぜPERが重要かというと、株価は将来の1株利益に対して値がつけられているという考えがあるためである。
EPS(1株あたりの利益)とPER(株価収益率) – アラフィフ、老後を見据えて暮らしとお金を模索中
以下は、S&P500の過去の期間別における実績PER(Trailing P/E)の平均値を示した表である:
| 期間 | 平均PER(実績ベース) |
|---|---|
| 過去100年 | 約 16倍 |
| 過去50年 | 約 15〜17倍 |
| 過去30年 | 約 17〜19倍 |
| 過去20年 | 約 19.4倍 |
| 過去10年 | 約 23倍 |
| 過去5年 | 約 25〜28倍 |
| 過去1年 | 約 29.7倍 |
このように現在のS&P500のPERは歴史的に高い状態である。
株式相場には、平均から逸脱した値は平均に戻っていくという考え方があり、高値のPERは近いうちに平均値に近いところに戻る、つまり、1株利益は急には変化しないので、株価が低下する、と考えている人は多い。
私もこの点には留意が必要で、いつ調整から暴落する局面がきてもおかしくはないと認識はしている。
ただ、少し違う観点で評価した時に、意外にこのPERはバブルというほどではなく、1標準偏差の高い位置にあるくらいではないかとも思っている。
テック企業の台頭とPERの押し上げ効果
何にでも言えることであるが、どの範囲に焦点を当てるのかというのは重要で、単にS&P500という集団のPERの経過をみるという意味では、PERは平均より高いのだろうと思う。
ただ、焦点を当てる範囲をセクターというものにまで狭めてみると、現在のPERに少し違った評価を行うこともできる。
現在は、GAFAM+NVIDIAのような超大型テック企業が指数に大きな影響を与えており、これらは業態として通常PERが高い(=利益成長が高いため)。
一方、過去(例:1980年代や1990年代前半)のS&P500は、製造業、エネルギー、金融などの低PERセクターが多く、PER全体が低く見える傾向があった。
このようにセクターには、そのセクターの特徴としてPERが高いものと低いものがある。
今後、金融や製造業の総時価総額とテック企業の時価総額のバランス自体に変化がないと仮定すれば、PERが高値であっても不思議ではないということである。
セクターごとの構成とPER
以下は、各セクターの構成比に加え、過去5年・10年・20年の平均PERを示した一覧表である。
| セクター | 構成比(%) | 5年平均PER(推定) | 10年平均PER(推定) | 20年平均PER |
|---|---|---|---|---|
| 情報技術(IT) | 31.6 | 30.0 | 23.5 | 18.6 |
| 金融(Financials) | 14.3 | 16.0 | 14.5 | 15.0 |
| 一般消費財(Consumer Discretionary) | 10.6 | 25.0 | 22.0 | 19.43 |
| 通信サービス(Communication Services) | 9.6 | 20.0 | 18.0 | 15.76 |
| ヘルスケア(Health Care) | 9.6 | 21.0 | 19.0 | 17.56 |
| 資本財(Industrials) | 8.7 | 20.0 | 18.5 | 16.54 |
| 生活必需品(Consumer Staples) | 5.9 | 22.0 | 20.0 | 18.07 |
| エネルギー(Energy) | 3.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
| 公益事業(Utilities) | 2.5 | 18.0 | 17.0 | 16.35 |
| 不動産(Real Estate) | 2.1 | 36.0 | 34.0 | 38.12 |
| 素材(Materials) | 1.9 | 18.0 | 17.0 | 15.77 |
現在のセクター構成比を固定して、過去20年、10年、5年と同様の構成比だった場合に、それぞれのセクターの各機関の平均PERを用いて、全体のPERを求めれば、今と以前の構成比の違いによる株価の差を埋め合わせられるのではないかと考えた。
下の表は、過去のセクター毎の平均PERを用いて、過去のセクター比率で今と同じだったらという仮定の下計算した値である。
セクター比率を今の値で固定し、各期間のセクター毎の平均PERを使用し全体のPERを算出した、S&P500全体の加重平均による理論的PERは以下の通りである:
| 基準期間 | 加重平均PER(理論値) |
|---|---|
| 過去20年 | 約 17.72 倍 |
| 過去10年 | 約 20.07 倍 |
| 過去5年 | 約 23.41 倍 |
2026年のEPSは305ドル程度と予想されている。(S&P500 EPS Forecasts For 2025-2027 As Of September 12, 2025)
2026年の予想EPS(305ドル)を用いて、各期間(20年・10年・5年)の加重平均PERから算出したS&P500の妥当株価は以下の通り:
| 基準PER期間 | 妥当株価(ポイント) |
|---|---|
| 過去20年PER(17.7倍) | 約 5400 |
| 過去10年PER(20.1倍) | 約 6130 |
| 過去5年PER(23.4倍) | 約 7137 |
記事を作成した2025年10月1日現在のSP500は、6700であり、来年のEPSに対するPERは、22.0となる。
ITバブルの再来か?それとも新たな常態か
投資の世界では5年という時間は長くはないとはいえ、セクター構成比が今後変化するとしても、世の中が進歩するとした場合には、PERが高い企業の多いセクターの時価総額が増えることが想定されるため、PER23というのは、決してバブルというほどはないともいえる。
ただ、過去の2000年代のITバブル後のように、現在のNVIDIAなどの企業株価が暴落すると、もちろん、セクター構成比率は変化し、IT関連の高PER分野の比率が低下することで、推定PERも低下し、予想株価も低下するという展開は十分に予想される。
ITバルブ崩壊のように歴史が繰り返されるなら、今のM7が同じように株価が低迷ないし暴落にすのなら、同様のことが繰り返されるであろうと考えられる。
ただ、ITバブル自体のIT企業の実情と、現在のIT企業の実情にかなりの違いがあることに留意する必要もある。
今と2000年代の「構造の違い」も重要
| 項目 | 2000年代(ITバブル崩壊後) | 現在のM7(2020年代) |
|---|---|---|
| 主役企業 | ドットコム企業、通信株 | Apple、NVIDIA、MSFTなど高収益 |
| キャッシュフロー | 弱い、赤字多い | 自社株買い・配当も可能な潤沢なCF |
| 業績成長の実態 | 楽観が先行、実態伴わず | 実態成長+ネットワーク効果+モノポリー的優位性 |
| 利益率 | 低い | 非常に高い(MSFT、AAPLなど40%以上) |
| 財務体質 | 脆弱 | 多くが無借金 or ネットキャッシュ企業 |
このように現在のM7は、ITバブル期の“夢の株”ではなく、“成熟した収益エンジン”としての顔を持ち、安定していると言える。
歴史は繰り返さないが韻を踏む
相場において、「歴史は繰り返さないが韻を踏む。」といわれる。
チューリップバブルも、ITバブルも、リーマンショックも、今後起きることはない。これらは時代背景がバブルをつくったこともあるが、教訓として対策もされているので、同じことは起きない。
ただ、やはり、相場である以上、ある何かに対して、その価値以上に相当高い値段が付けられていて、専門家を含む多くの人がそうとは気づかずにその価格を妥当だと判断し、下落したときにはじめて、その価格自体が幻想であったと気付くことは起こるだろう。
今、AIバブルだと言われているが、そうかもしれないし、実は別の何かがバブル状態であったことが、後に激痛を伴って知ることになるのかもしれない。
それはやはり現時点ではわからない。