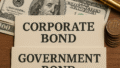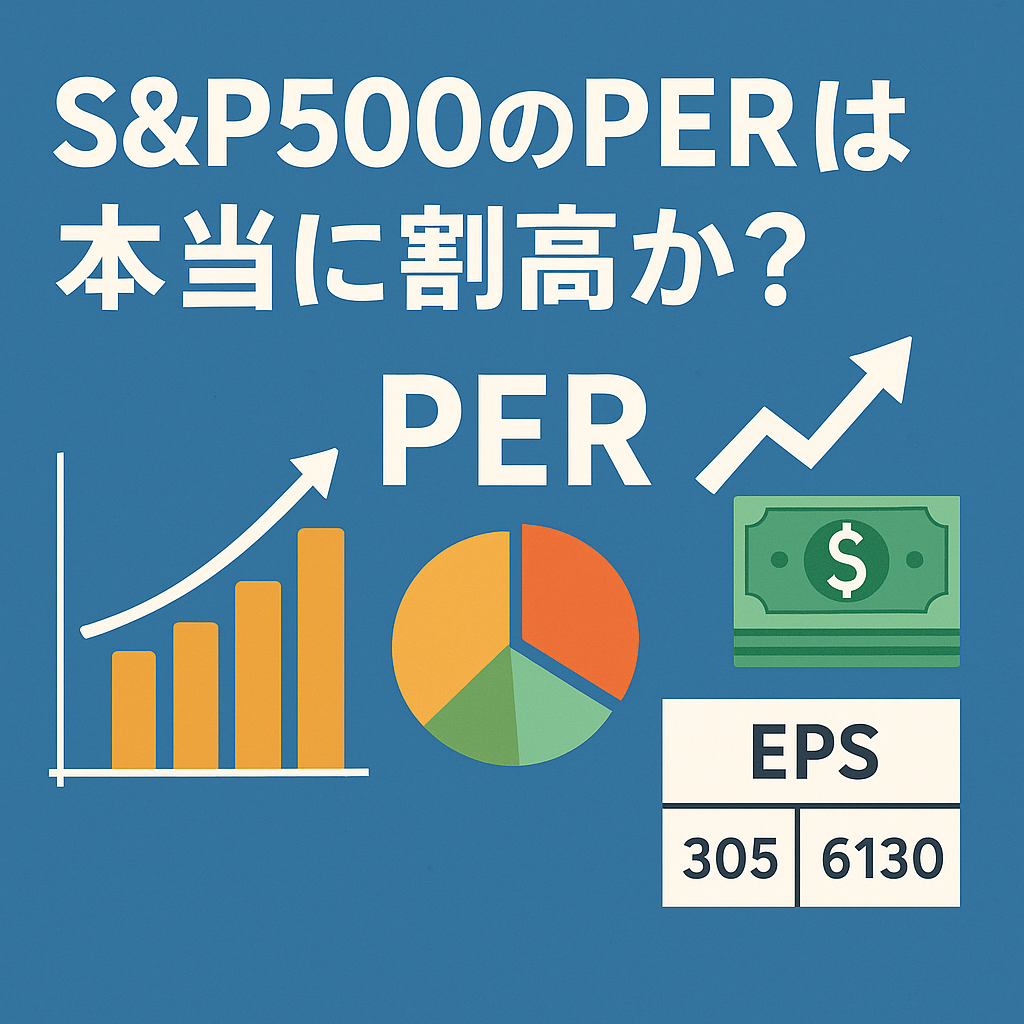はじめに
資産運用といえば株式や投資信託に注目が集まりがちですが、私は日本企業の社債にも一定割合を振り分けています。社債は「企業にお金を貸す」投資手段であり、利息(クーポン)を定期的に受け取れることが特徴です。株式のように値上がり益は見込めませんが、デフォルトさえしなければ日々の値動きはありませんので、ポートフォリオが安定します。アセット全体のリスクとリターンのバランスを取るうえで有効な選択肢になります。
今回は社債のリスク・利回り・位置づけについて整理し、私自身が保有している ソフトバンクグループの無担保社債 をとりあげたいと思います。また、比較対象としてメガバンクが発行する普通社債や劣後債の条件にも触れ、投資判断の参考になる情報をまとめてみました。
社債・日本国債の投資戦略|リスクとリターンの整理と私の考え方
社債の基本と種類
社債には大きく分けて以下の種類があります。
1. 普通社債(シニア債)
定義と位置づけ
企業の一般債務に該当する最も標準的な社債です。多くは無担保ですが、担保付の場合もあります。破綻時の弁済順位は比較的高位(劣後債やハイブリッドより優先)で、リスクが低い分、提示利回りは抑制的になりやすい商品性です。
代表的な条項
- 期間:2〜10年程度が中心(超長期もあり得ます)
- 繰上償還(コール):発行体に早期償還の権利が付く場合あり
- 保護条項:財務制限条項やクロスデフォルト条項が付与されることも
主要リスク
- 信用リスク:発行体の財務悪化・デフォルト
- 金利リスク:金利上昇局面で価格下落(満期保有で名目元本は返済予定)
- 流動性リスク:個人向け公募でも流通市場の板は薄いことがある
活用の場面
- 安定的な利息収入を重視し、元本回収可能性を相対的に高めたい投資家
- ポートフォリオの債券コア資産(「株式のボラティリティを抑える役割」)
商品例
- 日本政策投資銀行(DBJ) 第201回 無担保社債 DBJ
発行日:2025年7月18日
償還期限:2030年7月18日(5年債)
利率:1.155%
発行額:400億円
無担保・保証なし - 日本空港ビルデング株式会社 第5回 無担保普通社債 東京空港ビルディング
払込期日:2025年8月28日
償還期限:2030年8月28日(5年債)
利率:年 1.486%
発行額:50億円
格付:R&I で A+
2. 劣後債(期限付劣後債=Tier2が代表)
定義と位置づけ
普通社債より弁済順位が下位に置かれる社債です。とくに金融機関の自己資本規制(バーゼル規制)と親和性が高く、規制上の「補完的な自己資本(Tier2)」として期限付劣後債が広く発行されます。
※「劣後債」という用語は広義に使われますが、期限付(Tier2)と無期限(AT1=後述のハイブリッド)は性質が異なります。
代表的な条項(期限付劣後債)
- 期間:10年程度が多い(5〜15年など変動あり)
- コール:5年・10年等に繰上償還条項(発行体の任意)
- 利払:停止条項は一般に付かない(不払いは原則デフォルト)
- 劣後特約:破綻時に普通社債より後回しで弁済
主要リスク
- 弁済順位が低いことに伴う回収劣後
- コール見送りリスク(ステップアップ条項の有無や経済合理性により非行使の可能性)
- シニア債よりスプレッド拡大の影響を受けやすい
活用の場面
- シニア債よりやや高い利回りを狙いつつ、AT1ほどの条項リスクは取りたくない場合
- 同一発行体の資本構造の中層を取りにいく戦略
3. ハイブリッド債・転換社債・仕組債
ほかに、ハイブリッド債や転換社債・仕組債などがありますが、老後資金目的にするには複雑化と思いますので、雑記りとした説明にして、最後に補足として、追加説明を載せたいと思います。
- ハイブリッド証券(AT1・永久劣後債など) 債券と株の中間みたいな商品であり、利回りは高めに設定もリスクもその分高くなる。 利息が急に止まることもあるし、最悪の場合は元本が減る・株に変わることもある。 銀行や保険会社がよく発行する。
- 転換社債(CB) 普通の社債に「株に変えられる権利」がついたもの。 株価が上がれば株にして利益を得られるし、下がっても社債部分がクッションになる。 成長株に守りを入れながら投資したい人向け。
- 仕組債(Structured Notes) 株や為替、金利に連動する特別な社債。さまざまな条件が設定されている。 表面利率が高く見えるけど、条件を満たさないと元本割れすることも多い。 中途売却が難しい/不利になりやすい。 「高利回り」の裏に大きなリスクが隠れているので、仕組みを理解できない人には不向き。
横断比較(要点)
- 弁済順位の高低:シニア債 > 期限付劣後(Tier2) > ハイブリッド(AT1等)
- 条項リスクの強弱:シニア(弱) → 期限付劣後(中) → ハイブリッド(強:利払停止・PONV等)
- 複雑性:シニア(低)/期限付劣後(低〜中)/ハイブリッド(中)/CB(中)/仕組債(高)
- 価格ボラティリティ:ハイブリッド・仕組債・CBは市場ストレスに敏感(条項・オプション性のため)
最低限のデューディリジェンス・チェックリスト
- 発行体の信用力:格付・自己資本・利益安定性・負債構成
- 弁済順位:目論見書で自分がどの階層かを明確に把握
- 条項の肝:利払停止の有無・累積性/PONV/減損・株式化条件/コール条件・ステップアップ
- 満期・コール前提:「コールされない」シナリオでも保有可能か
- 流動性:中途売却の想定スプレッド・約定可能性
- 金利・スプレッド感応度:デュレーション/クレジットスプレッドの影響度
- 仕組みの可視化(仕組債・CB):損益の数式・パス図を自分で描けるか
小まとめ
- 普通社債(シニア債):債券の基礎。弁済順位が高く、条項もシンプル。
- 劣後債(期限付・Tier2):やや高利回りだが回収順位は下位。コールや期間の設計を吟味。
- ハイブリッド(AT1等):利払停止・PONV等の資本性リスクを理解できる投資家向け。
- 転換社債(CB):株式の上方参加と債券の防御の折衷。オプション性の把握が鍵。
- 仕組債:条件依存の損益構造。表面利率ではなく条件式で評価する姿勢が不可欠。
私の投資例:ソフトバンクグループ社債
私は現在資産の約5%をソフトバンクグループのシニア債に投資しています。
魅力
- 利率が 3%以上 と高水準。
- 満期7年の中期債であるが、ソフトバンクグループの企業の経営状態を考えると、私の判断では、10年以内であれば、デフォルトする可能性は低い。
- 国債やメガバンク債に比べ、収益寄与度が高い。
リスク
- 信用リスク:ソフトバンクグループは実質は投資事業であり、損益変動が大きく、格付けも「A」〜「B」水準とばらつきがある。また、孫正義氏の個人的カリスマ性が高いと考えており、孫氏になにか健康上のトラブルがあれば、それもリスクになると思われる。
(私としては、株式は相当下がると思うが、債権の償還はできるのではないかと判断している) - 流動性リスク:途中売却は難しい。
- 金利リスク:将来の金利上昇局面では価格が下がる。
しかし、資産全体の5%未満にとどめているため、最悪の場合でも資産全体への影響は限定的です。
一定の社債を入れると、その部分の値動きはなくなるので、アセット全体の値動きのバッファーになってくれます。
これは「リスクプレミアムを狙うスパイス」として合理的だと考えています。
メガバンク債との比較
メガバンク(MUFG・みずほ・SMFGなど)の社債はどうでしょうか。直近の発行条件を見ると、以下のような傾向があります。
普通社債(シニア債)
- 利率:1.1〜1.6%程度(3〜7年)
- 格付:AAクラス
- 信用力が極めて高く、破綻リスクは低い。
- 国債よりは利回りが高いが、インフレを考えると実質利回りは限定的。
劣後債
- 利率:2〜3%台(10年〜30年、5年コール条項付)
- 格付はA〜AA。
- 一定の信用リスクはあるが、ソフトバンクGよりは安定。
ハイブリッド債
- 利率:3〜4%台
- 35年満期、5年ごとのコール条項、利払繰延あり。
- リスクは高いが、発行体がメガバンクなら一定の安心感。
リスクとリターンの比較表
| 発行体 | 種類 | 利率(例) | 信用力 | 投資家視点での評価 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンクG | 無担保社債(第63回) | 3.03%(7年) | A(JCR)/B1(Moody’s) | 高利回りだが信用リスクも大きい。 |
| MUFG | 無担保普通社債 | 1.1〜1.6%(5〜7年) | AA- | 安全性重視。利回りは控えめ。 |
| みずほFG | 劣後債 | 1.4%(10年)〜2%超 | A+ | 信用力は比較的安定、長期投資で。 |
| SMFG(外貨建て劣後債) | 劣後債(USD建) | 5.8%(超長期) | A〜AA | 為替リスク込みで高利回り。 |
| 国債(3年) | 国債 | 0.93% | ムーディーズA1 | |
| S&P:A+ | ||||
| フィッチ:A | 理論上日本では最も信用が高い。 |
私のスタンス
私は以下のように考えています。
- メガバンク普通社債は「安全資産」枠 → 資産の大部分を置くには安心感があるが、利回りは物足りない。流動性の面で安全資産として考えるなら短期国債のほうがよいと思っている。【日本国債の基本と個人向け国債の特徴】定期預金との違いやメリット・デメリットを解説
- メガバンク劣後債は「ややリスク資産」枠 → 信用力が高い発行体なので、分散投資の一部に加える価値はある。
- ソフトバンクG債券は「高利回り狙いのスパイス」枠 → 資産の数%なら許容できる。だが全体の10%を超えるのは危険。
まとめ
社債投資は株式投資と異なり「大きく儲ける」ためのものではありません。むしろ、
- 安定的な利息収入を得る
- 資産全体のリスクを調整する
- 特定の企業に対する信用リスクを引き受け、その見返りとしてプレミアムを得る
といった性格を持ちます。
私自身は、資産の約5%をソフトバンクGシニア債に投資し、残りはETFや高配当株などに分散させています。今後も「高リスク高リターンのスパイス」と「低リスク低リターンの安全資産」を組み合わせることで、安定と成長のバランスを取っていきたいと考えています。
補足説明:ハイブリッド債・転換社債・仕組債
ハイブリッド証券(AT1・永久劣後債など)
定義と位置づけ
債券と株式の中間的性格を持つ「資本性調達」の代表。無期限(実質永久)が基本で、規制上はAdditional Tier1(AT1)等に該当します。弁済順位は社債のなかで最下位に近い階層です。
特徴的な条項
- 利払い繰延の任意性:発行体の裁量で利払停止が可能(多くは非累積=停止された利息は後で支払われない)
- PONV条項:当局判断等で「元本の一部/全部の減損(Write-down)」や「普通株式への転換」が発動し得る
- 繰上償還(コール):一定時点で発行体が早期償還可能。ただしコール非行使もあり、価格変動が大きくなる
- ステップアップ:初回コール不行使で利率が上がる設計がある一方、近年は規制適格性の観点で多様
主要リスク
- 利払停止・非累積の条項リスク
- 規制・当局判断に伴う元本欠損/株式化リスク(PONV)
- コール非行使によるデュレーション長期化と価格下落
- 市場ストレス時は価格ボラティリティが大きい
活用の場面
- 高利回りを狙う代わりに、条項由来の資本性リスクを許容できる投資家
- 銀行・保険・通信などの強固な発行体を選別し、条項を精読できる体制がある場合
転換社債(CB)・仕組債(Structured Notes)
1. 転換社債(Convertible Bond, CB)
定義と位置づけ
債券+株式転換オプションの複合体。投資家は一定条件で発行体株式に転換できます。価格は「債券価値+オプション価値」で構成されます。
代表的な条項
- 転換価額・転換比率:株式への交換レート
- 希薄化調整:分割・無償割当等があった場合の調整条項
- 早期償還・強制転換:株価が一定水準を超えた際の発行体コールや投資家プット等
- 弁済順位:原則は普通社債と同順位の無担保(目論見書で要確認)
主要リスク/リターン特性
- 株価上昇時:転換で上方参加(株式の一部アップサイドを取りにいく)
- 株価下落時:下方は債券価値がクッションになる一方、信用・金利には晒される
- ボラティリティ感応度:株オプション部分によりガンマ・ベガの影響を受けやすい
活用の場面
- 成長企業のアップサイドを狙いながら、純株式より守備的に取り組みたい場合
- 株式のボラティリティを部分的に緩和したい場合
2. 仕組債(Structured Notes)
定義と位置づけ
金利・為替・株価指数・個別株・コモディティ等にデリバティブを組み込んだ債券。表面利率が高く見える一方、元本・クーポン・償還時期が条件次第で大きく変動します。
代表的なタイプと条件例
- 株価連動/EB(株券参照):参照株が一定のノックイン(例:初期値の60%)を割り込むと、元本毀損や株式納入で償還
- インデックス連動(範囲指定):指数がレンジ内なら高クーポン、外れるとクーポン低下・早期償還不成立
- 為替連動:円が一定水準より円高(円安)に振れた場合、受取金額や通貨が変動
- 金利連動/デジタル:金利の範囲・上限下限でクーポン決定
- クレジット連動(CLN):参照企業等に信用事由が発生すると元本毀損(CDSに類似の経済効果)
注意すべき確認ポイント
- 参照資産・観測方法(終値/終値平均/期中観測)
- バリア水準(ノックイン/ノックアウト)と観測日
- 償還金額の計算式・早期償還(オートコール)の条件
- クーポンの累積性/非累積性、通貨、手数料・スプレッド
- 二次流通の価格透明性(中途売却が不利になりやすい)
活用の場面
- 条件を定量的に理解し、確率分布で損益を評価できる投資家
- 単純な「表面利率の高さ」ではなく、想定損失の深さと発生確率で判断できる体制がある場合