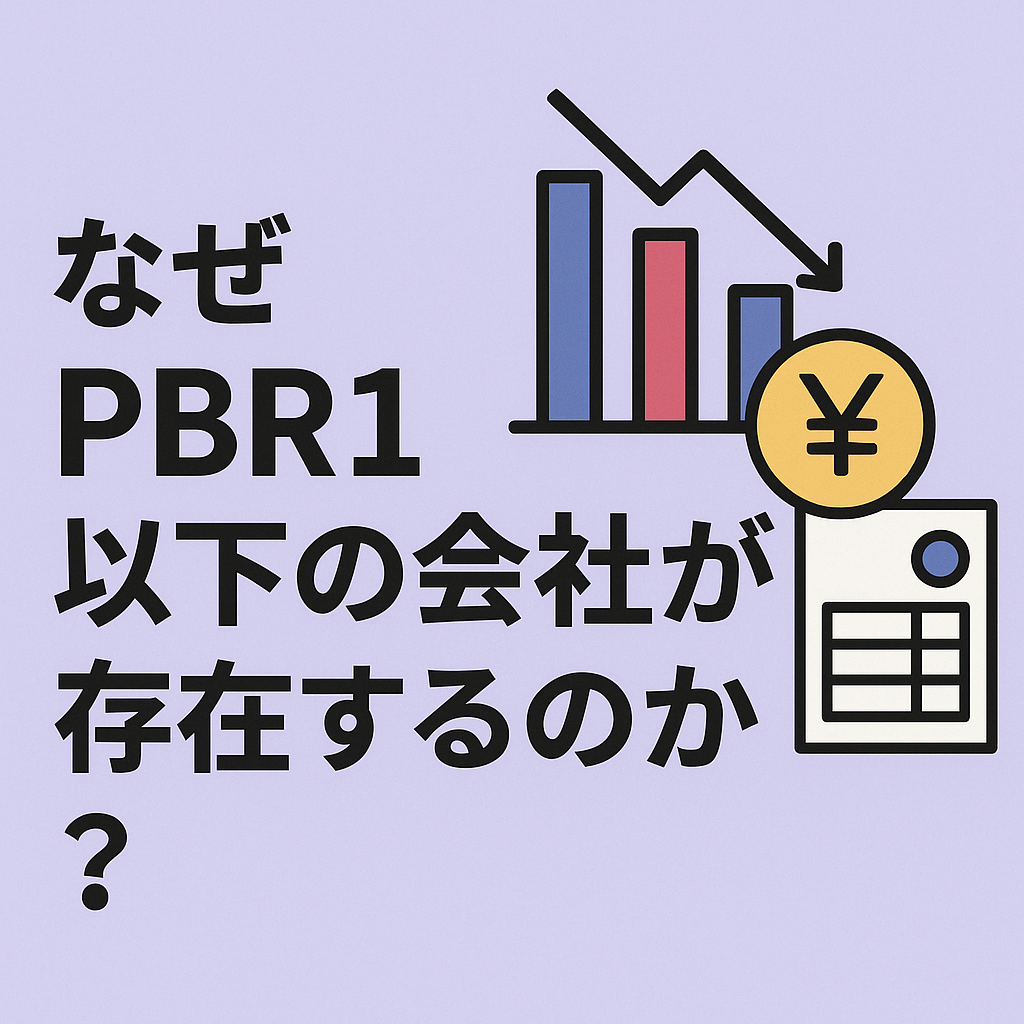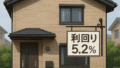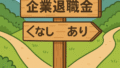はじめに
投資を始めたころ、私は、PBR(株価純資産倍率)1以下の企業への株式投資は損しないはずなのにと思い、PBR重視で株式投資を行っていました。
もちろん、そんな短絡的なことは株式市場ではありえず、今は、私も少しは賢くなり、安定している相場では株価にすべての情報が込められているというように考えるようになっており(効率的市場仮説)、PBRは会計の問題で時価と乖離することが普通で、それぞれの会社のPBRにはきちんとした合理性があると考えています。
今回は、「なぜPBR1以下の会社が存在するのか」について整理してみたいと思います。
PBRとは何か
PBRは、株価 ÷ 1株あたり純資産(BPS) で計算されます。
つまり、「会社が持つ純資産を株式市場がどう評価しているか」を示す指標です。
- PBR1倍:市場は会社の純資産を簿価通りに評価している
- PBR1倍以下:市場は純資産の簿価を過大とみなし、割り引いて評価している
- PBR1倍以上:市場は純資産以上の価値を見込んで評価している
簿価と時価のギャップ
会計上の純資産(簿価)と、投資家が考える実際の市場価格(時価)の価値には大きな差が生じます。
- 会計基準では、土地や建物、機械などは購入時の価格(簿価)を基準に、土地以外は減価償却で計上
- 市場参加者は、それらを使って企業がどれだけの利益を出してくれるかどうか(=収益性,将来性)や、実際に今の市場で売るとなればいくらの価格で売却可能か(=換金可能性)で評価
たとえば、東京では地価が上昇しているので、簿価が時価よりも安く、バブル期に買った地方の土地などは、簿価よりも実際の取引価格は随分と下がっていることはよくあります(注:会計上は減損処理が求められることもあります)。
また、実際に1億円の価値の純資産であっても、それを使って経営陣が1憶でその資産を売却するよりも大きな利益を上げてくれるなら、株価は純資産に比べて大きく上がります。
PBR改善要求(東証の動き)
日本では長らく「低PBR企業」が多いことが課題視されてきました。
2023年、東京証券取引所は上場企業に対して資本効率改善を要請しました。
具体的には:
・PBRが1倍を下回っている企業に対し、改善策を検討
・開示するよう要請自己資本利益率(ROE)や資本コストを意識した経営を促す
・株主還元(配当や自社株買い)の強化や、成長投資による資産の有効活用を推奨
つまり投資家から「資産を眠らせるな」という圧力が強まり、企業経営にも変化が求められているのです。
日本における業種別PBR比較
業種によってPBRの水準には大きな差があります。以下は日本株(TOPIX構成銘柄)をベースにしたおおまかな傾向です。
| 業種 | PBRが低い例(1倍未満が多い) | PBRが高い例(2倍以上も多い) |
|---|---|---|
| 銀行業 | 約0.4〜0.7倍 | ー |
| 保険業 | 約0.5〜0.8倍 | ー |
| 不動産業 | 約0.5〜0.9倍 | ー |
| 鉄鋼・造船 | 約0.5〜0.8倍 | ー |
| 商社 | 約0.7〜1.0倍 | ー |
| 情報通信 | ー | 約2〜4倍 |
| 医薬品 | ー | 約2倍前後 |
| 半導体・精密機器 | ー | 約3〜5倍 |
| サービス業(IT・人材) | ー | 約2〜6倍 |
(数値は2025年時点の市場水準を参考にした目安)
傾向
- 低PBR業種:銀行・保険・不動産 → 資産は大きいが収益性や成長性が低いと評価されがち
- 高PBR業種:IT・医薬品・半導体 → 将来の成長や高収益性が期待されるため、資産以上に評価される
PBR1倍以下は割安か?
PBRが1倍以下だからといって「お買い得」とはいえません。
本当に、純資産以下の時価総額であれば、市場は放置しないので、PBR1以下にはそれなりの理由があると考えるのが大事だと思っています。
投資家が確認すべきは:
- PBRが1以下かどうかは別に重要ではないと認識。(自戒を込めて)
そのうえで、
- 業種的にPBRが低いかどうか。
- 企業として、改革し、資本効率(ROE)が上向く施策があるか
- 成長性や株主還元策が実行されているか
こうした動きが伴わなければ、低PBRは「割安」ではなく「割安に見えて当然」なのです。
まとめ
- PBRは簿価と時価のギャップを示す指標
- PBR1倍以下は市場が資産の活用度や収益性を低く評価しているサイン
- 東証は低PBR企業に改善を要請しており、今後の経営改革が注目される
- 業種によってPBRの水準は大きく異なり、金融・不動産は低め、IT・半導体は高め
かつての私は「PBR1以下なら絶対に損をしない」と考えていましたが、今では背景を理解することが大事だと痛感しています。
補足:日本の会計基準における不動産の評価
原則:取得原価主義
- 日本基準でもIFRSでも、基本は「取得時の価格(原価)で計上し、その後もその価格を基準に処理する」という原則です。
- したがって、通常は不動産(土地・建物)の簿価を時価にあわせて修正することはありません。
例外:時価に修正するケース
- 減損会計(必須)
- バブル期に購入した土地のように、著しく価値が下がった場合には「回収可能価額」まで簿価を切り下げる(減損損失を計上する)必要があります。
- ただし「値上がりした場合」に帳簿を上げることは原則認められません(日本基準)。
- 不動産の時価開示(注記レベル)
- 日本基準では、投資不動産については貸借対照表には取得原価で計上しますが、注記として時価を開示することが求められています。
- つまり「帳簿価格と実際の評価のズレを投資家が把握できるようにする」ルールはあります。
- IFRS(国際会計基準)との違い
- IFRSでは「公正価値モデル(時価評価)」を選択可能で、時価に基づいた評価に修正することが認められています。
- そのため海外企業では、不動産を時価に近い形で評価しているケースも多いです。
- ただし、日本基準では依然として「原価主義」が原則です。
まとめ
- 原則:不動産は取得原価で計上(時価に引き上げはしない)。
- 例外:価値が著しく下がった場合は減損処理が必要。
- 注記:投資不動産については時価情報を開示する義務がある。
- 国際比較:IFRSでは時価評価を選択できるが、日本基準では原則不可。