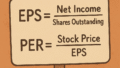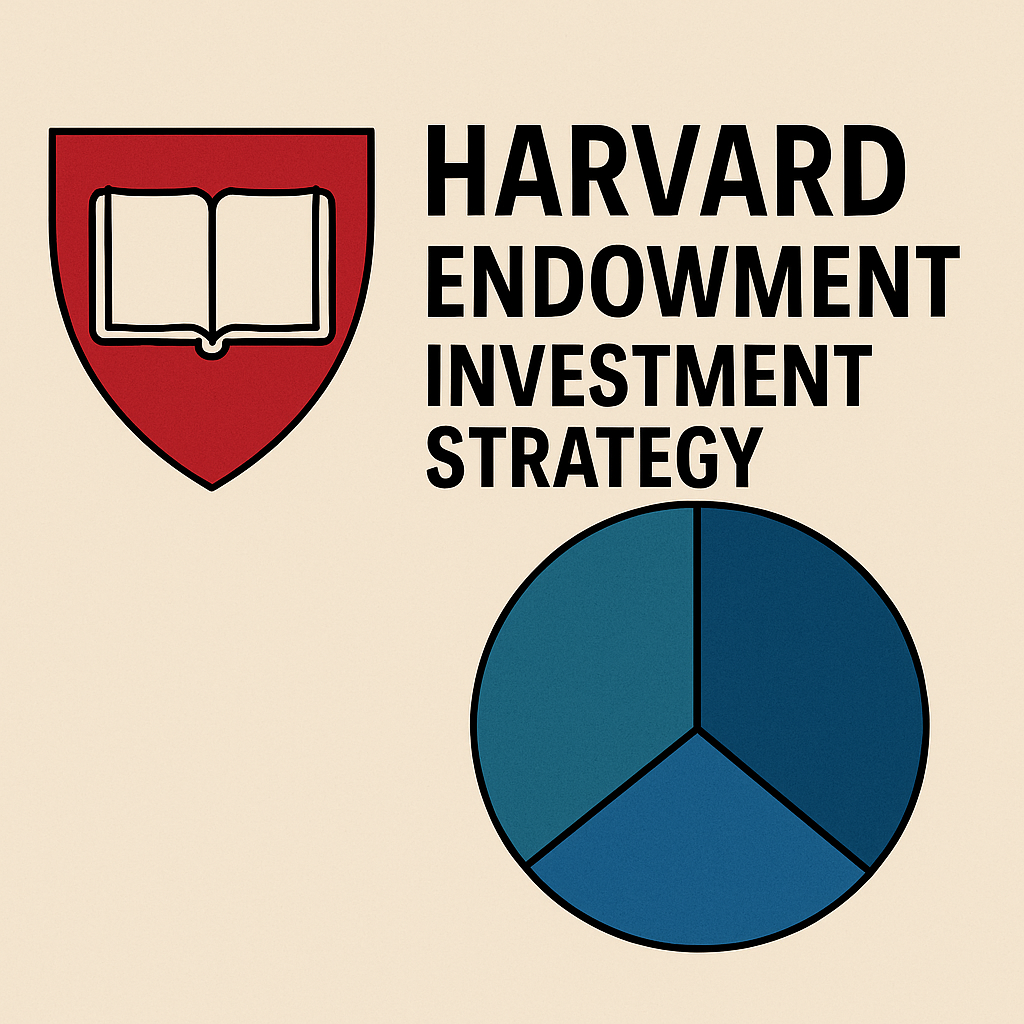オルカンが「王道」になった背景
ここ数年、個人投資家の間で「オルカン」(全世界株式インデックスファンド)ないし「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」への積立投資が王道という流れが定着しつつあります。背景には、故・山崎元氏をはじめとする識者の活動や、SNS・書籍を通じた情報発信があると思います。 私自身も、勉強している中で、特に数年前くらいからは、長期的に資産形成を行うなら、オルカンで十分だと考えており、私の株式ポートフォリオの核はオルカンです。オルカンは、世界中の株式に分散投資でき、低コスト、長期的な成長に乗れるという点で非常に合理的であろうと考えています。
証券会社が打ち出すメッセージ
証券会社にとってオルカンは多くは売れるものの、手数料が低く、薄利多売状態で、ビジネスとしてはあまりうまみがないように思います。そのためか、最近よく見られるのが、「オルカンは良い。でもそれだけで大丈夫?」という新しいアプローチです。
証券会社としては、正直オルカンを否定できるものなら否定して、手数料の取れる投資信託を宣伝したいのだろうとは思いますが、今の状況を考えると、オルカンを否定するより、オルカンを認めたうえで、+αが必要じゃないですかという感じで、+αを販売しようとする戦略を取り入れてきたように思います。 オルカンだけで大丈夫?と銘打ったうえで、「ヨーロッパ株」や「インド投資」「新興国株ファンド」を勧める流れは、この戦略に沿ったものだと思います。
「オルカン+α」に潜む落とし穴
資産の最大化を狙うなら、オルカンだけでなく、一部の地域やセクターへの投資を加える戦略をとる必要はあると思います。最近、ヨーロッパ、東南アジア、南米というのが、次の投資候補として有望という意見をよく耳にするようになっていますので、このあたりのETFや投資信託を勧めるのは自然なことかと思います。
ただし、目的があやふやなまま「オルカンだけだと劣後するかも」という不安を煽られて、何かを購入するのには注意が必要です。本来その人にとって必要のないリスクを取り、上昇したならいいのですが、損失を出したときには、その判断に対して後悔することになると思います。
まとめ:
オルカンは、老後資金づくりの「土台」としては非常に優れていると思います。そのうえで、追加投資を行うなら、「不安だから」ではなく、自分が投資する最終的な目標を忘れず、「自分の目的とリスク許容度」に基づいて検討するべきだろうと思います。
私の場合には、20年も株式投資をやっている割に、投資の勉強の仕方・順番がいびつでして、日本の個別株から初めて、アメリカ高配当ETF、最後にインデックス積み立てに辿り着いたという進み方です。今も日本の個別株とアメリカの高配当株ETFは持っています。数年前から、インデックス投資を知ったため、SP500の積み立てを始め、やっぱり全世界の方がいいなと思い、今はオルカンをメインで積み立てています。
日本の個別株・アメリカの高配当ETFを持ちながら、SP500少々とオルカンをメインに積み立てを続けている状態で、シンプルではないなぁと思っているのですが、ひとまずはこれでいいかとも思っています。投資の目的が、基本的には老後資金なので、資金が必要になるまでの時間が15-20年とみているので、今のものはそのままに、オルカンをメインとした積み立てでいいと思っています。