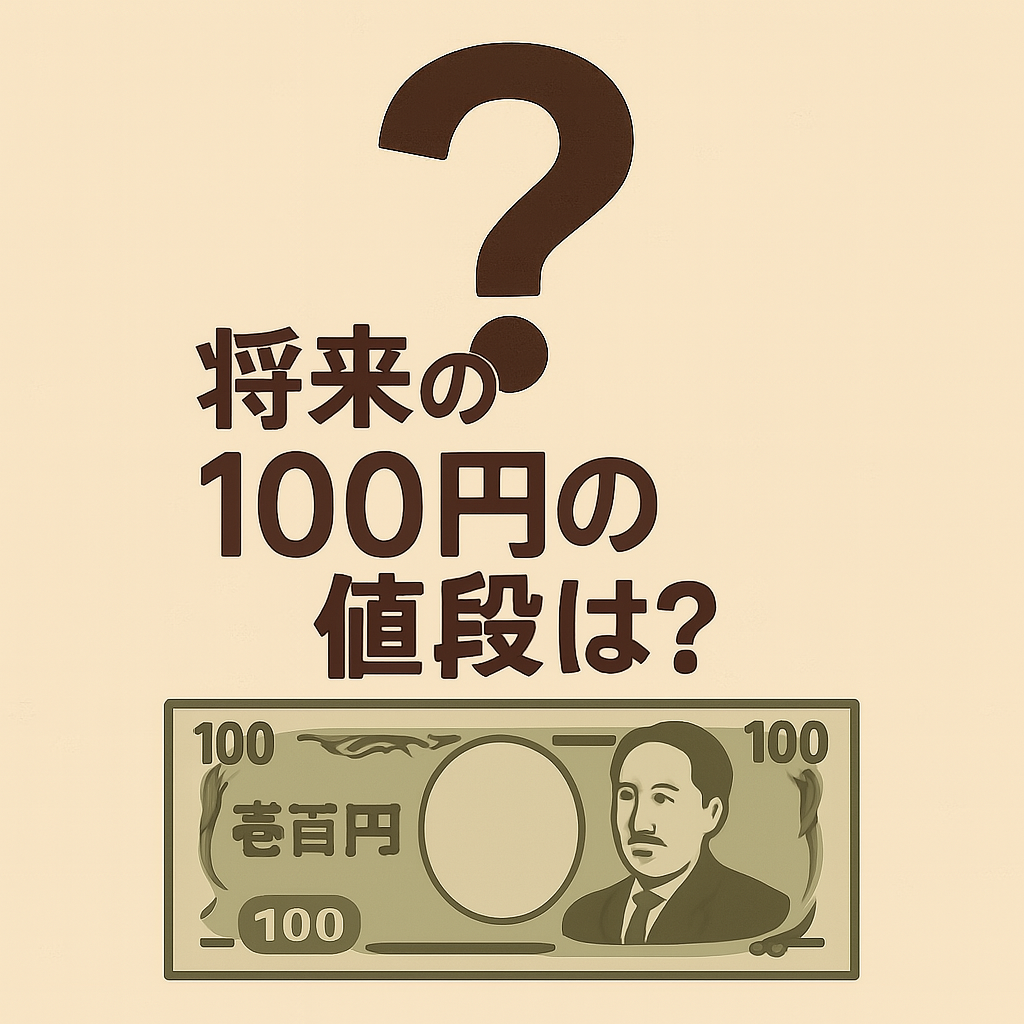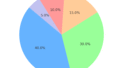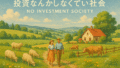初めに
投資を始めたころに、「現在価値」という考え方が、お金のことを考える上で重要だなと思いました。
ざっくりいうと、「100年前の100円」と「今の100円」の価値は違う、時間の経過とともに、同じ100円という額面でも実際の価値は異なってくるということ。
インフレ率など影響を与えるものを考慮して、10年後の100円には、今いくらかの価値があるのかということが、現在価値ということになります。
たとえば誰かがこう言ったとします。
「君が僕から10年後に100円を絶対にもらえる権利を、今いくらなら買う?」
あなたはその“約束”に対して、今いくらまでならお金を払ってもいいと思えるか?
この「将来のお金に対する今の値段」を考えるのが、現在価値という考え方です。
また、投資は未来の価値に対して今お金を出しますので、投資するということは投資先の未来の価値を今いくらと値付けするのかということになります。
【1】未来のお金には「値段」がある
だれかに10年後に100円あげる権利買ってよと言われたとします(もらえることは絶対に保証されているとする)。10年後までに物価が上がっていると、物価があがるということはお金の価値が下がるということですので、100円という金額は同じでも、10年後の実際の100円の価値は低下しているということになります。
だから「10年後にもらえる100円」には、価値の低下のリスクがあるわけです。
【2】未来の100円を“今ならいくらで買うか”という考え方
ここで登場するのが「現在価値」という概念。
10年後に確実に100円もらえることが確約されていたとしても、その権利を今100円で買ってしまうのは「割高」な気がしませんか?
じゃあ、今いくらなら、その“10年後の100円”を買ってもいいのか?
これを考えるのが現在価値です。
言いかえると、
🔍「将来にお金をもらえる“権利”を、今いくらなら買うのか?」
を判断するための考え方です。
世の中は基本的にインフレです。インフレ率を予想することが必要になりますが、簡単に考えるためにインフレ率2%とすると、インフレはお金の価値の低下ともいえるので、お金の価値が1年後に2%低下するとも言えます。つまり、1年後の額面100円の現在の価値は、98円になります。2年後はさらに98円の2%減少した96.04円になり、以下、年数分これを繰り返していくことになります。すると、10年後の額面100円の現在の価値は、82.03円になります。
ある種の債権は、この現在価値をもとに、10年後に100円に交換できる債券を、例えば、50円で販売したりしています。一般的な利率5%の債権なら、毎年5%(税引き前)もらえますが、50円で販売されている債権は毎年の利率はもらえませんが、実際には、単利で10%、複利で7.2%の債権であるといえます。
【3】現在価値は、投資や企業の値段にも使われている
このような現在価値の考え方は、企業買収や、株を買うといった判断をするときの基本になっています。
たとえばある会社が、今後5年間、毎年1億円の利益を出すとしましょう。
その会社を買うとすれば、「5億円で買ってもいい」とはなりません。
なぜなら、予定通りなら額面1億円ずつを1年後、2年後…と受け取るとしても、1年後に1億もらえる権利と、5年後に1億もらえる権利では、同じ将来の額面1億円でも事業の不確実性とインフレによる価値の減少のため、同じ1億円でも価値は異なります。細かい計算は一旦置いておいて、インフレによる価値減少や事業・利益の不確実性などを元に利率を決めて、1年後の額面1億円の価値を算出、さらに2年後、3年後、4年後、5年後の価値を同様に算出してそれを足し合わせます。
その5年分の計算した現在の価値を足し合わせた金額が企業の“現在の購入価格”になるわけです。
これが、M&Aなどで使われる**DCF法(割引現在価値法)**の基本的な仕組みです。
DCFは利益ではなく、キャッシュフローで計算していたりと違いはありますが、大きな考え方は同じです。ただ、実際には、何年後のキャッシュフローまで足し算するのか、インフレ率を含めた価値の減少を年何%に設定するのかは、いくつかのよく使用される計算式やモデル式などはありますが、何パターンか幅をもってシミュレーションして、最終的に責任者の判断で、これでいくと決めているように思います。(大手コンサルではもっと複雑な計算式があるのかもしれませんが、収益で10億単位の売買では、えいやで決めているのをみていました)
【4】株価も「未来のお金の値段」である
株を買うことも、突き詰めれば将来の利益や配当をもらう“権利”を今のうちに買っておくという行為です。
つまり、株価というのは、
「この会社が将来生み出す利益を、今いくらで買うか?」
という市場の判断が反映された“価格”なのです。
成長企業ほど未来にたくさんの利益をもたらすと期待され、その未来の利益が大きければ、今の値段も高くなります。逆に成長が鈍化すれば、「今はそんなに払えないな」となって、株価が下がることも。
このように、株価もまた「未来のお金の現在価値」と言えるのです。